終戦時の陸軍病院で
栃木県 福田 ミチ
病院の空襲
私は旧宇都宮第一陸軍病院の従軍看護婦でした。
昭和二十年八月に入り空襲も頻繁に成って参りました。薬庫、被服庫、食糧庫と連日小型爆弾が投下され、逃げ遅れた衛生兵が直撃を受け、手・足は吹飛び、内臓破裂で空をにらみ無念の形相で即死しました。
そのもの凄さ、防空ごうの中で唯傍観するのみです。精神病患者が一人とび出したため、艦戴機に発見され、キューンと音が聞えたと思った瞬間、急降下して機銃掃射です。
病棟の屋根は穴だらけ、桜の大木は横真一文字に穴があき、バリバリと大音と共に倒れていきました。
連日の空襲で、担送ごう(担架のまま入る防空ごうのこと)に入り放しの患者は傷の手当も受けられず、傷口からはウジ虫がポロポロと落ちてくる有様です。
度垂さなる空襲で、遂に院外待避の命令が出ました。伝染病棟勤務だった私は、食事療法で体力のない患者を引卒して院外に出ましたが、かけ足が出来ませんので待避も遅々として進みません。艦戴機に発見され機銃掃射です。道路わきの川にとび込み、隙をみて川からはい上り再び逃げる。波状攻撃をかけてくる。敵機は又機銃掃射です。なかなか目的地に看きませんでした。
夜明けの待避でしたが、夕暮れまで食糧はとどかず、やっとおにぎり一個にありついた時は夜に成っていました。内地にあっても野戦病院さながらの状態でした。
終 戦
八月十五日終戦、天皇の玉音を拝聴して病室にもどると、垣根越に師団司令部の内務班があるのですが、そこから号泣する兵士の声が聞えてきます。私たちも泣きました。その夜、初年兵をいじめぬいた上官たちは袋叩きにされ、ゆるしてくれと叫んでいる様子があちこちで見られました。その様子もすさまじいと表現してよいのか、二十歳だった私にはショッキングな出来ごとでした。
その夜、私は四十二度の発熱、院外待避が続いたため完全消毒ができず、チフスに催ってしまいました。
内務班休養でしたが、勤務に追われる看護婦達は同胞の看護をする暇もありません。自分で洗面器を持って水を汲みに行くのですが、内務班に帰るまでに水はこぼれて洗面器の中には三分の一位しか水は入っていません。頭を突き込んでいました。診察もなく、意識不明寸前でした。こんなことで死にたくない、死にたくないと何度も口に出して言いました。
終戦を心配して、三日がかりで切符を手にしたと言って面会に来てくれた姉に名前を呼ばれ、よかったと安心した私はそのまま脳症を起してしまい、気が付いた時には病室におりました。姉のお陰で九死に一生を得たわけです。手遅れで死んだ軍医もおりました。
民間人のチフス患者が続々入院して釆ます。手遅れで一夜にして十数人の死体をみとったこともございます。軍隊の町宇都宮市内は全焼でした。六畳一間に焼い弾八個の割合で投下されたそうです。
南方から栄養失調の兵士
南方から栄養失調の兵士が入院してきました。食事時は大騒ぎです。内地に帰ったのだから白米を食べさせろ、漬物が〇〇兵より一切れ足りない、大きいの小さいのとつかみ合いの喧嘩、配膳するのに苦労したものです。栄養失調症には、始めから並食を食べさせると消化不良を起して死んでしまうのです。どんなに説明しても飢に苦しんできた兵士には理解出来ないのです。駆虫剤を飲ませればトイレはゆでめんをぶちまけた様な回虫の山。入浴時には貧血を起し浴槽に浮き上がる。首にさげてる、垢で太くなった認識票の紐、不潔だからはずしなさいと言えば、飯がもらえないと泣き出す有様です。認識票が無ければ食べ物がもらえなかった捕虜生活が頭から離れないのです。この姿を見た時、私は胸が痛くなりました。
民間人が被服庫を夜襲する
民間人が被服庫を夜襲する。下士官が食糧庫から缶詰をトラックで運び出す。市内では夜中にドラム缶泥棒、横倒しにしてゴロゴロところがして運ぶ音しきり。師団司令部に進駐軍が駐屯してから進駐軍の砂糖を盗み出し、病院のこわれた塀の穴から逃げ帰る進駐軍勤務の日本人。残務整理を終えて身の丈より倍もある荷物を背負って復員してゆく兵士。白衣の兵士が義足をわざわざ見せたり、黒メガネをかけて街角や映画館の前に立ち、傷い軍人の名をかりて募金箱を首からさげ、募金したお金を神社の陰で山分けしている兵士。これが敗戦日本の人間模様の一コマです。
私はチフスに躍った
私はチフスに躍った時、高熱のため左の耳が中耳炎になっておりましたが、多忙のため治療が出来ず、痛さを堪えての勤務でした。左耳は今全く聴えなくなってしまいました。戦後四十二年経った現在、中耳炎の後遺症の頭痛、耳鳴りに悩まされております。過労のため結核も患いました。日本国民が愛国の名のもとに堪え忍んで来たあの悲惨な生活、陸軍病院でも常食はコーリヤンの赤い御飯でした。故郷ではジャガ芋、さつま芋、芋ずる、大豆を御飯がわりに食べていると思うと、まだましなんだと自分に言いきかせて食べたものです。
今日、物資はあふれ
今日、物資はあふれ、使い捨て、物の大切さを忘れている若者を見るにつけ、苦しかった戦時中が走馬燈の様に脳裡に浮んできます。戦時中の話をすると、体験者のノスタルジアに過ぎないと一笑に付されたこともどざいます。ノスタルジアにしては余りにも辛い悲しい体験でした。
再び戦争を起こしてはいけないのだと言うことを、後世に残しておく義務が私共にはあると思うのです。
1988.2月 朝風1号掲載

父の戦災死
-昭和二十年六月七日-
枚方市 岡野 弘
空襲警報
この日は朝から早やばやと警戒警報が出たかと思うと、すぐに空襲警報のサイレンがけたたましく鳴り渡った。
大東亜共栄圏の建設を旗印に掲げて、鬼畜米、英国を相手に昭和十六年十二月八日ハワイ真珠湾奇襲攻撃の大東亜戦争をしかけて、既に足かけ五年目に突入していた。
商業学校生として入学した最初の一年間は日々の軍事教練と並行して、それでも英語のリーダーや英作文の授業もあり、支那語も少しずつ習い始めていたが、二年生に進級してから敵国語は習うなと、外国語の授業はすべて打ち切られてしまった。
風雲は急を告げている。戦局にあわせるように、大学生も中学生も学徒出陣、学徒動員と、若い肉体と魂を消耗品の如く召し出し、狩り出されていったあの過去。人間を弾よけとしたあの悲しい悲しい過去の現実。
動員された軍需工場の中庭に掘られた防空壕の中で、足をかかえ小さくなって、私も工員達と一緒にうずくまっていた。
キューン、キューンという鋭い金属音が、耳をつんぎく轟音が、連続で壕の天井を貰いて伝わってくる。誰れかの大声が怒鳴る。「艦載機の大編隊が低空で飛んで行くぞ」怖いもの見たさで、私も外へ出て空を見上げた。頭の真上を機体もあらわに、何組ものB29爆撃機が、グラマン戦闘機が、大編隊を組んで次ぎ次ぎと機首を大阪方面へ向け、東へ東へと低空で向かっているではないか。
敵機来襲
ドーン、ドーンまたドーン、ドーン、この不気味な腹の底までこたえる遠雷のような地響音が、昼を回るまで続いたのである。
動員先の阪神千舟工場から見た大阪の空は悪魔の空であった。紅蓮の火焔と火の粉、空一面を蔽う黒煙で、東の天空は真黒に荒れ狂っていた。親父はこの日、艦載機の銃弾で死んでいた。昭和二十年六月七日の事であった。
この大阪大空襲の後、阪神電車も阪神国道線も全部ストップしてしまった。帰宅したくとも帰るに帰れない。その時、動員先の千舟工場から、梅田方面へ会社のトラックを出すというので、従業員の人達と一緒にそれに便乗して大阪へ向かった。
大阪に近付くにつれ国道二号線は大混乱である。このままでまともに大阪に入れない様子を察知した運転手は道を替え大阪の西側でどんどん南方面へ下り、それから御堂筋へ出て北上する方法をとった。
御堂筋は修羅場地獄
御堂筋を北上するトラックの荷台から見た大阪の街は、誠にものすごい修羅場地獄であった。黒煙が地上を覆い卑し、火の粉が熱風にあおられて舞っている。通過して行くいく筋かの川の橋という橋には、甘い物に異黒く集る蟻のように、無数の人間が群衆となり黒い回りとなって悲鳴を叫び乍ら、当てもなく揺れ動いて助けを求めているのである。
すさまじい火災と火焔の熟さの為に、水を求めて川の流れる橋に集まり来たったのであろうか。
国鉄大阪駅東口の阪急百貨店西側の広場にやっとの思いで着いた。トラック貨物荷台の上から見たものは、つんときつく鼻を突く累煙が煙幕になって広場を流れる中に、ここでも避難場所を失って右往左往うごめいている人達であった。
眼の前に、阪急百貨店西側五、六階の窓々からすさまじい火焔も噴き出し燃えさかっている光景があった。
天六方面の道筋も、扇町へ向う道路の行く手も、火の粉を天に噴き上げ舞い上げて、燃え盛っているではないか。地上も天空も一面火炎と黒煙で覆い尽くされている。到底これ以上前に進めそうにない。
街全体が焔を上げ猛火猛煙の中で悪魔のような熱気を噴き立てている。こうして立っている体が、ぐにゃぐにゃとろけ出すような熱さである。
火の粉と火煙が熱風を作り出し、またそれがぐるぐるまいにあおられて舞い狂っている。さながら地獄とはこんな形相なのであろう。無数に投下された油脂焼夷弾が、大阪を完全に灰墟に焼き早くしているこの状況。夏の太陽をねばっこい黒煙がおおい隠して、さながら阿鼻叫喚の地獄の夜を作り出している。
「おい君 帰れるかいな」
「いや、天六も扇町も燃えているから行けませんねん」「仕方がない。それやったら、今夜は会社の寮でも泊って、明日帰ったらどうや、そうし、そうし。」
「そんならすんませんけど、そうさしてもらいます。会社まで引き返すのん車に乗せてもらいます。お願いします。」
会社の寮に泊まる
親切な会社の人が誰であったのか分からない。我が家に帰れそうにない何人かの人と、また会社まで引き返したのである。
阪神国道線歌島橋の佃工場の寮に帰り着いた。寮生に支給される夕食を私もいただいて、誰の部屋であるのか知らないが、その部屋に用意して下さった布団に小さくなってもぐりこんでしまった。別に何も用もなし、明日電車が動くかどうか不安な気持のまま、早くから寝床に就いてしまったのである。
翌朝、早く眼を醒まして様子を聞くと、矢張り電車は全面ストップしたままで、運転再開の目途も立っていないらしい。帰宅する方法は歩くしかない。
配給制になっている貴重なお米も、こうした軍関係の工場にはまだあるのだなあと、羨ましく思いながら、寮から出してくれた朝食をそこそこに食べて腹ごしらえをすます。
阪神国道沿線沿いに野田まで歩いて、そこから天六方向へ道を辿る。その辺から道路ぎわの電柱がすべて焼けただれて、ごろごろと道端に横倒しに投げ出され倒れている。人家も町もなく一面に茶色い瓦礫になってみな焦土と化していたのであった。
”何と一夜にしてものすごいことになったものだ“一体これが家が並んでいた町であるのか。立ち辣んでしまう。
ぶすぶすまだくすぶり続ける煙が、瓦礫の山と化した焦土の上を這うように流れている。建物は何も無い。無残に焼き早された焼け跡が、がらくたや汚泥をぶちまけたように広がっているのみ。油脂焼夷弾のきつい鼻をつく異臭が焼け跡を蔽う。
焼け転がっていた死体
ふと足許にころがっている丸太のようなものは何だろう。近寄ってよく見る。焼け焦げた人の死体ではないか。少し気味が悪いが気を取り直して附近に眼をやると、同様なものが眼に付くではないか。
″わぁ-これだけ町全部が燃えたのだからきっと逃げ遅れたのだろう。可哀想に“思わず手を合わせたが、体ごと眼をそむけてしまった。一面の焦土からぶすぶす異様なくさい煙がまだ噴き出ている。
焼け落ちた瓦礫で、道路は塞がれ細く狭まっている。それでも、その焼けただれた無残な道を歩くしかない。天六までどうにか出て来た。体が、焼跡から出ている熱気で、何だか暑くなっている感じがする。天六の交差点でトラックが止まり、大勢の人達が、周囲からトラックの荷台に乗り込んでいる。
「どこまで行くんですか。都島へ行きたいのですが」
「そうか、都島も通るから乗ったらいいぞ」
よかった。助かったとすぐタイヤに足をかけ飛び付く。上から手を引っ張って貰い荷台へ引き上げてもらう。
焼け野原の都島
トラックの荷台から見た所、天六交差点附近は、新京阪電車のビルもその前の蔦におおわれた北市民会館も建っている。天六商店街の入口付近も無事な様子だ。
少し安堵感が湧く。ところがトラックが都島大橋を越えようと一番高いアーチの頂点に来た途端、眼を疑うばかりの光景の出現に愕然となる。
余りの驚きに声も出ない。都島の街並全体全く何も無いではないか。見渡す限り、先刻見て来た焦土が、見事なまでに広がっているのだ。
何一つ遮蔽物のない先に、国鉄城東貨物線の古い高架の璧がわずかに円弧を描いて遠くに見えている。一望千里の焼け野原とはこのことだろう。一綱打尽に燃え上がって焼き尽され見渡す限りの眼を覆う無残な潰滅的な焦土の残骸であった。廃墟の世界であった。
何とむごい。心が震え上がる。気が遠くなりそうである。茶褐色一色の廃墟に、街路だけがぼんやり白く痩せ細って残っている。都島本通り交差点でトラックから降りた。
我が家は瓦礫
我が家は都島本通り五丁目三十番地であったが、もう跡形もない。瓦礫と化していた。
大阪には大空襲がまたあると噂があり、少しでも被害を少なく安全を考えた父は、旭区北浦水町に借家を借りて家具等を疎開中であった。トラックの調達が出来ないので、大八車という荷車を借りて毎日自力で疎開荷物を運搬していた。
こうした事情があったので、京阪電車千林駅近くの北清水町のその移転先へ行けば家族の様子が分るだろうと考え、硝煙くすぶる都島の道を歩き出した。
この時偶然、同じ本通五丁目の並びで、餅菓子店の商売をしておられる矢倉さんのおじさんと出会った。「弘ちゃん、これで日本もおしまいやなあ……戦争は負けや」 とつぶやくように言われる。”何だこの人、非国民やなあ″私は声には出さなかったが、そう胸のなかで憤満を漏らす。
日本は神国であり、戦争は絶対に負けない。きっと神風が吹いて必ず勝つのだと幼な心で盲信していた。そんな健気な軍国主義に洗脳された子供になっていた。
今この惨状を目前にしても、まだ私には戦争の本質と結び付けて考える思想的成長は出来ていない。真白い童心は見事に何色かに染められてしまっていた。
足を引きずりやっとの思いで北清水町の移転先へ帰り看いたが誰もいない。表戸は締っている。どうしたものか、腹もペコペコで疲れもひどい。ペたりと服のまま玄関口に座りこみ、何時かうとうと眠ってしまっていた。
無事な母と姉
母と姉の声で眼を覚ました。空襲の最中、父は荷車を返しに行くと言って、母と別れたきりまだ帰ってこないことを知る。その為、今日一日中、二人で父を探して都島のあの焦土の中を探し歩いて来たのだと言う。二人共疲れもあるのだろうが、どうも口数が少ない。焼け跡で数多くの死体を見たのに違いない。二人の様子から疲労だけでなく、可成りショッキングだったことが伺える。
いつもの雑炊の夕食で空腹を押え、駅前の銭湯で汗を流し、早々に莫暗い寝床に入る。翌日は黒い大粒の豪雨。空襲の大火災のあとでは、必ず黒煙と灰を含んだ黒い大雨が降ると噂が流れていた。この土砂降りはそれであろう。
父の遺体を探し当てる
三日目、三人で父探しに出る。都島本通五丁目と六丁目の北側四ツ辻の道路に、空襲後の死体が二十数体並べてある。母親達と再度一体一体見て行くが父らしい遺体は無い。
都島工業学校で都島区役所の係が出張して、臨時の窓口を開き、戦災死亡者等の登録受付け事務をしていると聞いてそこへ行く。母が父と別れた際の状況などを細かく説明して、父の戦災死亡証明書の交付を受ける。これで父のお弔いは、一九四五年昭和二十年六月七日の大阪大空襲がしてくれたと言う結果になった。棺桶のお世話にならずに、父は集団で葬られたことになる。
「あれ、これうちの自転車と違うやろか」校門の前にずらっと並んで置かれている自転車の中に、私は家で使用していた自転車を見つけた。
「そうや、間違いないわ。これお父さんが乗っていた自転車やわ」
それから私達がその自転車をよく見ると、タイヤカバーの金属板の泥除けに、前車輪のカバーに二ケ所、後事輪のカバーに三カ所、直径二センチ位の六角形に撃ち抜かれた穴を発見した。この穴は、戦闘機からの機銃掃射が命中しているのだと思った。
父は自転車で避難中に、きっと米艦載機の銃弾を浴びて死んだのに違いないと判断せざるを得なかった。
雑然とした人込みの中で、三人は涙も出なかった。
朝風記念文集掲載 2003.12月

風船爆弾
金沢市 福岡 重勝
極秘の「ふ号作戦」即ち風船爆弾」
昭和十九年、戦況はサイパン守備隊玉砕、グアム、テニヤンの日本軍全滅など我が方の暗いニュースが 伝えられても、あくまで損害軽微と虚偽の報道を繰り返す大本営は、総力を挙げて徹底抗戦を国民に強制し続けていた。
この年の九月東京在住の私に予期していた召集令状が届いた、私は二十五歳で独身、両親は未だ五十歳台で老人の域に入らず、従って全く後顧の憂いも悲壮感もなく若者らしい大胆不敵の心境で、勇躍千葉県東部七六部隊に陸軍兵長として入隊した。この部隊は砲兵科に属する「気球連隊」との事であった。
昭和十五年から三年間を北支派遣軍歩兵砲隊の精鋭と自負して討伐作戦に明け暮れて、十八年暮に同年兵七百名余と共に現役満期除隊となった私は内地にこんな珍しい部隊の存在を初めて知った。軍隊生活の経験者として未知の部隊へ入隊すると言うことは 大いに興味もあり内地の部隊では先ず命を落とすこともないだろと古参兵らしい図々しい態度で入隊した。
同時入隊者約二千名は関東、東北地方出身者で昭和二年~十五年徴集の召集兵で兵科、階級、年齢も種々雑多、年配者の中には見るからにひ弱な体格で今後の軍隊生活に耐えられるかと思われる一つ星もいた。郷里に妻子を残して来て心配だ早く帰りたいと実感を洩らす者、名前を呼ばれても返事のない難聴の人、機械に指を挾まれて自由の利かない準身障者などいかにも内地の残余の兵隊の寄せ集めの感があり、これが当時の日本軍隊の実態であった。
入隊後の一の宮海岸での気球に関する教育訓練は一ケ月を要した。この間この部隊は極秘の「ふ号作戦」即ち風船爆弾」の放球部隊と教えられた。
晩秋から冬にかけて太平洋上の亜成層圏には最大秒速七〇メートルの偏西風が吹き荒れていると言う、薄暮から払暁の無風時を選んで、気球をこのジ ェツト気流に乗せてアメリカ大陸まで飛翔させる。 途中気象の変化や水素の漏洩などにより気球が下降すれば装置が感知し備え付けの砂袋が落下してその軽みにより再び上昇し飛翔を続ける。五〇~七〇時間でアメリカ木土に達し搭載の爆弾が投下され同時に気球と装置は自動的に燃焼炎上し証拠一切残らないと言う仕掛けである。奇抜と言うか、奇想天外と言うか日本人の考えそうな作戦である。
この作戦の目的は広大なアメリカ大陸の彼方此方に連続的に山火事が起こり住民は何処からどの様にして爆弾が炸裂したのかと恐怖心を抱かせ心理的効果を狙った神経戦といえる。当時はこの部隊は名誉あるアメリカ本土攻撃部隊であり偏西風は「神風」だ、風船爆弾はこの戦争の決戦兵器だ、これで日本は勝てるとまで信じ込ませて、我々を暗示にかける教育をさせられたのである。
気球の放球場所
この気球の放球場所は千葉県一宮、茨城県大津、福島県勿来地区の一帯であり各地区に六百~八百名が配置された。大本営直属部隊の所為か支給された被服、装備はすべて新品ばかりで、特に軍衣袴は物資不足の時節に拘らず贅沢な羅紗製であった。一の宮基 地は風が強いので周囲、高さともに二〇メートルの防風壁を建てた。大津、勿来基地は小高い山に囲まれているので天然の風除けとなり、また機密を保つ上にも絶好の場所であった。
さて、私は大津基地に配属された。この一帯の山中は軍が既に開墾整備を進めていたらしく水素ガス発生工場や数基の巨大ガスタンクも設置され、松林の中に点在する粗末な土窟式三角兵舎が我々の内務班であり、窓は偽装樹葉で覆われ天井は低く薄暗くジメジメした赤土の上に丸太で組んだ板上にムシロを敷いた寝台で起居する事になり洗面、洗濯、食器洗いは谷川の流れを利用した。
中隊長は砲兵大尉でその言動には威厳もあり現役将校の貫禄充分に備わった人であったが以下の将校、下士官、兵に至っては全て召集兵であり、野戦で鍛えた古参兵もおれば、三ヶ月の教育召集を受けたのみの新兵もいて全くの寄り合い地帯である。内務班では年上の新兵が若僧の古参兵の世話をするという日本陸軍特有の悪弊が罷り通っていて悲喜劇が随所に見られた。
「この部隊は大本営直属で唯一のアメリカ本土攻撃部隊である。誇りをもって軍務に精励し内地に在る留守部隊として国民の期待を裏切らないよう一層努力すべし」とは基地を視察した侍従武官の訓示でありまた連隊長の士気を鼓舞する癖口であった。しかし一部の古参兵グループは少しも動ぜず上官の命令には直ちに応ずるという厳正な態度は見られず率先して物事に当たる事もなく、きつく命令されると「班長さんよ、お互いに野戦で苦労してきた召集兵じゃないか。要領よくお手やわらかにたのむぜ」といった調子で班長も苦笑する始末だ。軍隊では「上 官の命令には絶対服従」という鉄則があるがここでに通用しないのだろう、軍隊生活の裏表を熟知して いる古参召集兵の集団では軍規も乱れ伝統的な帝国陸軍の権威も崩れ、自由奔放な生活を送り、上官に対する欠礼や、服装の乱れは日常茶飯事であった。
現役時代は内務班や演習で追いまくられ、無抵抗の初年兵を私的制裁で殴り絶対服従の精神を叩きこんで、無思索、無批判の兵隊を作り上げられた当時とこんなに違うものかと今度の応召でつくづく感じ た。
放球開始(気球打上げ )
十一月に入りいよいよ放球開始(気球打上げ ) の時期となった。一個の気球を三十名が操作する、吊り紐(麻ロープ )は十九本あってそれぞれの吊り紐 に操作兵がつき、その他気球に水素ガスを充填する者、高度保持装置を取り付ける者、爆弾を装着する者それぞれの担当が割り当てられる。この時ばかりは古参兵、新兵が共に協力して真剣に準備に取り組んだ。気球に関してはみんなが初体験なのである。
小隊長の「撃て!」の号令で風船爆弾の第一号が 放球台を離れると、その成果を期待して浮上する気球を見上げて一同感激の一瞬である。気球は毎秒五 メートルの速度で垂直上昇し四〇分後には一万メー トルの上空に達し偏西風に乗って目的地(アメリカ) に向けて飛翔する。気象状況がよければ引き続き連続して発射される。
各基地、各中隊が一斉に打ち上げるので数十個の気球が舞い上がり恰も落下傘部隊のようなまことに見事な景観である。これは防諜上極秘の作戦であるが数キロ離れた遠隔地からも望見できるので近くを通過する列車は鎧戸を閉めさせた。又近隣の住民は公然の秘密をしゃべれば憲兵や特高の厳しい目が光っていた。
このようにして晴天無風の日が続けば昼夜の別なく放球が続けられる。しかし状況が悪ければ内務班待機となり、次の放球日まで英気を養うよう休養の時間となり、故郷に便りを書く者、被服の手入れや洗濯をするなど、又碁、将棋に興ずる者、果ては賭博を開帳するなど正に自由時間である。
こんな生活が続くうち昭和二十年を迎え、日本の都市が次々と空爆をうけて壊滅する事態となった。 我々も放球の合間に岩間の防空壕堀りや海岸の蛸つぼ堀りの作業にも就いた。
四月となり偏西風の終期と共に風船爆弾の打ち上げは終わった。第二次大戦中に日本から八千キロメートル離れたアメリカ大陸に超長距離爆撃を敢行したのはこの部隊のみで世界史にも珍しい事実として記録されているようである。
三百個がアメリカに到達したと言う
この期間中に打ち上げられた数は九千個、このうち三百個がアメリカに到達したと言う。その被害は僅少と聞いているが山火事が起こったり、送電線に被害があり死亡者も出ているとのニュースも聞いた。オレゴン州にはこの記念碑が建てられているそうであり、ワシントンの博物館には不発で落下した風船が展示され深い関心を集めているようである。しかし、これが当時の金で一千万円以上を注ぎ込んた作戦の全戦果であったとは作戦に携わった我々として聞くに忍びない。ただ軍が密かに計画していた生物兵器の搭載は研究半ばにし挫折したことは何より幸運と言えるだろう。もし細薗兵器が完成していて気球に使用されていた場合、風船爆弾は無差別殺戮兵器として取り返しのつかない歴史上に大きな汚点を残すことになっただろう。
五月、任務を終えたこの部隊に転属命令が下った。大津地区の八百名は関東、東海地方の沿岸警備に移動することになった。私は他の四十名と共に今秋から再開される放球作戦の準備要員として残留することになった。基地内の建物の巡回警備、保管物資の整備点検など気楽な軍隊生活を送ることになった。
六月一日、陸軍伍長に任官した。既に断末魔にあえぐ大本営は沖縄を見捨てて本土決戦の準備に狂奔していた。この頃敵機の空襲は益々激しくなり制 海権、制空権を確保したアメリカ艦載機は悠々と低空で飛来し地上の動くものすべてに機銃掃射を浴びせた。ここ大津の漁港の町にも付近に軍事基地があるという事で数回の来襲があり民家が被害を蒙った。おかげで住民は大いに迷惑した事だろう。敵機の来襲があっても何一つ応戦もできない軍隊では正に戦意を喪失した腰抜け部隊で烏合の衆に過ぎないだろう。
新型爆弾が投下
八月七日、私は任官して初めて衛兵司令の任務に着いていた。夕刻巡回に来た週番司令から広島に新型爆弾が投下され全市が一瞬にして壊滅したと聞かされた。新型とは一体何だろう、超大型爆弾か、細薗を含んだ爆弾か、殺人光線の類か等々議論続出で衛兵所は被害を憂慮する一方好奇心で深夜までざわめきが続いた。これはウラニユムを使った放射性の原子爆弾と聞いたのは二日後であった。そして長崎も同じ被害を受けたと言う。これでは戦争もそろそろ終わりに近い予感がした。八月十五日、運命の日、この日は珍しく敵機の来襲が無かった。正午に重大発表があると言うので全員が広場に集まりラジオで天皇陛下の詔勅を聞いた。雑音入りの上に難解な語句であったが降伏、敗戦を直感した。兵舎に帰る兵の足どりは重く皆が無言である。しかし内心は「これで敵機から逃げ回ることもないだろう。どうやら生きて帰れる、アメリカ軍は何時くるのだろう、故郷の家はどうなっただろう」が実感であり、無念さと安堵かが交錯して複雑な気持ちであった。事態がこのようになれば一日も早く家に帰りたいのは皆同じだろう。
降伏
降伏による武装解除の準備が始まった。移管物資(兵器、機材、被服等一切の軍事用品 ) を占領軍に引き渡す作業は先ず小銃の菊紋章の削り取り、特殊 爆弾や精密兵器の破壊埋没、或るいは海洋投棄、機密書類の焼却などこれらは敵機の偵察を警戒しながら夜間に行われた。こんな毎日が続くうち食事の量は大盛りになり、休憩時には甘味品まで支給され久しく経験したことのない満腹感を味わい一同の顔にも明るい笑顔が戻ってきた。これは部隊が解散するにあたり経理部や炊事係の計画した厚意であろう。
部隊が解散するとなれば倉庫に備蓄してある食糧や物資が兵隊達によって次々と持ち出されたが、こんな無秩序状態を誰も止めようとしなかった。先日まで「徹底抗戦」を叫んでいた将校までが人夫を使って大量の物資を持ち出したり、兵器係の下士官がガソリンを満載してトラックごと運び出す悪行もあった。
待望の復員
二十九日待望の復員の日が来た。どの顔も満面の笑みを浮かべ嬉しさを隠せないようである。敗戦のドサクサに紛れて掻き集めた貴重な復員土産を背負って故郷に帰る我々は恥曝しの敗残兵であるにも拘らず、凱旋兵を思わせる錯覚を覚える。この部隊は敗戦後いち早く部隊を解散し復員を行った。それは細菌兵器を搭載する計画を察知したアメリカ側が極度に恐れていた秘密部隊であったからだろう。
戦争は敗戦の憂き目をみたが、国民は滅私奉公の精神で行動した。そんな中で若くして敵弾に繁れたり、馴れない土地で病魔に侵され世を去った幾多の戦友や遺族の心情を思う時深い悲しみを覚える。我々は戦前の日々を懐古する時無駄の無い日常生活だったと思う。今日の豊かさや自由さを誰が想像しただろう。
我が国の現在の発展と平和は国の礎となった戦友達や我々の青春時代の苦労が基礎になっている事を子供や孫達に、しっかり伝え残したいと思っている。 (完)
朝風記念文集掲載 2003.12月
--------------------------------------
風船爆弾は、日本の攻撃によってアメリカ本土で唯一の死傷者がでたとして、ずいぶん騒がれたようです。 "balloon bomb" で検索しますと、ずいぶん多くのサイトが検出されます。その中の二つをご紹介します。
1945年5月5日、オレゴン州で、風船爆弾による6人の死者の死亡を確認した森林警備隊員の体験記
http://www.oldsmokeys.org/Links/BLY%20BALOON%20BOMBS.htm
犠牲者の夫の談話を報じるシアトル・タイムズ紙の記事
http://www.stelzriede.com/ms/html/mshwfug2.htm

白木の箱
別府市 和泉 徴
昭和十七年夏のこと、松山市の西部六十二部隊に在隊中、遺骨受領の命令を受け戦友数十名と共に広島県宇品港に出張、南方より送られてきた名札付きのそまつな木箱に入った南方戦線散華者の遺骨を受領した。
そまつな木箱から正式の白木の箱に移しかえるため木箱を開いてみると、遺骨の状態は戦線の状況を如実に物語っていた。
戦線後方の野戦病院等で死亡した者は、丁寧にダビに付されたきれいな白骨であるが、戦線が先に伸びるにつれて黒ずんだ骨片に変わり、更に前線に行くとダビに付する余裕もなくなるためか箱の中味は簡単な所持品(印鑑、万年筆等)に変る。
ある箱を開いてみると、我々が軍隊用語でギューカンと呼んでいた牛肉の缶詰の空き缶が一個入っている。中をのぞくとロウ状のものが詰めてあり、中に何やら妙なものが入っている。眼をこらすとギョッ!根本から切断された小指である。緊迫した最前線ではダビに付するいとまも無く、急拠戦友が右の防腐処置を施して後送したものと思われる。
さらに前線に進むとそれもかなわず、箱の中は何もない空っぽなのである。
問題はその空の箱の処置である。遺族の心情を思うとき、空の箱を渡すのは何としても堪えられぬ。鳩首協議の結果、死なば共にと誓い合った戦友同志の間柄、たとえ他人の遺骨であれ供養されれば同じことではないか。遺族を悲しませるのは何とも堪えられぬ。英霊への冒とくにはあたるまい、英霊も冥してくれるのではないかと他の箱から分骨することに決定した。遺族をあざむく行為におののきながら震える手で白骨を空の箱に分け入れ、絶対他言無用を誓い合ったのである。
この行為の是非は未だに心に決めかねており、終生いえることの無い心の傷として残っている。
その後、絶えて遺骨受領の命令は受けたことはない。船舶運行はひっ迫し、遺骨を後送する船腹の余裕は無くなったのである。
ちなみに同行した戦友たちは、昭和二十年沖縄戦で玉砕して果てた。そして遺族の元には遺品はおろか一片の遺骨も帰らなかった。
文字どおり、海ゆかば水潰く屍、山ゆかば草むす屍、空ゆかば雲むす屍と化した悲惨な結末を迎えたことは衆知のとおりである。
この件は固く口外を控え胸の中に納めていた秘事で、戦死者への冒とく、遺族に与えるショック等を考え公表することに悩んだが、文集「朝風」が戦争の罪過と悲惨さを後世に語りつぐ趣旨に賛同し、この件も戦争の一側面と、行を共にした無き戦友に代り敢えて一文を草したものである。
遺族各位お許しあれ。
英霊の鎮魂を念じ、二度と再び「白木の箱」の復活無きことを祈念して筆をおく次第である。
合 掌
1988.5月 朝風2号掲載

慟哭の岬
浜松市 吉岡 芳郎
岬を訪れる人よ わが故郷に告げよ
われらは眠る この海の彼方に
祖国の平和と 残せし人を想いつつ
われらは眠る とこしえに
なんという悲しい詩なのだろ。
これは、ある戦没者慰霊碑の表面に刻まれることになった鎮魂の詩である。その稗は、北海道釧路市近郊、厚岸(あつけし)町海岸のアイカップ岬にある同町々立公園、筑紫恋の浜に建てられ、昭和六十三年八月二十六日、その除幕式が行われる。
昭和十九年二月十九日夜、私が入営して間もない初年兵だったころ、仙台歩兵第四連隊の現役古参兵の大部分が、北方戦線を目指して出発して行った。それから一か月も経たない三月十六日夜、その人達を乗せた輸送船日蓮丸は、敵潜水艦の攻撃を受けて沈没。三千余名の将兵は、流氷の漂う酷寒の海で、祖国と故郷に思いを馳せつつ無念の戦死を遂げた。
しかし、それから何日かの後、なんと、それらの戦死者の中の十数名の遺体が、軍装姿のままで北海道の海岸に漂着したのである。その海岸こそ、冒頭の慟哭の詩が刻まれた慰霊碑が建てられることになった、北海道厚岸海岸、愛冠岬の、ツクシコイの浜である。
当時、軍は固く事実を秘匿し、そのため、奇跡的に漂着した遺体も、その身元さえ確かめられることなく、地元の正行寺という寺に、人知れず埋葬されたそうである。
戦後四十数年、遺族ら遂にそれを知り、北海道厚岸の浜辺に集う。ときに昭和六十二年八月。遺体の帰らなかった遺族にとり、釧路厚岸の海は、夫が父が兄が息子が、静かに眠る聖地である。漂着した遺体が埋葬された正行寺には、北海道の木、オンコで造られた木柱慰霊碑が建てられた。そのときの遭族の一人の挨拶-
「夫が戦死して以来、いくたびか夫の夢を見た.貴方は今どこにいるのと尋ねても、なんの答もない。このたび厚岸を訪れ、遥か海の彼方に眠る貴方に会えた。ごんな日本の近くにいながら、なぜ貴方は今までそれを私に教えてくれなかったの」-と。
これが契機となり、今夏、道東の桜とつつじの名所、愛冠岬に立派な慰霊記念碑が建てられる。
募金目標額は四百万円。私も心をこめて、貧者の一灯を捧げる。
思えば太平洋戦争は日本の国力を超えた戦いであった。彼我の国力の差が歴然とした昭和十九年以降は、日本は速かに矛をおさめるべきであった。それをしなかったところに、数限りない悲劇が生れた。多数の陸兵を乗せた輸送船が、その目的地への到着以前に、アメリカ側の空と海からの攻撃を受け、遂に多年の猛訓練の成果たる一弾をも発射することなく、恨みを呑んで大海の藻屑と消えた.このような戦死を遂げた陸軍将兵の無念は如何ばかりであったろうか。
昭和十九年秋に、水戸市外の陸軍航空通信学校を私と共に卒業した三百六十人の幹部候補生の仲間の九割近くが、やはり輸送船の沈没による戦死をしたそうである。
運よく内地に残された私は、敗戦とともに復員。その後四十数年、徒らに馬齢を重ね、彼らの三倍も長く生きている。この上は生ある限り、生き残った者の務めとして、彼らに代って戦争の苛酷さと愚かさを後世に伝え、人類最大の愚行たる戦争の、再発防止を訴え続けて行かんのみ。
ここでもう一度、あの悲しい鎮魂の詩を唱え、二度と再びこのような詩を作らないで済む平和の世の、とこしえに続くことを祈る。
岬を訪れる人よ わが故郷に告げよ
われらは眠る この海の彼方に
祖国の平和と 残せし人を想いつつ
われらは眠る とこしえに
(文中、一切の敬語を省略。お許し下さい。)
1887年7月 「朝風」3号掲載

渦潮の悲劇
別府市 和泉 徹
終戦を旬日余にひかえた昭和二十年八月二日早朝。
淡路島に要塞構築の命を受けた宝塚海軍航空隊甲種飛行予科練習生の一隊は、機帆船二隻に分乗し、徳島県撫養港から一路淡路島の阿那賀港目指して出港した。
折も折、渦潮を以てなる鳴門海峡の真只中を航行中、突如中天より襲い掛かったグラマン戦闘機数機から嵐のような一斉銃撃を浴びせられた。
鉄火の洗礼を浴びた一瞬、船内はこの世の地獄と化し、船はあえなく炎上、辛うじて被弾を免れた僅かな生存者は渦潮逆巻く鳴門の海中へ…。
終戦を旬日余に控えていようとは、神ならぬ身知る由も無く、悲憤の涙を飲んで鳴門の渦潮に散った幼き戦士は、その数八十二柱。最年長者にして十八歳、最年少者に至っては僅か十四歳に過ぎなかった。
遺体は、淡路島の阿那賀港附近に漂着、収容に当たった村人たちは、戦死者のあまりにあどけない幼な顔を見て絶句したという。
俳優山口崇氏は、この事件の数少ない目撃者の一人で、阿那賀出身の氏は、当時小学校五年生だったという。
太平洋戦史の片隅に、世に知られぎるままに消えた戦争悲劇の一コマである。
私の弟も この中にいた一人である。享年わずか十五の若さで散った。
星霜移って昭和三十九年の初夏、ゆかりの地淡路島阿那賀の高台を切り開き、桜ケ丘と名付け、広く浄財を募って八十二の墓石を建てると共に、口ぐちに母親の名を呼びつつ息を引きとった少年戦士の霊を慰めるため、高松宮妃の題字を頂き、慈母観音像を建立した。
老松の繁るこの高台の突端を鐙ケ崎といい、過ぐる源平の昔、戦に敗れた平家の公達どもが、己が悲運を嘆いて自らの鐙を巌頭から鳴門の渦潮めがけて投じた処と伝えられている。
これが鐙ケ埼の名の由来であるが、なにか因縁めいたものを感じられ、涙を誘われるのである。
運命の無情か、戦の非情か。
臨終の際に口々に、母の名を絶叫しつつ悲運に倒れし童顔未だ去らざる幼き戦士八十有二。
墓前にぬかずき、その心情を思うとき、滂沱とあふれ落ちる涙を抑うる能わず。
源平のかみ、平家の公達が鎧の袖を絞りしと聞く鐙ケ崎の岩頭に立つとき、名にし負う鳴門の大景観は眼下に一望、鳴門の潮騒と松籟はむせぶが如く訴うるが如く、粛々と我が耳を打つ。
み霊よ、慈母観音の慈悲にすがり、とく故郷の母の懐に帰れ。慈母の懐に抱かれ、とこしえに安らかに眠れと祈るのみ。
星霜重ねること今や四十三年。毎年五月二十七日を期し、生き残りの戦友遺族相集いて墓前に慰霊祭を挙行す。少年戦士の恋慕いし慈母も大方は鬼籍に入り、年を追うごとに参列者の数少なきを悲しむ。
誌友諸氏、淡路を、訪ねたもう折あらば、願わくば墓前に一輪の花、一掬の涙を供し賜らんことを。
袖しぼる 鎧ケ崎の潮騒を 涙の鎮魂歌と 我は聞くなり
合掌
1988年11月 「朝風」4号掲載

ああ、豊川海軍工廠挺身隊
筆者・三樹 敬
提供・本多まさ子
豊川といえば、お稲荷さんの街で昔から通っているが人口は三万たらずの田舎であった。昭和十四年に「豊川海軍工廠」が建設されてからは、一躍「工廠の街」となり、昭和十九年には、人口は九万二千と膨張した。
工廠の規模は、敷地約六十万坪、建物七万坪、当時の建設費八億円、従業員は軍人軍属をはじめ徴用、志願、学徒、女子挺身隊、年少工、養成工など最盛時六万人を数え、うち約三割が女子であった。
九六式二五粍機銃一万五千挺ほか、九三式十三粍、九二式七・七粍等、全海軍の八割近く、又機銃弾の薬包四百万発その他、信管類二〇万個を生産していた。また測距儀や高角砲の射撃装置等も生産した、我が海軍の最重要武器生産工場であったのである。
余談になるが、昭和十三年に海軍がこの土地を購入した値段はいくらかというと、豊川市史に次の如く記されている。
「一平方メートルにつき、北部の松林地帯は六十銭、南部のよい所でも二円乃至三円であった」総工費八億円が、いかに巨額なものであったかの想像がつくのである.なお、昭和十九年に九万二千人にふくれ上がった豊川市の人口は、戦後五万人弱となり、昭和三十年で六万人、爾来漸増して五十五年の国勢調査で十万三千九十七人となっている。
ところがである.昭和二十年八月七日午前十時半、米軍B29の大編隊が突如、来襲し、数千の爆弾、焼夷弾、機銃弾が投下されたのである.何しろ集中生産の現場、しかも銃弾薬包の現品の有るところに、強烈な爆撃を食ったわけだから、たまったものではない.廠内は一瞬にして、文字通り修羅の巷と化し、阿鼻叫喚、この世の地獄となり、軍人軍属はもとより、女子挺身隊、年少工に至る尊い命二千五百余を奪ってしまったのである.その惨状は目を覆しめ、混乱の状況は筆舌の及ぶところではなかったのである.
広島、長崎のすさまじい原爆に世人が驚愕したのに対し、豊川工廠のこの戦慄の実相が、案外、世間に知られていない.この爆撃で犠牲となった学徒は四百六十四名、国民学校の児童も五十四名が含まれているという悲惨さであったのである.
この実況を実録の中から若干取り上げてみたい.。
現在豊川市の市長である山本芳雄氏は、昭和三十八年から連続四期市長を勤めた生粋の豊川人であるが、五十四年に「市制あれこれ」という随筆集を発刊された。市長自身、豊川工廠の機銃部に勤務していて、九死に一生を得たのであるが、次は「紫陽花の色さめて」の一文である。
「アジサイの花の色がさめて、夏の空に入道雲がわく八月になると、わたしはいつも悲しいあの日のことを思い出す。終戦の年の八月七日、豊川海軍工廠が一瞬のうちに消し飛んだ、物凄い夏の日の被爆の光景である。
真の日の太陽を、ある人は赤かったといい、別の人は黄色かったといい、また別の人は黒かったと言う。みんな嘘ではない。
巻き上がる砂塵により、真夏の太陽は、赤く、黄色く、黒く変わっていったのだ。 屍山血河、凄愴言語に絶する大惨事、第二次大戦における最大の悲劇であった。
爆撃当日、工廠の防空発令室の放送員をしていた石井計記という人の「海軍工廠最後の日」が豊川市史にのっている。
「私は、清水中将をはじめ総帥郎の人々を残して、死の防空発令室から地上に脱出した。地上の光景は地下で想像していたより遥かに凄惨なものであった。真夏の明るい筈の天空は濛々たる土煙で赤黒くおおわれ、燃え広がった火焔は、すさまじい熱風を呼んで渦巻き、時を忘れて咆哮する高射砲のうなりに和して、形容し難い様相を呈していた。しかも、それらの間を恐怖におののく人々が、必死になって逃げ回っているのだ。
爆風で跳ね飛ばされた鉄帽に、鮮烈な血があふれていた。白い片腕が落ちていた。
顔が真二つに割られた首があった。首のない胴体があった。海軍道路の木の枝に若い女の生首が髪の毛で引っ掛かっていた。足を失った年少工が真っ黒な顔をして両手ではい回っていた。どの顔も死の形相にゆがんでいた。
懸命に逃げて、安全地帯に身を置き、振り返ってみれば、工廠の一帯は凄絶な火の海である。寄宿舎の畳が木の葉のように舞い狂い、誘爆は相次いで発生し、その轟音は豊川海軍工廠最後を思わせる断末魔のうめき声とも聞こえた。
空には超低空でP51 十数機が魔鳥のように旋回していた。」と。
豊田譲という作家が「空母信濃の生涯」という戦史物に「ああ豊川女子挺身隊」と題して、このことにふれている。
「横須賀の挺身隊に東北出身者が多かったのに比べて、豊川は北陸出身者が多かった。
そして空腹の辛さと作業の苦しさは同じであったが、豊川の少女たちの運命は、横須賀より苛酷であった。八月七日の大空襲で、工廠の全火薬が爆発し、彼女たちの大部分は犠牲者となったのである。
この日、豊川海軍工廠を襲ったB29は計百三十機、投下された爆弾は二百五十キロで三千発、一トン爆弾二発。被害は即死二、四〇〇名、重傷三千余名、軽傷六千数百名と。
広島の爆弾投下は八月六日、長崎が九日、日本中の、いや世界の眼がこの二地区に向けられていた丁度中間の七日の出来事であった。
戦争の悲惨さは、勿論どの地区でも変わりはないのであるが、豊川工廠の場合は、限定された工廠の謂わば塀の中で、しかも火薬頬の充満した地域に、一時間に亘り爆弾、焼夷弾、機銃弾が無数に投下されたという意味で、これは又特殊の悲惨を呈したのである。
豊川稲荷の裏手に稲荷公国という緑の美しい地域があるが、その一角の広場に立派な石造の供養塔が建っている。
これぞ、豊川海軍工廠戦死者を祀る供養塔で、昭和二十一年九月、工廠従業員生存者一同が、挺身国難に殉じた英霊二千余柱の冥福を祈るため、献金と汗の奉仕により竣工したものである。塔の側面には、ギッシリと英霊の名前が刻まれている。勤務別に区別されており、学徒は学校別に整理されている。中でも涙を誘うのは、国民学校の児童の名前である。
会計部の戦死者は殆どが女子であるが、これは当時の賃金計算ソロバンの名手達であろう。
工廠の生存者で「八七会」という会が結成されており、毎年八月七日に法要が営まれる。八七会の「供養塔の由来」というパンフレットに次の如く記されている。
「因みに塔中には戦死者名簿と廠内縁りの土を納め、各工場の石定盤に戦死者氏名を刻し、台座周囲に組み、以って永久の冥福を祈るものである。」と。
雨の日でもお参りができるように、ローソク、マッチ、線香などがきちんと保管してあり、お花も常に新しい。昨年は八七会の会員と自衛隊の協力により、全長百五十米の参道も完成した。因みに八七会の本部の調査で、豊川海軍工廠戦没者は総計二、五四四名になっており、その内訳は地域別では愛知県が一、一六九名、静岡県が三三一名で次が長野県の一一四名となっている。
男が一、五四五名、女が九九九名、そして学徒が四五二名も数え、女子学徒が何と二五八名の多きに達している。本稿の題名を「ああ、豊川海軍工廠挺身隊」とした所以もここにあるのである。
日本海軍の機銃及び弾薬包の八割を生産し、多くの挺身隊員が日の丸の鉢巻きをしめ、乏しい食料に我慢して、その青春を死を以ってかざった豊川海軍工廠六十万坪の跡地は戦後どうなったか。
自衝隊豊川駐屯部隊が一角にある。当時の海軍将校クラブは豊川市役所となり、物資部は郵便局に共済病院跡は警察署である。日本車両その他の大企業も数多い。
自衛隊豊川駐屯部隊の隊内に「資料館」があって、昔時の海軍工廠の資料や爆撃当日を物語る幾多の遺品、模型などが陳列されていて胸を打たれる。小野一曹という隊員の中の篤志家がコツコツと蒐集されたものだそうである。
また何よりも、このあたり、供養塔、稲荷公園、緑町、桜木町から佐奈川の堤、駐屯地の門前から市役所にかけての「サクラ」の美しさはどうだ。「昔、海軍さんがサクラに錨ということで、このあたり桜を沢山植えたが、五十年後の今日この様に開花しました。」と、古老に聞いたことがあるが、日本中にこれ程立派な桜の名所はあるであろうか。
多くの挺身隊員の死が、桜となって生まれ変わって来たのではないか、と錯覚されるのも筆者の感慨であろうか。
豊川の人々は奥ゆかしい。海軍工廠の惨事も日本中に喧伝されなかった。否、原爆の凄まじさの陰に隠れてしまった。そしてこの桜の開花の美しさも、ついぞ国鉄の「花どころ」としてポスタ-となったこともない。
心ある人は、あの太陽のギラギラする八月七日に、豊川に来て海軍工廠戦没者の供養塔に花を捧げられよ。さらに春には、佐奈川堤の爛漫たる桜花をめでたまえ。 おわり
1990.6月 朝風7号掲載

沖縄戦の前線で斗った者として
桑名市 近藤 一
わたしは昭和一五年に入隊し、三日後には中国に渡った。「お国のため」とか「満州は日本の生命線だ」と、なんの疑問もなく思っていた。しかし中国に渡り内地で報道されている事と、まったく違うことを肌で感じた。
「勝った、勝った」というが、実際に占領しているのは点と線だけだった。八路軍と交戦したが、かれらは統制がとれていた。
あるとき八路軍が村民を通して日本の負傷兵を戻してきた。我々の場合、捕虜にしたらみな殺していた。
共産軍は、どこかが違うと思った。
そして昭和一九年八月に沖縄に渡った。私の所属していた石部隊は最初から最前線だった。陣地は変わりづめで、作戦もどんどん変わっていく。
蛸ツボを堀り、一〇KG爆弾をかかえて米軍戦車に突っ込むといったこともやらされた。
沖縄では負傷しても歩ければ戦斗に出なければならなかった。わたしの部隊二〇〇人中、生存者は一一人だった。
それでも戦争が終わり、憲法もでき、これで平和の国になれるという思いと、生活に追われ、保安隊ができたり、自衛隊となっても、疑問をもちながらも、原爆の犠牲もあるし、まさか戦争はやらないだろうと思っていた。
いまから一二年前に教科書問題がおこり「沖縄で日本軍は住民を守らなかった」ことが出された。まったく知らなかった。自分が沖縄に行った兵隊であることが云えなくなった。最前線で戦ったものとして沖縄住民を殺したとは信じたくなかった。
戦後に知ったことだが、後方の軍司令たちば個室に住まい女が一人ずついて、うまいものを食いちらしていた。かれらは最前線で火災で真っ黒になりやられほうだいやられている歩兵の姿を、ー目でも見ていたらと思う。沖縄の住民の方に迷惑をかけぬ戦斗ができたと思う。
国を守るというが、住民を守るのではなく、ただ体制側を守るために、一日でも長く戦斗をのばすことだったのだ。
やはり一二年ほど前慰霊のため沖縄にいったとき、バスガイドが当時の牛島司令官の切腹を美化する「黎明の塔」について説明したとき、黙っておれず、その説明をさえぎり、「最前線の兵士からすればけっして立派な司令官ではなかった」と云った。
沖縄戦が間違って伝えられている事を強く感じた。後方にいた連中が、まるで自分が沖縄戦を戦ったように云っている。
沖縄戦は、日本政府によって沖縄そのものが、そして、兵士そのものが捨てられたのだ。捨てた側は、ノホホンとして生き残っている。天皇がいい例だ。
それからいろいろな場で話すようになった。
いま「国際貢献」がいわれるが、戦前の「生命線をまもれ」と「五族共和」の言葉がダブってくる。徴兵制は必ずやるだろう。
経済大国になったという。しかし庶民のくらしはどうか。湾岸戦争で一三○憶ドルもだしているのになぜ老人ホーム一つが満足にできないのか。
世界から孤児になったら困るというが、アジアから孤児になったら困るのだ。
朝風14号掲載 1994.4月

「残念だ」の一言残して ~長崎、痛恨の日の思い出~
町田市 伊藤 鶴代(当時一八才)
長崎に近い大村にいた私は、連日連夜の空襲警報に睡眠不足の目をこすり、黒ずくめのモンベ姿で軍歌を歌いながら、一路軍需工場へ通うのが日課であった。途中で米軍機が突然雲間から急降下、私達はてんでに土手にへばりついたり、鉄橋の下へ隠れたりして難を逃れた。すでに二一航空廠は爆撃を受け、仮工場が分散していた。本廠空襲の時、逃げ遅れた鹿島高女生が機銃で大地に縫付けられ、清純な血は飛行場の土に吸われ少女達は絶命した。
あの日も田んぼの中の工場で紫電改(飛行機)の部品作りをしていた。十一時過ぎ、工場内に一瞬の閃光! 続いて大地をゆるがす爆発音、沈黙の中に不安な顔、顔、顔が、目と目をぶつけ合い、作業台の下へ身を寄せた。シーンとした空気を奮わせて、老工場長の緊迫した声。「新型バクダン、全員タイヒ-」
間髪を入れず外へ飛び出した。異様な空に紫、桃、青と不気味に変化するキノコ雲を、退避すもことも忘れて見とれていた。
二十年八月九日、長崎市は、爆発音と火柱と火炎に包まれ、黒雲は空を覆った。その夜は、炎に染まった長崎の空を見ながら、私は長崎医大在学中の兄の身を案じた。翌日、長崎行きを願ったが、電車が不通で市内には入れないとのこと。帰省許可を待った。
数日後、男子部の生徒が続々と担架で運ばれて来た(長崎師範男子部は長崎、女子部は大村にあった)表皮はめくられ、火ぶくれになった痛ましい唇で、水を求めて亡くなっていった。
やっと許可が出、帰省の途についたのが八月十五日、終戦の日とも知らず、早朝並んで切符を求め、やっと乗車したが、警報で途中下車したり、のろのろと煙を吐く汽車がうらめしかった。佐世保の家は六月未の空襲で全焼したが、家族は辛うじて助かり、北松浦郡の志佐へ疎開していた。ジリジリと照りつける太陽も静止しているような静まり返った田舎道を黙々と歩いた。銀翼を誇らしげに広げた米機が、ビラを散らしながら、稲穂に機影を落として去って行った。無意識にビラを拾い、三時間余り歩いてやっと着いた。藁屋根の土間に茫然と立った。一間だけの侘び住まいに、変わり果てた兄が寝ていた。
八月九日、一瞬の閃光と同時に、鉄筋校舎の下敷きになり、失神状態で倒れていたが、煙にむせ、友の名を呼びつつ瓦礫を押し分けて火の海から逃れ、山水で飢えを凌ぎ、その後、多くの人々に助けられ、トラックや担架で運ばれて、ようやく家に辿り着いたのが被爆後五日目の八月十四日であったとか。
頭と足には包帯、ピリピリのワイシャツ、誰の靴だろうか大小片々の革靴。焦げたような皮膚に落ち窪んだ目。持ち物は避難の途中で亡くなられた友人の防空頭巾一つであった。血に染まったその頭巾は、兄の遺言で後日御両親にお届けした。
この世の人とも思えぬ姿になった兄であったが、意識はしっかりしていて、被爆時の様子を話してくれた。まさに生き地獄を想像させられた。放射能に汚染された水とも知らず、飲んだ山水のせいか、下痢と高熱に苦しみ、幾度も意識が薄れたが、母の面影一筋に生きる力をふり絞って辿り着いた仮住居で、医大生らしく体温、脈拍を自ら計り、「もう大丈夫だよ」と、皆を安心させたのも束の間、十六日の朝、容態が急変し、悪寒と高熱に半日以上も苦しみ、その日の夜半、両親に先立つ不幸を詫び「残念だ」の一言を残し、終戦のニュースも知らず、二一年の生涯を閉じた。その無念の心情を思うと胸に竹槍を突き刺される思いである。
職業軍人の父に追従せず、平和主義に生きる権利と、人類愛を唱えていた人情家の兄の心が痛ましい。一片の氷すら手に入らず体温は水銀柱一杯に上がっていても、悲しむ家族をいたわるような眼で絶命した。
あの時の兄の苦痛の表情は、今も決して脳裏から離れない。せめてもの慰めは、たった一日でも会えたことと、母や姉妹に看取られて他界したことである。亡骸と薪をトラックに積み、地名も知らぬ夜中の野辺で茶毘に付した。白木の箱の前で、帰るに家なき家族は、父の帰りを待ちつつ、空箱を食卓に侘びしい日々を過ごした。
翌年、父は無事帰還したが、老いた両親は人生の最後を、淋しい不自由な生活に耐えながら、相次いで兄の許へ逝ってしまった。
四月長崎花の町
八月長崎灰の町
十月カラスが死にまする
正月障子が破れ果て
三月淋しい母の墓
これは、戦後長崎市の子供たちの間ではやった手まり唄だが、一、二行目は、米機が撒いた宣伝ビラのことばである。被爆者の死体に群がるカラスに戦き、寒さに震え、原爆症で亡くなった母を野辺に送り、孤児になった子供たちも、今日まで幾人生き残ったことであろうか。 多くの人々の犠牲を礎に続いた平和であるが、地球上の総ての国々の子供達が、恐怖と悲しみの涙を流すことのない、真の世界平和の到来を願う日々である。
朝風25号掲載 2000.4月

東京大空襲
松戸市 後藤 守雄
去る八月十五日の午後二時から五十分間、松戸市立博物館で、同名の記録映画を観た。編集はNHKで約半分の画面は、アメリカ空軍側の撮ったモノの複写である。
ただ今、当会で話題になつている焼夷弾を落とす前に、どのような方法で東京都内、主として下町の屋根にガソリンを散布したか?
B29三百三十四機がそれぞれコース目標別に爆装して離陸するまでが問題である。どのB29もガソリンをドラム缶に詰めて飛行機に載せるシーンはなかつた。合計一千七百八十三トンのナバーム性M69=油脂焼夷弾やエレクトロン・黄燐などの焼夷弾であつた。
アメリカ空軍は、この東京大空襲の実績で十数年あとのベトナム戦の教訓を得ていった。
ガソリンは非常に軽い比重の液体である。しかも引火点はきわめて低い。仮にB29の胴体に穴を明けガソリンを空中散布したら、たちまち高々度では気流となつて、後からつづく友軍機にガソリンがかぶり、誘爆して全機目的を果たす前に墜落してしまうだろうというのが私の考え方である。それともあの日、29が東京上空に達する前に、地上で別動隊が待機して、ガソリンを各家々に散布していったとすると、話は通る。
かねてから東京には、三月十日の陸軍記念日には大空襲があるのでは?と街の噂は合った。
悪い時には、わるいことが重なるものだ。三月九日は昼すぎから北北西の強風が吹きはじめ、夜十時三十分に第一回の空襲警報がなったが、すぐB29は房総半島をゆつくり旋回しただけで退散してしまった。やれやれ、ここで一旦、警報を解除した。都民は翌日十日の朝に向かつてほつとして眠った。十日の午前零時八分、三百三十四機が、東京湾を真っすぐ北に上がって、深川木場に第一弾を落としてごく低空で浅草方面をねらつて爆弾を投下していった。アメリカ空軍兵士の談話として日本の高射砲の弾丸はB29の飛行進路よりはるか上空で破裂していた。(それまでのB29は一万メートル上空を侵入していた。この逆をやったわけだ。戦争の駆け引きを日本軍は誰も気付かず、米軍のなすままだつた)
ナパーム弾と小形の焼夷弾は、百五十メートル間隔で落とす計画であつたといいう。
地上では一瞬に千数百度の高温になる。もちろん木造の家などすぐ出火する。路上を逃げている人は瞬時炭化して、後、数時間あとにはセミのぬけがらのようになつて、下町の路上を風に吹かれていったと、これは日本側の記録である。
これだけの高温になると地上の酸素は一瞬にしてとんでしまって、消防ポンプのガソリンエンジンは酸欠で全て使いものにならなかったそうな。
この米空軍の作戦指導者はまだ健在だが、その自宅玄関には昭和天皇から贈られた大勲位旭日章の勲章が、ガラスケースに入れて飾ってあるのが不思議なムスビの映画だつた。
『朝風』八月号の二十一ページに三月十八日東京大空襲とあるは、明らかに誤りである。
正しくは昭和二十年の三月十日である。同人諸士の記憶を訂正乞う。東京都民の十二万の犠牲者の霊魂よ勲章の件は、ご納得されるや?(おわり)
朝風32号掲載 2000年10月
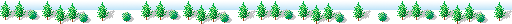
めくるめく夏に
秦野市 坂東 正子
ひまわり、光る海、季節は又巡り来て残りの人生をせめて心だけでも安らかに終りたいと思っておりますが、絶対忘れ去ることの出来ない劫火の記憶です。太平洋戦争も敗戦色が濃くなり、三重県の尾鷲上空から又高知の室戸沖から阪神工業地帯を狙って毎夜のように、怪鳥の唸りに似てB29が上空を通過してゆきました。徳島なんか、まさか、でもいつか、と暗闇の中で空襲警報に怯え乍ら不安な日々を送っていました。昭和二十年四月十六日、昼、急降下してきたB29一機「あれ何だ-」人々の叫びと同時に轟音とものすごい土煙が上り、息を切らせて家に帰つた私の目の前を泥だらけの人が泥と血にまみれた人を担架に乗せて走って行きます。
小型爆弾であつたということでしたが、大きな穴があき、二百米四方、確にそこにあつた町並みが無惨に破壊され、全く見た事の無い光景になつていました。祖父、父母亡き後家業を継いでいた叔父は中国大陸で戦死し、次の叔父はフイリッピン沖で輸送船と共に沈み、女子供四人爆風で壊れた窓ガラスに厚紙を張り、傷んだ板塀を打ち付け、命があつたことがせめてもと、寄りそって暮らしておりました。そしてその空襲が、幕明けでした。昭和二十年七月三日未明、グァム島基地、硫黄島経由、米国第二十空軍団B29、総数129機、投下焼夷弾1050トン。徳島市は瞬く間に火の海となりました。「逃げろ-」の声に辛うじて持ち出した薄いふとんを防火水に浸して被ると、祖母を中にしてとにかく走りました。
父の末の妹、叔母二十才、私十七才、弟十三才、泥を拾ったふとんは次第に重くなり、行く先々は火の海、家の焼け落ちる音、B29の爆音、次々と襲ってきては焼夷弾の雨を降らし、腹を返して急上昇してゆく。その機体は炎に照らされて血を吸った鮫のようでした。
どこをどう走ったのか、町を抜け、畑道に座りこんでしまいました。植えたばかりの田に焼夷弾がブスー、ズシーンと不発弾となつて突きささり、四人固まったまま、茫然としていました。いつの間にか爆音は消え夜はしらじらと明けていました。今親水公園百選に入っている市の中心部を流れる新町川も逃れた人の死に場所となりました。焼け残った小学校に布袋ようの物に納められた遺体が無数に並べられ、その中に同級生も入っている筈でした。
毎晩繰り返される警報がその夜もやっと解除され、ほつと横になった途端、「空襲だ-」の叫び声、跳ね起きた時は、もう周囲は真赤。いつも持ち出しているお位牌や、父母の写真も持ち出すひまもなくすべて失ってしまいました。
やがて目眩めく夏の陽が焼けた街を照りつけ、暑い、暑い夏の始まりとなりました。着のみ着のままでお腹を空かせて、どこへ行こうかと必死になつて考えていました。市街の八割は焼失、死傷者三千五百とありますが、確認作業は行われておらず、又発表もされず、もっと多数であつたともいわれております。その後も焼け残った小学校や四十三連隊が爆撃され、太平洋に面している県南部は、毎日のように艦載機による機銃掃射が行われ、鉄橋の列車を銃撃し、今以て静かな街や村に投弾してゆきました。
食糧不足のため、買い出しに行った人が駅に着けば警察に没収されるので止まる前に飛び降りて亡くなり、又けがをし、駅の宿直室に横たえられているのを見ては、このような悲しいことが、何時まで続くのか、何故どうして。心の中で繰り返すばかりでした。このような事は国内各地で起ったことと思います。沖縄、広島、長崎の人々の苦しみには比べようもありませんが、戦争によって命を落とした個々の惨めさ、痛ましさは変りないと思います。
兵現役から帰って来た叔父は祖父と共に家業を継いでいました。私達姉弟を父とも兄とも可愛がってくれました。やがて支那事変が勃発し、深夜に戸を叩く赤紙に家中緊張が走りました。挙手の礼と襷で四ケ月後に生まれる我が子を残して叔父は「勇躍」戦地へ出発してゆきました。そしてその年十月羅店鎮の夜襲で戦死してしまいました。葬送のラッパと共に兵士の胸に抱かれて帰った白木の箱に入っていたものは、石と肩章ようのもの、フイリッピン沖で沈んだ叔父は名前の書かれた木片が布に包まれてあつたと。子供の私には見せてくれませんでしたが、祭壇の前で祖母もつれ合いの叔母も泣きたかったろうに。大声で泣けば少しは心も鎮まったかも知れないのに、御国の母と、皇国の妻には許されないことであつたと思います。
一昨年初めて靖国神社へ行きました。神社仏閣の多い関西圏からみると思ったより質素な社でした。大好きな叔父、乙種補充兵としてヒヨロヒヨロと召集されていった酒好きの次の叔父、神になつたとは露思っていませんが、ここに戦死した人々の魂がいると幼い頃から教えられてきた私は自然に掌を合わせておりました。若かつた叔母が父の顔を知らない息子の手を引いて、はるばる四国から、この社に来た時、菊の紋章、日の丸を見て、憎いと思ったでしょうか。つらいことだけど、一瞬、夫を父を誇りに思った(思わされた)でしょうか。分りません。叔母は今、生と死の自覚もなき如くベットに横たわったままです。願わくば安らかに逝かせてあげたいと思います。
想像も出来ない凶々しい事の起きる昨今ですが、まずは穏やかな秋の一日、各々故郷の異なる同年輩とお喋りをしていました。
「え、近くに軍需工場でもおましたのか」
「あらあなたは戦争被害者でしたの、まぁ」
「戦争のこと、あまり感じなかつたですけど」
私は愕然としました。あの私の記憶はまぼろしだったのか。少くともあの時代を共有していたと思っていたのに。私は茫然としました。そして慄然としました。
それが熱海集会に参加させて頂くきっかけになつたのです。会員皆様の気迫に圧倒されました。参加させて頂いて有難うございました。そしてまた、廻り来た夏、生かされて感謝します。人口二十六万のささやかな故郷徳島市です。先祖供養の盆踊りも今は阿波踊りとして知られ、又始まります。賑やかで騒々しくて、ほとばしる汗、その渦の中でちよつぴり淋しい私です。どうかずっと平和でありますように。君が代も日の丸もいつの時代にか変わつてゆくかも知れません。その下で、二度と悲惨な戦争が起こらないこと、心から、心から願っております。
朝風29号掲載 2000.7月

戦争中の悲話
新潟県 渋木 喜一郎
昭和十九年十九才で私は海軍軍属として青森県の大湊施設部の第三部隊に配属され根が鍛冶工だったので鍛冶関係の仕事に従事.軍律きびしく今更言うまでもないが教育勅語を地で行くようなつらい毎日でした。
その鍛治工場は宇曽利と言う地にあつて、すぐ前が大湊軍港でその先が陸奥湾であつた。工場のすぐ隣、十米と離れていない所にこの世の地獄と言われた「タコ」部屋があつた。おそまつな建物で間口五間の奥行八間位だつたと思う。関係者以外は絶対立入禁止になつていたが、軍とのつながりがあつたのか、土工用 スパイキ(トロレールの止め釘)、鎹(カスガイ)等の注文があり納品のため時には中をのぞく程度だが見る事ができた。入口に立つやブンーと悪臭が鼻をつく。建物の真中が土間の通りになつていて巾五尺位あつたろうか、両脇にはつるつるした丸太が土台のように敷かれていた。部屋に間じきりはなく、柱を残し全部素通しである。炊事場は別棟になつていたが、すきまだらけの板の間にムシロが敷いてあり、がりがり毛布が三枚、厳寒の冬でもこれで通し足元に棺桶みたいな箱が一つ、三尺の六尺の「ゴザ」一枚が自分の住居となつている。そして丸太の長木が全収容者の枕である。
この土間での焚火は許されていたようだ。屋内には煙が充満し大変だろうが窓が全くない。この土間の通りが排気口である。只、穴が掘ってあるだけの便所。大便で汚れ、黄泉い便があふれ近辺がずらずらしている。板二枚を渡し用を足す。以上で大体お察しがつくと思うがこれがこの世の地獄、「タコ部屋」の実態である。便所には「ウジ」がふたにはつてわき不潔なんて話にならない。大体四五十人位収容されているらしいが、その食事たるや、家畜同様、よく生きてきたとしか言いようがない。
朝はうす暗い内に十人一組とされ腰なわでつながれ、武装した「かんとくに引張られ、いづこかへ連れて行かれる。帰途もくたくたになつて同様に有刺鉄線に囲まれた我が家に帰ってくる。とにかく逃亡に目を光らせ、絶対に逃げ出せないようになつていた。
私はこの目で見た。逃亡者がつかまって、前庭に後手に縛られ引出され、見せしめの「リンチ」が始まる。こん棒と「ムチ」でたたきのめされ、全身血がにじむ。紫色にはれ上り「ヒーヒー」と泣きながら悲鳴を上げていた。
やがて動けなくなりボロをかぶせられ地獄部屋へ。数々のリンチで当然犠牲者も出たであろう。どう始末したものか私共にはわからない。寝苦しい程、暑い夜だつた。丸出しの裸で両手両足を縛られ、外に放り出され、全身に「チユウ」を吹きかけられ、「蚊攻め」の体罰も見た。助けてくれと泣き叫ぶ。誰一人手助けしない。制裁者以外は近寄れないのである。原因は命から二番日の食事をかすめた体罰だつた。
現場統率者は勇ましい軍服に乗馬ズボン、左腰に軍刀を下げ、右腰には拳銃をぶらさげていた。銃口の長い逸物だったようで騎兵そのもの軍馬にまたがりさっそうとしていた。
後で其の通の人から聞いた話だが、これらの人達は皆まじめな務め人か、零細企業に働く方達、中には風来坊もいただろう。高給と甘い言葉にだまされ、募集人のえらい歓待で列車に乗せられたが最後、厳重な監視の下に連れてこられたのだときく。
中には学資稼ぎにと「わな」にはまった学生もいたという。
昨日、召されたタコ八が
弾丸にあたって名誉の戦死
タコの遭骨はいつかえる
骨がないのでかえらない
タコの親達や、かわいさう
こんな気の毒な替え唄がこつそり歌われていた。危険をともなうトンネル掘り、一番辛苦な重労働、一番危い攻撃目標とされる現場。これらが彼等の職場だつた。どう考えても軍とのつながりがあるように感じられる。従軍慰安婦と同様、ひたかくしの行為かも知れない。
戦後この人達はどうしただろう。知る由もないが、この疑問は今だにとけていない。
十年程前に、私は個人でこつそりこの現場まで旅して来たが、すっかり変ってしまって住宅街となつていた。
(注)山の斜面を削り落す作業場を見た事がある。個人個人に放たれてはいたが足には重い鎖りがつけられ、その先には砲丸のような鉄塊がつけられており絶対逃亡不可能になっていた。
半分ボロボロの麦めしは(中食)は立喰いだつた。あわれ目も当てられない光景だつた。
朝風37号掲載 2001.3月

私的制裁と日本の軍隊
東京都 室井 辛苦
軍隊の精強さは規律が厳正で、兵士たちが命令一下死地に飛び込む気迫が漲っているか否かに依存する。この点日本軍の軍紀は厳正であったと言えるが、問題は、何によってその軍紀を維持したかということである。日本軍はそれを暴力という手段に訴えた。
暴力は日本軍隊の生活のあらゆる面で吹き荒れていた。たとえば「帽子のかぶり方が曲がってる」「ボタン一つを掛け忘れた」といった服装の乱れ、「兵器の手入れがおろそかになっている」「部屋の掃除の仕方が悪い」「典範令の暗記が遅い」から「整列が遅い」「返事が遅い」「声が小さい」「動作がにぶい」「態度がでかい」といったものまで暴力の対象になる。
暴力をふるおうと思えば材料に事欠かないのであって、掃除した直後でも古い兵舎の片隅から一片のゴミを見つけることはやさしい。どんな大きな声で返事しても「まだ小さい」と言うことはできる。「態度がでかい」という判断なら、いつでも誰に対してもできる。
軍隊用語で私的制裁といったが、もっとも多いのはビンタ、頬を殴るのだが、それは平手でなくゲンコツであった。なぐる方は腰を落とし手を大きく後ろに回し勢いをつけて殴るので、殴られる者は倒れてしまう場合が多い。その時はすぐ立って次のビンタを受ける態勢を整えなければならない。往復ビンタといって左右を代わる代わる殴られるときは、右に左に体は大きく揺らぐことになる。下手に避けたりしたら、その制裁は数倍に増えることになろう。
ビンタにはゲンコツだけでなく上靴(皮のスリッパ)のビンタもあるし、帯革ビンタ、対抗ビンタと称し、戦友同志を殴らせる場合もある。仲間だと思い手加減すると「ビンタはこうして取るものだ」と、下士官達は手本を示すため戦友を普段より余計に殴り、被害は更に大きくなるので、仲間同志でも力一杯殴り合わねばならない。
ビンタを二~三〇回もとられると頬は膨れ上がり、数日間はものを噛むことも出来にくくなる。このほか、みぞおちを突き上げることもあれば、演習中、地上に伏せているような場合頭を蹴飛ばされる。以上は日常茶飯時であり、本格的になると数人がかりで手も足も使って文字通りふくろ叩きにする。 私は現在、耳が遠い。このようなことは程度の差があるにしろ、多くの軍隊生活者が味合わされたはずである。
それらの他に、捧げ銃、営庭内一周の肉体的罰あり、鴬の谷渡り、自転車競争、セミなど、大の男が涙を流し柱にしがみ付きミーンミーンと鳴く、その嗜虐的制裁の姿は親兄弟に見せられたものではなかった。軍隊は徴兵・懲役一字の違い、と称されたが、監獄でこれ以上の制裁があったとは耳にしていない。まして死刑の判決を受けた者以外に死刑は無いが、軍隊は戦地に出れば否応無く死が待っていたのだ。
人智の限りを尽くしたと考えられる私的制裁と称されたこの処罰は、根本はどこにあったのであろうか。いかに日本軍隊という暴力機構でも、その暴力を正当化する錦の御旗が無けれは組織として長続きし得ない。また一つの組織・団体には、その存在の目的がなければ団結は期待できないし、ついには瓦解するだろう。これら二つは結局一つのことを言っているに過ぎないがこの役割が天皇制なのである。軍人精神の根幹を示したもので、軍人が朝に夕に唱和させられ、暗記をさせられた「軍人に賜りたる勅語」には「…下級の者は上官の命を承ること、実は直ちに朕が命を承る義なりと心得よ」という文句がある。この句は上官に対する絶対服従を要求する意味と解せられており、上級者が下級者に無理な命令を発し暴力をふるう時にしばしば引用された。「俺の言うことは天皇陛下の命令と同じだ。天皇陛下の命令に背くのか」と、馬鹿の一つ覚えのように怒鳴ってビンタをとるわけで、天皇陛下の御命令となれば、なに人も絶対従うより他なく、反対や批判は決して許されないことになる。
その天皇陛下と軍隊との関係は、先にもあげた軍隊組織の基本を定めた「軍隊内務令」の綱領一および二に次のようにさだめられている。
一、「軍は天皇親卒の下に皇紀を恢復し、国威を宣揚するを本義とする。
二、軍隊統率の本旨は将兵の心を一誠に帰し一致団結、以って軍の本義に邁進せしむるにあり。
軍紀を保つための暴力の基礎である天皇制は、天皇制の正統制、合理制を論理的に説明できないために、再び暴力に頼ることになり、凶暴な暴力と、訳の分からぬ訓示は相乗作用をもって再び兵営内に荒れ狂い兵隊を命令のままに動く動物と化して目的を達することになる。かくて日本軍隊はいかなる命令にも服従し、黙々として死地に飛び込む精兵となるわけである。(奴隷的兵士)
あの、鉄と吹き荒れた私的制裁の根源が軍人勅諭の一項目「上官の命を承ること実は直ちに朕が命を承る義なりと心得よ」にあったのである。下級者をなぐる口実としてこれほど安易な項目は他にない。今更ながら軍人直喩によって殴られた全兵士の怨嗟の的であっても軍人勅愉の賛美者は皆無であろう。
戦争に斃れた戦友たち、その戦争責任者追及のため昨年五月以来次の本を読んだ。
天皇と戦争責任・児島襄、日本の戦争責任・若槻泰雄、戦後世代の戦争責任・加藤周一、戦争責任の受け止め方・加藤周一、戦争責任・家永三郎、連合国捕虜虐待と戦後責任・油井大三郎、日本のアジア侵略・小林英雄、天皇ヒロヒトの戦争責任・山田朗-加藤実紀代、日本の戦争責任をどう考えるか・船橋洋一、戦争と罪責・野田正彰時効なき戦争兼任-裁かれる天皇と日本・アジア民衆法廷準備会、戦後世代の戦争責任・田口裕史、キーワード日本の戦争犯罪・小野田裕司、天皇制と軍隊・藤原彰、日本人の十五年戦争観・アジアに対する日本の戦争責任を問う民衆法廷準備会、天皇-帝国の終焉・児島襄。 以上十七冊を読み、愚かな私ながら、いかに日本軍隊が奴隷的兵士になりさがって戦友同志をもなぐる無法な兵士となり、敵国人に対し、情け容赦ない非道の振舞いをしたか、今更ながら日の覚める思いがしました。
戦争体験者諸氏、ビンタや屈辱の制裁に奴隷と化した昔日を思い浮かべ、死んだ戦友たちのためにも、再び戦争の惨禍に巻き込まれない為にも、現代の政治から目を離してはならないと思います。政治への無関心は、再び戦争に自らの血を流す結果になることを、くれぐれも忘れてはならない。
朝風51号掲載 2002.6月

反戦老人の独り言
静岡県 秋元 実
反戦老人の独り言(3)
三島市の中部第十部隊に入営し、第六中隊第一内務班に所属したわたしたちは、まず、初年兵係の古兵から、内務班生活の心得などについて、いろいろと教わりました。
そうした指導を受けながら、兵隊屋敷の最初の三日間はなにごともなく過ぎて、人のいい十五名の新兵たちが、「軍隊っ一て、意外におとなしいところじゃないか」なんて思い始めた四日めの夜のことでした。
日夕点呼が終わった午後八時四十分ごろ、初年兵係で現役二年兵の竹沢一等兵が、突如叫びました。
「初年兵、整列!」
ガタガタと床を鳴らして、寝台と食卓の間に、横一列に並んだ十五名に向かって、メガネをかけた長身の竹沢一等兵は、背筋をピンと伸ばし、きびしい口調で言いました。
「お前たちは、すでに、帝国陸軍の軍人だ。お国のために、いのちを捧げる軍人だ。しかるに、入隊以来のお前たちを見ていると、起居動作すべてダラダラしていて、完全に地方人のままだ。自分は、お前たちの教育係として、一日も早く、お前たちを一人前の軍人に仕立てる責任を負っている。それで、今夜は、軍隊特有のやりかたで、お前たちに軍人精神を注入することにした。わたったか。新兵の十五人は答えました。
「はい、分かりました.」
一等兵は、吠えました。
「声が小さい!」
そこで、十五人は、あらん限りの声で叫んだのです。
「わかりましたァ。」
一等兵は、ドスのきいた声で、命じました。
「足を半歩に開いて、奥歯を噛み締めろ! メガネを外せ」
言われたとおりにすると、竹沢一等兵は、新兵の列の端に立ち、そこからひとりずつ、平手でバシッ、パシッと殴り始めたのです.
一等兵は、やがて、覚悟をきめ、メガネをはずして直立しているわたしの前に立ちました.見ると、一等兵の両眼は充血して、妖しく光っています。それは、まさしく、かつて何かの小説で読んだ、サディストの目そのものでありました.
一等兵の猛烈なビンタをもらったとき、わたしの左の頬は、激しい痛みとともにカッと熱くなり、一瞬目の前が暗くなりました。 これが、大日本帝国陸軍が、無力な新兵に加えた、最初の肉体的、かつ精神的打撃でありました。
平時、内務班の定員は、三十名ないし三十五名ぐらいのものでしたが、わたしが入営したときは、太平洋戦争開始直後で、急遽召集された兵隊で、五十名以上にもなり、ひとりが一つの寝台というゆとりはなく、すべての寝台を隙間もなくっつけて、その上に、古兵と新兵が枕を並べて、ぎっしり二列に、寝かされていました。
当時、班には、野戦帰りの召集兵、現役と補充の三年兵、現役の二年兵とわたしたちのような初年兵がいました。
現役四年兵の班長藤井軍曹と召集兵の班付き下士官和智伍長は、五人同居の下士官居室(こしつ)にいて、ふだんは、日夕点呼のとき以外、班に顔を出すことはなく、五十人雑居の第一班を仕切っていたのは、野戦帰りの召集兵、ヤクザっぽい山田兵長でした。
昭和の昔、兵役法による陸軍現役兵の服役年限は二年で、平時なら、一月に入営して翌年の十一月には、二つ星か三つ星になって、私服に着替えて、「ハイ、さよなら。」といやな兵営を後にしたものでしたが、大陸の戦況が深刻になった昭和八年ごろから、特別措置で服役年限が三年になり、しかも、太平洋戦争に突入する寸前からは、満期除隊しても、半年ぐらいでまた赤紙が来るようになって、どこの陸軍部隊でも、内務姓は、年次・年齢・階級の異なる、現役・補充・再召集の兵隊で溢れ、動物園の同じ檻に、ライオンと狼と猿とうさぎを閉じ込めたような、すさまじい雑居のジャングルになっていたのでありました。
昭和二十七年、野間宏の原作を山本薩未監督が映画化した「真空地帯」では、身に覚えのない窃盗罪で告発された、現役四年兵の木谷一等兵が、陸軍の監獄から刑期を準えて帰って来たとき、歩兵部隊の内務班に雑居していたのは、現役の三年兵と二年兵、補充兵の三年兵、学徒兵と補充兵の初年兵でしたが、あのモノクロームのリアルな画面で、初年兵を徹底的にイタブルのは、内務班では「神様」の、現役三年兵たちでありました。
明治以来、貧乏国日本の軍隊は、装備や兵力の不足を兵隊の精神的エネルギーで補おうとして、若者たちを、困苦欠乏に耐え、死を恐れない「戦国マシーン」に仕立てるために、その卑近な方法として、主として、内務班における下級兵に対する上級者の日常的なリンチを、黙認してきたのです。
入営して四日めの一月二十八日の夜、初めて、初年兵係竹沢二年兵の整列ビンタをもらってから、わたしたち補充の初年兵は、いくたりかの古兵から、実にヴァラエティに富んだ、日本陸軍伝統のシゴキを頂戴することになるのでありました。
ピンタをもらった最初の夜、斑内にはいっぱい古兵がいたのでしたが、その連中は、ただ黙って、新兵の殴られるのを眺めているだけでした。教育係の二年兵が、どんなに理不尽に新兵たちを殴っても、だれもなんとも言わないのが、軍隊家庭の内務班の仁義なのです。
日本の軍部は、「殴れば殴るほど、兵隊は強くなる」と信じていたし、同じ班のある召集兵などは、「いいか、軍隊には、世辞も愛嬌もいらねえんだ。」などと言って、些細なことで、初年兵を殴っていました.
中隊には、夜間、紅白の縞の肩章をっけ、軍規風紀を取り締まる週番士官もいます。 しかし、そういう隊付き将校も、内務班の暗い電灯の下で、初年兵が革の上靴で殴られたり、永い時間、前支えをやらされたりしていても、見て見ぬふりをしているだけでした。
わたしたち第六中隊の属する第二大隊には、兵舎の北の厩に、将兵を乗せる「乗馬」、荷物を曳く「駄馬」、火砲や弾薬車を曳く「輓馬」という三種類の軍馬が、四百頭ぐらいいましたが、わたしたち初年兵は、よくそこで、厩週番上等兵の指揮で、馬の糞便の掃除や、担架に載せての、寝藁の出し入れをやらされました。
馬の糞便は、ときに手で掴んで処理しなければなりません。汚いと言ってためらっていると、週番上等兵に、竹箒で殴られます。
週番上等兵は、寝藁の搬出など、五こ班の競争でやらせ、負けた班の初年兵に、「対抗ピンタ」をやらせました。
対抗ビンタというのは、二列に並んで.向き合い、自分の前に来た相手とビンタの張りっこをすることです。
同年兵だからといって、ビンタの手を抜くと、週番の鬼が釆て、よしと言うまで、何度でも、力いっぱい殴り合いをさせます。
軍隊には、いたるところに、初年兵を虐げて快感を感じるサディストがいました。たとえば連隊の炊事。食事が終わると、各班の食事当番の初年兵が、炊事へ食缶返納に行くのですが、そこに古兵の炊事勤務兵が待ち構えていて、執拗に検査をし、ほとんど、虫メガネでしか見えないような飯粒が残っていても、たちまちピンタか、「カンカン踊りです。
「カンカン踊り」というのは、食缶を頭から被り、自分で唄いながら、たとえば「農兵節」とか「佐渡おけさ」などを踊ることで、それを、炊事兵が「よし」と言うまで、繰り返すのです。
連隊の炊事は、各中隊の落ち、こぼれの兵隊が行くところだということで、おそらく、そういうサディストの兵隊は、無力な初年兵をいじめることで、軍隊日陰者の胸のモヤモヤを晴らしていたのでしょう。
初年兵係は、ときどき編上靴(へんじょうか)の検査をして、手入れが悪いとビンタでしたが、見物人の班の古年次兵のなかには、やはり、野戦帰りのサディストがいて、「おい、竹沢一等兵、そいつら、各班を回せ!」などとけしかけるのがいます。 そこで、命じられた初年兵は、紐を結びあわせた編上靴を首から胸にぶらさげて、階下二こ班、階上三こ班の各班を、ひと巡りします。
わたしも、やりました。班の入り口に立って、叫びます。
「第一班秋元二等兵、第二班の古兵殿に、用事あってまいりましたァ。」
鬼の召集兵が答えます。
「何か?」
「はい、古兵殿に、編上靴の磨き方を教えていただきにまいりました!」
「分かった。こっちへ来い!」
わたしは、覚悟をきめて、寝台に腰掛けて並んでいる赤鬼・青鬼たちの前へ、オズオズと進みます。
チョビヒゲを生やした古兵のひとりが、わたしの編上靴を手にとって調べて、やがて尋ねました。
「この靴は、どなたにいただいたものか?」
答えは、決まっています。「はい。大元帥陛下からであります。」
「その大切な靴を、こんな磨き方でいいと思っているのか?」
「はい。思っておりません。」
古兵は、それから、靴の手入れについて二、三しゃべってから、 「よし、歯を噛み締めろ、メガネをはずせ。」と言って、わたしの頬を一発殴ると、「帰ってよし!」と言って、わたしを解放してくれました。
これを書きながら、わたし、ふと思いました。
わたしは、こんな新兵シゴキの三か月の後、思いがけなく、臨時召集に切り替えとなって、教育召集の補充兵三百六十名のうち、残された連隊六十名の同年兵とともに、遠くビルマ転戦中の野戦重砲兵第三連隊に配属されて、以後四年とちょっと、ビルマ・雲南・ティモール・小スンダ列島と、戦旅の苦労を味わってから無事復員し、八十三歳になっても、比較的元気に生きているけれど、生来まじめゆえに、まじめにわたしたちを殴ったあの初年兵教育係の竹沢一等兵や、ウサ晴らしに、抵抗できない新兵たちをシゴイた、あの中隊の古年次兵たちは、その後どうなっただろうと。
全員八十四歳を超えたはずの今、どこでどうしているだろうと。もし、生きている皆さんがあったら、ぜひ会って、昔話をしてみたいたいなァと。 (つづく)
朝風84号掲載 2005.4月
反戦老人の独り言(4)
軍隊という真空地帯にいて、永らく、女っ気のない.殺伐とした内務班に長居していると、地方という一般社会ではどんなにマトモな人間でも、どこかオカシクなってくるものですが、どの班にも、その典型として、初年兵をいたぶることにサディスティックな快感を覚え、それで、万事不如意の兵隊屋敷の憂さ晴らしをする、何人かの古年次兵がいました。
わたしの投げ込まれた第一内務班の場合、特に、その冷酷で執拗なリンチで初年兵に恐れられたのは、黒田一等兵と藤島上等兵の二人でした。
Y中尉の将校当番を勤める黒田一等兵は、あと少しで三年兵になる補充兵で、しかもいまだに星二つの、いわゆる「万年一等兵」でした。
人事係の覚えも悪く、進級できない黒田一等兵は、旧式の軍衣に二つ星の巨大肩章を付け、鼻下にヒゲを蓄えて、いつも、一つ星の初年兵たちを威圧して、班内をのし歩いていました。
高等小学校しか出ていない黒田一等兵は、ことさらに、高等教育を受けた初年兵を敵視し、それをいじめることに生きがいを感じているようでした。
わたしとは一つ置いた右横の寝台に寝ていたのが、慶応大学出身で二十六歳の沢材でしたが、まず、黒田万年一等兵の標的にされたのが、長身猫背で万事動作ののろい、インテリのこの沢村で些紳なことで、一等兵に殴られていました。
わたしが、情けないと思ったのは、大学出の沢村が、黒田の敵意の前で、いつもオドオドしていることでした。殴られるときも猫背の沢村を見て、わたしは、なにか「老兵の悲しみ」のようなものを感じたのでありました。
ある日のこと、班内の掃除で疲れてしばらくボーツとして立っていたら、わたしは、「貴様、何をボサッとしてる!」という声とともに、後ろから膝の関節のあたりを殴られ、前にのめって、ごつんと、アタマを寝台の角にぶつけました。
急いで立ち上がって振り返ると、目の前に唇を歪めた黒田一等兵の、鬼の顔がありました。
内務班における、初年兵への日常的な体罰には、二つの種類がありました。
一つは、初年兵係竹沢一等兵が、それでわたしたち、新入り補充兵十五名を鍛えたような教育的体罰で、もう一つは、系統的教育や訓練とは関係なく、あらゆる場面で、恣意的感情的に、古兵が新兵に加える、私刑の体罰です。
あの兵隊演歌「可愛いスウチャン」の歌詞にある「人の嫌がる軍隊」とは、多分に、「上官黙認のリンチで初年兵を泣かせる」鬼の軍隊」という意味ではないでしょうか。
わたしが調べたところでは、明治以来日本の軍隊が、ビンタや前支えを初めとして、新兵いじめに使った調教的リンチの数は、二十数種にものぼっていますが、三島野重三の中部十部隊で、黒田一等兵のような古兵が、無抵抗の初年兵を苛めるのに使ったテクニックに、「箱根山自転車競争」と「三島芸者」というのがありました。
ある日、初年兵にしては態度がでかいと見られた新井が、黒田に指名されて、箱板山を自転車で駆け上がるハメになりました。
黒田は、食卓を二つ並ペて間を五十センチほどあけ、そこへ新井を立たせて両手を食卓につかせ、からだを支えながら、両足を床から離すよう命じました。
黒田は言いました。
「皆さん。ただ今から、箱根山自転車競争を行ないます。スタートは、三島大社前。用意、ドン!」
新井は、古兵新兵環視のなかで、両足をグルグル回転させて、自転車のペダルをごぐまねを始めましたが、一分もしないうち、その目が充血してきました。
黒田は、言いました。
「さて、いよいよ、箱根山です。坂道です。がんばりましょう。」
新井の足の回転は速くなり、汗が流れ、息づかいが激しくなりました。しかし、箱根外輪山の登り道は遠く、笹原・三谷(みつや)・山中の各部落を通り抜けて、目的地の箱根峠に着くまでには、かなりの時間がかかります。
さすがの黒田一等兵も、失神しそうな新井を見て、自転車が三谷にかかるころ、この残酷な拷問をやめたのでしたが、このときの残酷な光景は、現在でも、八十三歳になったわたしの根底に、鮮烈な映像として残っています。
黒田は、なおもチョビヒゲの顔で初年兵に迫りながら、ときどき、わたしたちに、「三島芸者」になれと迫りました。「三島芸者」とは、初年兵にこの上ない侮辱感を与える。ある冷酷ないじめのテクニックでありまtた。
内務班には、高さ六十センチほどのゴミ箱がありました。
黒田は、わたしたちをその上に正座させ、メシのシャモジを撥にして、ベンベンと口で伴奏させながら、「よし」と言うまで、民謡や流行歌を歌わせたのでした。
当時、内務班には、事務室からときどき新聞がまわってきて、ストーブにあたりながら、古兵のだれかが読んだりしていましたが、ある夜の点呼後、竹沢ー等兵が、初年兵に集合をかけて整列させると、次のように問いかけました。
「お前たち、今日の新聞に、恐れ多くも、天皇睦下のお写真か載っていたのを知っとるか?」
「天皇」と聞くと、十五名は、反射的に不動の姿勢をとりました。
「休め!」と号令してから、初年兵係は、黙って立っているわたしたちに言いました.
「お前たちには、いつか、新聞に陛下のお写真が載っていたら、それを切り抜いて、日夕点呼前に中隊事務室の前の郵便受けに入れるようにと言っておいたはずだ。それをやるのも、お前たちの仕事だ。一事が万事、近ごろお前たち、どことなくたるんでるぞ!」
すると、まわりで見物している古兵たちの中で、野戦帰りの藤島上等兵が叫んだのです。
「初年兵係、竹沢! そいつらを吊るせ!」
すると、それに同調して、やはり野戦下番の二、三人の古参召集兵が叫びました。
「吊るせ、吊るせ、竹沢! 遠慮するな!」
兵室と中央廊下の仕切りに太い梁が渡してあります。 南北の兵室に分かれ、それぞれ横一列になったわたしたち初年兵は、「かかれ!」という竹沢一等兵の号令で、その梁に飛びついて、その角に手を掛けてぶら下がりました。
召集兵たちは、その下に、水を満たしたバケツをいくつか並べました。
やがて、力尽きたわたしたちは、次々とバケツの上に落下して、全員、ずぶ濡れになったのでありました。
わたしは、現在、四百冊に及ぶ戦争及び旧軍隊に関する出版物を持っていますが、それによると、日本陸軍の場合、各部隊で、わたしが書いてきたような私刑や体罰がおこなわれていたようですね。
うわさによると、満洲に駐屯し、関東軍に属していた部隊のリンチは、内地の野隊に比べて、一段と凄かったようで、わたしは、関東軍の兵隊だった五味川純平の「人間の条件」「戦争と人間」を初めとする、戦争を描き、軍隊の不条理と腐敗を描いた名著の数々は、ひとつには、そうした満洲駐屯部隊で、鬼の古兵たちに容赦なくしごかれた反動として生まれたのではないかと、思っているのです。
なお、「人間の条件」(五部)は小林正樹監督、「戦争と人間」(三部)は山本薩夫監督によって映画化され、日本の侵略戦争の実相を措く、すぐれた歴史的作品となりました。
わたしほ、最近、「もとより生還を期せず」(大隈秀夫・日本文芸社)、「学徒兵の青春」(奥村芳太郎、他・角川書店)などの貴重な出版物を読み、「学徒兵」として動員された皆さんが、入営直後には、やはり、わたしたち同様、鬼の古年次兵たちにさんざんいたぶられたことを知って、深い胸の痛みを覚えました。
映画「真空地帯」でも、学徒兵たちは、小学校しか出ていないような、粗野な現役三年兵の一団に、徹底的に「調教」されるのですが、こうした古兵たちの胸中にあったのは、学歴のない劣等感と、その反動としての、高学歴者への反感や敵意でありました。
わたしは、六十三年たった現在でも、「鬼の六中隊、地獄の一班」でわたしたちを虐げた、黒田万年一等兵や藤島野戦下番上等兵の顔を、忘れることはありません。
そして、地方におれば、おそらく平凡で善良だったはずの二十代のこうした人間を、何年も「兵隊屋敷」に閉じ込めて、弱者をいじめて喜ぶ陰湿なサディストに変質させた天皇の軍隊というものに、今更ように、深い憤りと悲しみを覚えるのです。 (つづく)
朝風85号掲載 2005.5月

竹矢来
京 土竜
岡山県上房郡 山村の五月
時ならぬエンジン音がこだました
運転するのは憲兵下士官
サイドカーには憲兵大尉
行き先は村役場
威丈高に怒鳴る大尉の前に
村長と徴兵係とが土下座していた
貴様ラッ!責任ヲドウ取ルノカ!
老村長の額から首筋に脂汗が浮き
徴兵係は断末魔のようにケイレンした
大尉は二人の案内で一軒の家に入った
川上聡一ノ父親ハ貴様カ!
コノ国賊メガッ!
父にも母にも祖父にも
なんのことか解らなかった
やっと理解できた時
三人はその場に崩れた
聡一は入隊一ケ月で脱走した
連隊捜索の三日を過ぎ
事件は憲兵隊に移された
憲兵の捜索綱は二日目に追い詰めた
断崖から身を跳らせて聴一は自殺した
勝ち誇った憲兵大尉が
全員をにらみ回して怒鳴った
貴様ラ-コノ始末ヲドウ付ケテ
天皇陛下こオ詫ビスルカッー!
不安げに覗き込む村人を
ジロッとにらんだ大尉が 一喝した
貴様ラモ 同罪ダッ!
戦慄が村中を突き抜けて走った
翌朝 青年団総出の作業が始まった
裏山から伐り出された孟宗竹で
家の周囲に 竹矢来が組まれた
その外側に掛けられた大きな木札に
墨痕鮮やかに
『国賊の家』
あの子に罪ゃ無え 兵隊にゃ向かん
優しい子に育ててしもうた
ウチが悪かったんじゃ
母の頬を涙が濡らした
ワシゃ長生きし過ぎた
戦争せえおこらにゃ 乙種の男まで
兵隊に取られるこたあなかった
日露戦争に参加した祖父が嘆いた
これじゃあ学校に行けんがナ
当惑する弟の昭二に
母親は答えられなかった
友達も迎えに来るケン
父親が呻くように言った
お前にゃもう 学校も友達もねえ
わしらにゃ村も国ものうなった
納得しない昭二が竹矢来に近づいた時
昨日までの友達の投げる小石が飛んだ
国賊の子!
女の先生が そっと顔を伏せて去った
村役場で接待を受けていた大尉は
竹矢来の完成報告を満足して受けた
ヨシ 帰ルゾ
オ前ラ田舎モンハ知ルマイカラ
オレガ書イトイテヤッタ
アトハ署名ダケデ済ム
彼は一枚の便箋を残して引き揚げた
一読した村長は顔色が変わったが
黙って懐に入れ 夜更けてから
竹矢来の家を訪れた
三日後 川上家一同の死が確認された
昭二少年の首には 母の最後の愛か
正絹の帯揚げが巻かれていた
梁から下がった三人の中央は父親
大きく見開かれたままの彼の目は
欄間に掛けられた
天皇・皇后の写真をにらみつけていた
三人の足元に置かれた便箋の遺書に
「不忠ノ子ヲ育テマシタ罪
一家一族ノ死ヲ以テ
天皇陛下こお詫ビ申シ上ゲマス」
村長は一家の戸籍原本を焼却処分した
村には不忠の非国民はいなかった
朝風86号掲載 2005.6月
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
谷田川会長・注
竹矢来の由来
ある学習会でひとりの母親から「また、こんな世の中になるようでおそろしいわ」と言って渡されたものです。
一読してびっくり、(これはきっとよく出来すぎた作り話かもしれない)と思いながら作者の゛京土竜氏゛調べをしたのです。
なかなか存在を確認出来なかったのですが、私の友人が国会図書館まで出かけ、数カ月がかりで京都在住の詩人とわかったのです。
さっそく飛んでいって事実か作り話かとおききしたところ、私は科学者です、ウソは言いません、作り話はしませんとおだやかにおっしゃったのです。
満蒙国境の幹部候補生だったそうです。叔母さんという方も野戦病院の看護婦さんをしていた方だそうで、その方からもずいぶんたくさんの詩の材料を入手されたそうです。
HP担当 佐藤・注
私が出征するとき母は「荒縄で括られた白木の箱で返されるようなことを決してするな」と厳しく言いました。 刑を受けた遺骨は荒縄で括られたのでしょうかね。
とにかく兵も家族も村八部にされることを一番恐れていたのです。家族の為に兵は死ぬ程の我慢をしたのです。

16歳少女の東京大空襲体験記
炎の風に追われて(1)
福島 ヨシエ
まえがき
あの忌まわしい太平洋戦争が終結して六〇年、少女だったわたしも、今は七五歳、それでもあの夜、あの日に体験した戦争の悲惨、一九四五年、昭和二〇年三月一〇日の東京大空襲の記憶は今以てわたしの脳裏に、鮮明な記憶として残っております。
あの夜零時八分から始まった東京大空襲は、家屋二〇数万を炎の中にのみ込み、一〇万余人の命を断ちました。それは広島原爆に匹敵する大惨事でした。
あれから六〇年、ここに犠牲になられた方々への鎮魂と、世界が一日も早く平和な時代へと変えられることを祈り、併せて戦争の惨禍を、風化させないための記録の一つとし、その体験を 「炎の風に追われて」 と題して書き残しました。
なおこれは、草の実会編により、太平洋出版から出された 「妻と娘の戦争体験」 その中の一篇でございます。
二〇〇五年一月
本 文
当時、すでに私は、日本橋にある日本銀行本店に、事務員見習として勤務していた。
その日帰宅した私は、いつものように母と夕食の支度をした。夕食といっても当時は、食糧事情が悪く、乏しい食事を家族五人が、互いに分かち合うものでしかなかった。黒い布で覆った薄暗い電灯の下で、お膳を囲んだ家族は、それでも団欒のうちに今日一日の出来事を話し合いながら食事をとるのであった。
「明日(三月一〇日)は、陸軍記念日ね。南方に回された兄ちゃんはどうしているかしら、清四郎(山形へ学童集団疎開した弟)は元気でいるだろうか、お腹を減らしていやあしないだろうか」いつか話は、兵隊や徴用で工場へ行った兄や、学童疎開した弟たちのことなど、家を離れて暮らしている兄弟たちの安否を気遣う話となった。その時、側で黙って聞いていた母は、「今夜はサイレンが鳴らないといいがね」とポッンと言った。
その夜は、夜が更けるにしたがって、寒さは一段と厳しさを増していた。夜半になるにしたがって、いよいよ辺りは静まり返り、なんとなく無気味さを思わせる夜だった。
その夜も私たち姉妹は、防空頭巾とモンペを枕元にきちんと重ねて寝床に入った。これがいっか習慣のようになってしまっていた。
床に就いてから、どのぐらいの時間がたったであろうか。空警を知らせるサイレンで私は目を覚ました。辺りは暗かった。
階下に寝ていた母のところへ、私は急いで降りた。母もまた目を覚ましていた。そして私をいたわるように、母は言った。
「今夜はこっちへは来そうもないだろうから、もう少し横になって様子をみるといいよ、お前も明日勤めがあることだし。」
母に言われた通り私はまた二階にのぼった。が、なぜか布団の中に入る気にもなれず、むしろ寝ていた妹二人を起こして、支度するように言って、私もモンペをはき、頭巾を被ってまた階下に降りた、階下に降りると、もう少し寝ていたらと言った母自身、身支度をし、さらにご先祖様の位牌と貯金や保険の通帳類を風呂敷に包み言った。
「もうこれで大丈夫!」と、それをしっかりと腰に結んだ。
こうして母と私は戸外に出て外の様子を見た。見ると、深川の方の空が薄紅に染まり、遠くの家々が、ちょうどプラネタリユームで見ているように、家並みがシルエットのように、くっキリと浮いて見えた。それは秋の夕映えのように美しくさえ感じられた。しかしその夜の辺りの静寂さと美しさは、何か、これから起こるであろう異常さを、予感させろものであった。
末の妹(当時六才)が後ろから、「ねずみのいる家は焼けないんでしょ」と、問いかけるように言った。
父は、警報が鳴ると同時に家を出て、出動の時を待つため、町の詰め所に駆けつけて行った。危機感は一層増して行く、母は家の裏から大八車を引き出して来た。
「危ないから逃げる用意をした方がいい」とせわしく言って家の中へ入っていった。
母は数枚の布団と柳行李、夏蚊帳、といだお米の入っているお釜とやかん、それらを大八車に積んだ。その時、近所の人は誰も見当たらなかった。さっきまで薄紅に染まっていた深川、本所辺りの空は赤さを増し、既に真っ赤に燃え盛って見えた。その時、風向きが変わった。
母は、町会の詰め所へ出動して行った父を気にしながらも、私たちに、「避難しょう」と厳しい声で言った。すでに母の手は、大八車の取っ手を握っていた。
問も無くして、風に乗った火の手は追いかけるような速さで迫って来た。母、私は急ぎ足で大八車を引っぱる。少し行くと荷物に掛けた縄が緩み、荷物がずり落ちてきた。止まって縄を直そうとしたが、その暇はない。野火のように押し寄せて来る火勢から車の荷を守りながら、一層速く走りだす。大八車を引っ張る母も、後押しする私たちも夢中だった。
水神様辺りまで来たところで私は母と交替し、大八車の梶を取った。末の妹は、遅れまいと一生懸命、梶につかまって走る。母とすぐ下の妹(当時女学生)は後押しに回った。この辺りまで来るとあちこちの細い路地から出て来た人たち、二間幅の道路はいっぱいに埋まってしまった。
大きな布団を肩から背負った人、赤ん坊を背にし、両の手でしっかりと幼い二人の子どもの手を引いて、懸命に逃げる母親。みんな小松川方面に向かって逃げて行く人たちだ。その道は一つしかない。
私たち親子四人も、その走って行く人波の中を夢中で車を引き、人々の後を追うようにして逃げた。しかし、逃げるにしたがって、身の危険を感じた人たちは、持って出た荷物を路上に投げ捨てて逃げて行く。その投げ捨てられた荷物で道は全く足の踏み場もないほどだった。
私たちその間をどう縫って逃げたか覚えがない。ただ逃げなければという感覚以外、何もなかった。車の舵棒と末の妹の手を握り、「かあさん!」と母を呼び、またすぐ下の妹の名を呼びながら、私は車を引いた。
(次号へ続く)
朝風94号掲載 2006.2月号
炎の風に追われて(2)
日立電気の亀戸工場付近を過ぎようとした時、隣の下駄屋のおばさんであったか、前の氷屋の嫁さんであったか、定かでないが、近所の人に出会い、七丁目辺りまで一緒に逃げたが、大勢の避難する人の群れの中で、分からなくなってしまった。その人とはその後、会うことはなく激しい火災の熱風に追われながら、やっと九丁目のはずれにある小松川橋のたもとまで辿り着いたとき、すでに対岸の町も真紅の炎に包まれていた。
逃げ場を失った私たち親子は、同じように行き場の無くなった人たちと共に、北風に乗って狂い回る火炎の輪の中で、降りしきる火の塊を消すのに必死だった。妹の頭巾、母の衣服にも火の粉がつく、あの時どのようにして消し止めたか分からない。ごーつと体内をつんざくばかりの爆音が、すぐわきを横切る。私たち母と子はそのたびに身体を一塊にちじめて布団を被り、息をこらした。路上のあちこちに焼夷弾の火炎が吹き上がる。敵機B29は、私たちを見下すようにその巨体を揺さぶりながら、悠々と海上の方へ去っていった。
いかに戦争とはいえ、いったいこれでいいんだろうか、なぜこんな怖い思いをしなければならないんだろうか。込み上げてくるなみだは、戦争に対する憎悪の涙であった。
悪夢のような一夜が明けた。末の妹は、いつどこで怪我をしたのか、片方の目が紫色に腫れ上がり、痛さをじっとこらえている。でも私たちは何も言わなかった。ただ生き延びることが出来た!と言うことだけだった。こうしてようやく私たちにも、周囲を見回す余裕がでてきた。と、すぐそばの路上には数人の死体がころがっていた。
それからどのくらい時間が経ったか、口伝えで知ったのは、浅間高等小学校が焼け残っているということであった。この小学校へ行く道には、戦火をくぐり抜け、生きのびてき来た私たち被災者であった。みな一様に肩を落とし、重い足を引きずるようにして学校に向けて歩いた。どの顔もどの顔も火煙に煤けて真っ黒、ただ猛火に痛みつけられた目だけが、赤く充血していた。校庭を通って私たちは講堂に入る。講堂の中には三々五々、人々がうずくまっている。皆無言だった。
私たち母と子も空いているところに座った。少し落ち着いて気が付くと、大八車はどこでどうしたのか、母が大事に抱えていたものは、といだお米が入ったお釜一つと、一枚の布団だけであった。
再び夜が来た。その夜はまた、寒さの殊に厳しい夜であった。私たち母と子どもたちは、残された一枚の布団の下に身をすりよせ、互いの体温で温め合った。またもや警報が体の底にしみ込み入るように鳴りだした。
三日目の一二日、母と私は自分たちの家がどうなっているか気掛かりだったので、余塵のくすぶる町中を出掛けた。一面焼け野原と化し、どこを向いても生まれ育った町の面影はなかった。わが家の跡に近くなるにつれ、逃げ遅れた人たちが焼死体となって路上のあちこちに転がっていた。どぶに上半身を突っ込んで裸になって死んでいる人、三本の棒炭のように、黒焦げになった母子の焼死体。セルロイド状の色になった半焼けの死体など、おびただしい焼死体の惨状は、その夜の空襲がどんなに酷いものであったかを物語っていた。累々と横たわる老人と子ども、母親の無言の悲しみ、苦しみがひしひしと胸に響き、私は言葉を失って黙って歩いた。
水神様の所へさしかかった。水神さまもまた跡形もなく焼失し、わずかに鳥居の敷石だけが目印となって残っていた。水神さまは町内の氏神さま、一日と一五日は町の人や婦人会の人たちの参詣が多く賑わった。また私たちにとっても、幼い頃の心のふるさとに連なる、数々の思い出のある神社であった。
どれほど歩いたであろうか、ようやく亀戸五丁目一八四番地のわが家の焼け跡に着いた。近所の人たちはみな無事だろうかと案じつっ辺りを見回した。
しかし、近所の人は誰も見当たらない。茫漠とした焦土がどこまでも続いていた。よく見ると、角の自転車屋さんの店先あたりの所に母子と思われる焼死体が焼けぽっくりのように黒く焦げて二つ並んでいた。溢れる涙と、やり場の無い怒りがこみあげてきた。私の母はまばたきをしながら「南無阿弥陀仏」と手を合わせていた。
母と私は土中に埋めておいた瀬戸物類を棒切れで掘りはじめた。田舎に親戚のないわたしの家ではこの空襲で、全くの無一物になってしまった。その上その時、父の行方、生存も知ることは出来なかった。とにかく誰かが尋ねて来ても判るように立て札を作ろうと、焼け跡を見回した。と、そこに赤く焼けたトタン板が一枚あった。私はその赤く焼けたトタン板に、母子みな無事であること、および避難先を焼けて出来た木炭で何回もこすって書き付け、その立て札を我が家の焼け跡の中にしっかりと立て、避難先の小学校へと戻った。
その日、軍から乾パンの配給があり、層災証明書も発行された。
翌日のこと、その消息を心配していた父が、無事避難先に姿を現した、私たちは家族の無事を共に喜び合った。父の話によると、あの夜、警防団員として最後まで町に残り、雨のように無数に落ちてくる焼夷弾を、他の団員と懸命に消しているうち、気が付いてみると辺りはすっかり火の海となり、煙の中を這うようにして、命からがら亀戸駅の線路上まで逃げ延びたと言う。しかし、そこも安全な場所ではなく、火災から生じる熱風と激しく吹き付ける北風に立ってはいられず、線路と枕木の間に横になったと言う。
風に舞い、狂い叫ぶような火の粉は、容赦なく体に降り落ちて来て、服が燃える、そのたびごとに手で払いのけるが、燃え広がる方が早く、そのまま体をゴロゴロ転がし、服に燃え付く火を消し、かろうじて一命を取り留めたという。また、同じ場所に避難した人たちが、熱風に煽られてバタバタ倒れて行く様には、全く生きた心地はなかったとも言った。
父は夜が明けると間もなく線路伝いに歩き、五反田の知人の家を頼って行き、そこで火傷の手当をしてもらい、体を休め、ようやく今日、あの世以来別れたままの家族や家のことが心配で、ここに尋ね当てて来たという。途中、浅草橋、深川、本所と、焼け果てた被災地のどこもかしこも、そこには焼死体となった犠牲者が、路上に置き放され、葬る人とて無く、その中を何時間も歩いているうち、これでは女・子どもだけでは逃げ切れるものでは無い、家族のことを思い、とうてい助かる見込みはないと、半ばあきらめの気持ちになって、わが家に向かったという。家の近くまで来ると、焼け跡に何やら立て札のようなものが立っているのを見つけ、急いで駆け寄り、何回もその立て札を読み返し、皆が無事であることを噛みしめ、はやる心を押さえながら、避難所に当てられた小学校を尋ねて来たと言うことだった。
五日目、私たち家族五人は小学校を出て、再びわが家の焼け跡に来たが、近所の人たちの消息は、誰一人として知ることは出来なかった。亀戸駅の省線のガード下に逃げ込んだ人たちは、蒸し焼きのようになって死んだという。その数、何百と、人から人へと伝えられていた。
私たち家族は、一枚の布団と空のお釜、そして少々の瀬戸物を持って、池袋の親戚の家に、一時避難させてもらうため、住み慣れた町と別れた。亀戸、本所、探川、両国橋と行くうちにつれて被害状況は酷くなり、さながら地獄絵そのものの惨状であった。
本所辺りであったろうか、兵隊さんたちが、路上の焼死体の山を鳶口のようなもので、ひょいっと引っかけてはトタン板の上にのせ、それをトラックに運んでいた。まるで炭俵でも扱うように、機械的に動いていた。延延と続く死体の行列、その惨状を目の当たりにした私たちは、いつか放心したようになり、家族はみなただ黙ったまま歩続けた。
どこをどう歩いて来たのか、はたまた電車に乗ったのかどうかも覚えていない。気が付いてみるとそこは親戚の家であった。その親戚にはすでに他の被災者も避難していた。親戚の家に汚ち着いた私たち家族は、やっと生気を取り戻すことが出来たのである。
罹災から一週間目、私は銀行へ出勤した。職場の方たちは無事であった私の姿をみて、あのすざましい東京大空襲、猛火の中を、よく潜り抜け、生き残り、助かったものだと、共に喜んで呉れた。 私が一六才の時のことである。
朝風95号掲載 2006年3月

戦争と差別 ~一兵士としての体験から~
「戦争と差別」は一九九五年七月一〇日に四日市工業高校の人権講話で近藤一さんが講演したものです。
☆
近藤 一
皆さん、こんにちは。ただ今ご紹介にあずかりました近藤一です。年令は七五才、桑名市に住んでおります。暑い中、たいへん疲れてみえる中をくどくどと私の話を聞いていただくのは、たいへん申し訳ないのですが、今日は人権ということについて、戦争をとおして話をしろと言われてますから、自分の戦争体験、あるいは戦前にはこういう教育で差別というものがありました、というようなことをお話させていただきます。
小学校で最初に教えられたこと
わたしは一九二〇生ですから、大正九年ですね。小学校に入るのがちょうど大正一五年、昭和天皇にかわる時期です。小学校に入り一番最初に教えられたこと、これは皆さんご存じないと思いますけど、当時は奉安殿いわゆる天皇、皇后の写真がきちっと立派なセメントづくりの部屋に飾ってあり、それに対して敬礼をして校門へ入ること、これを小学校一年生の小さな頃から教えられている。それは後年に至って、まず差別の第一歩である、とわたしは思います。当時、小学校のときは、そうは考えられません。そういうことをせなあかんということで、敬礼をし、君が代も歌い、日の丸も見、そうやって成長していきました。
徴兵検査で四つんぱいに
軍隊に入るのは満二〇才で、徴兵検査というものがあります。徴兵検査には素裸で、越中ふんどしひとつになり検査を受けるんです。越中ふんどしになってどういう検査を受けるかというと、まず男のシンボルを握って、しごいて、いわゆる性病があるか、ないか。
その次に四つんばいになる、犬の格好ですね。そして肛門の検査。これは痔疾といって、痔の病気があると行軍ができないんですね。軍隊では間に合わないということでペケになってしまう。
そこでもう、いわゆる人間の尊重とか、何とか、いっぺんに吹き飛ばされてしまう。完全に俺はダメな人間だっていうふうな、本当になんていうかね、悲惨な、悲惨なんて言うとおかしいですけど、そこで人間の尊重というものをなくして、そして軍隊組織の中へ入れていくというのがありました。
残飯を漁った初年兵時代
中国の今の天津から北京へ行きまして、北京からずっと南下して石家荘というところがあります。石家荘から西の方へ入って山西省、山ばっかのとこなんです。その中のある一つの部落の所に私らの一三大隊といいますけど、大隊がありまして、そこで初年兵教育を受けました。軍隊に入りますとご存じのように、これはもう上下階級を根本にして成り立っていますから、人権とか、差別というような、そんな言葉も考えも何もありません。
一番驚いたことを申し上げますと、初年兵に入りますとものすごくお腹がすくんです。朝五時ごろ起床ラッパというのが鳴ります。飛び起きます。
すぐに班内の掃除とかいろんなことやる、整列する、朝食になる。朝食も、もう本当に一秒か二秒で、本当に一秒か二秒で、そんで飯が食えるかと言われるんですけど、パパアーッと飯を食っちやって次の行動に移る。
その場合に私はあまり活発な青年でなかったために、ご飯を食べるのが遅いんですね。取り残されると三分の一ぐらい食べてもう終わらなきゃならない。
そういう結果がずっと続きまして、結局お腹がすくっていう状態になって何をやったかと言いますと、炊事場へ行くと残飯が、大きな甕に人っていまして、その残飯の中へ手をつっこんで食べるんですね。豚の食べるようなものを食べる。そこまで一個の人間が落ちてしまうんです。
そういうことから軍隊では非常に厳しい軍隊生活というものをやらされたわけです。さきほども言いましたように、まず腹がすくっていうことからもう犬、野犬と同じ状態ですね。
殺し方を教わる
次に何を教えられるかといいますと結局人を殺すこと。人を殺すことはどういうことかといいますと、そういう感触をもてということで、ある日初年兵が集められました。
そこに中国の人が二人後ろ手にくくられて、目隠しはしていないんです。捧にくくられていました。それを私ら初年兵が、こちらから三八式歩兵銃という小銃を持たされてますから、その先に銃剣を着けて、突き刺すんです。
最初、人を殺すんだということで、自分の良心というものが多少残っていますから、ああ人を殺すんだなあ、ということでちょっとグッときたんですけれども、それでも特にそれが悪いこととかどうとか全然思わないんです。
それはなぜかというと、小学校の時から教えられたのは、中国人は、チャンコロ。もう本当に侮蔑した言い方ですね。チャンコロだということで、我々は大和民族、世界で一番優秀な民族である。そういう差別から教えられているのですから中国人、チャンコロを殺すのは別に悪いことでもないし、痛ましいことでもないということで、初めて生身の人間を剌すという手ごたえを覚えたのであります。
次にー〇日ほどしてから、今度は首を切るのを見せるというので、これもまた二名の中国人が後ろ手にくくられて座っていました。首を前へさしだしているところを、当時の准尉、下士官の上の人ですが日本刀で首斬りをやりました。
ところが、首は三分の二ほど斬れて、あと三分の一は残るものですから、苦しんでいるのを無理やりにまたそれを斬り捨てるということで殺しました。
次は下士官が、中国の青竜刀という刀があります、それで斬ったんです。これはものすごく斬り方が上手か、青竜刀がいいのかわからんですが、スパッと斬れ、首が前ヘコロコロッと転げました。もちろん大動脈から血がパアーッと吹き出しますね。それを見せられても、別にそれは当たり前のことで、痛ましいとか、そういう考えは全然起きないのです。
そんなふうに人を殺すことを何とも思わないのは、教育で差別意識というものを植え付けられてきたからです。その上社会に出ても、わたしは丁稚奉公である商店に勤めたんですが、そこでも上の人はご主人であり、我々は丁稚、小僧であるということで、厳然たる差別の中で六年間商店に奉公してました。
軍隊の生活も差別という点では同じです。当然、二等兵、一等兵、上等兵、兵長、伍長と上を見ればきりがない。大将まで何十段というほどある。 だから人権、差別ということは、あたりまえで、当時はそういう言葉も知らないぐらいなんです,差別ということは当然、私らは子供時分から体で覚えていますから、差別はあるんだということで、これが社会なんだということで大きくなった。
古年兵の凄惨なしごき
初年兵教育でいろんなことを教えられて、今度は中隊に入ります。中隊というのは、約二〇〇名ぐらいの人です。その中へ初年兵が七〇名ぐらいで入ってきます。
中隊へ入りますと、今度はそこにはさきほど言いましたが、上の兵隊で古兵、二年兵、三年兵、四年兵がいるわけですから、当然差別があるわけです。
初年兵は、入って何をやるかというと、まず古兵の洗濯物、これはふんどしから何から一切全部をやります。それからめし、あの食事です。食事の盛り付けとか、上げたり下げたりするこれも全部です。初年兵はそういういろんなことをやって、古年兵は何をしとるかというと、何もせずにばくちをやっているのです。
その部屋の中で、麻雀をやったり、あるいは将棋を指して、その中で初年兵は、一日中動きづめなんです,何か失敗があると、お決まりのビンタ、制裁が加えられます。
この制裁の一番ひどいのを見ましたのは、私の同年兵でちょっとあることをやって、助教の部屋へ呼ばれて、三〇分ぐらいして帰ってきました。顔がこんなにはれあがって、目の色は白いところが、一日目は真っ赤になって、二日目はそれがもう紫色になり、顔がこんなにはれてしまった。
何でそんなに殴られたのかというと、手ではないって言うんですね、帯革と言いましてバンドですね、軍隊の。それに八番線の銅の尾錠がついているんですが、その尾錠で殴るんです。しなるんですから、ものすごいたたかれ方をします。だから無残な顔になってしまう。
そういう私的制裁を受けました。
それから軍隊の靴というのは、靴底にイボイボがずーっとついている。かねのイボイボが。
靴の手入れの場合、そのイボイボに多少でも土がついたりしている場合には、検査をさせられて、靴のその土を舐めろと言われる。
イボイボのついているところを仕方がないから、きれいに舐めて、その上こう見せて、しましたと言うと、それを一足ひもで結んで首ヘかけ、今度は各小隊を回って来いと言われるんで、回って行きますと、小隊の古兵がいて貴様何をしたと言う。
実は靴の手入れが不十分で、きれいにしてきましたから見て下さいというようなことを言うと、貴様、その天皇陛下からお預かりしたものを粗末にした。
こういうことで、またそこでもピンタをくらいました。それを四個小隊、四ヵ所を回って繰り返しやられる。
討伐と称して
さて、今度は討伐とか戦闘状態になるとどういうことになるのか。 中国の山西省は先ほど言いましたように、山ばかりなんですね。
谷合いに小さい部落がー〇戸とか二〇戸、あるいは多いのは一〇〇戸ぐらいあるとこもあるんですが、ほとんど小さな部落で、そこヘ八路軍、共産軍がいるということで攻め込みます。
共産軍がいた場合、ずっと山手の方へまず逃げていきます。その後、住民なんか荷物を持って逃げます。 日本車がパアーと入ったおりには、老人子供あるいは足の弱い婦人しかそこに残っていません。
そうしますと我々兵隊は何をするかというと、まず第一に金目の物がないかどうか、お金に変わるものがないかどうか、それを取るということ。
次には、お定まりの女の人を見つける。二十代三十代の女性はほとんどいないわけですが、たまにいたこともありますけれども。まあ歳のいった人、五十代、六十代の人までいれば、皆さんもお聞きしておると思うんですけど、輪姦ですね、強姦、それを競ってやるんです。 初年兵のおりにはそれを見まして、なんてことをやるんだ!と思って、それを見てるだけなんですが、二年、三年経って古年兵になってくると、やはり同じようなことをやるんです。
老人の耳を削ぐ
私の同年兵でちょうど二年兵でしたけど、ゴボウ剣、いわゆる銃剣、歩兵の持っています短い五〇センチくらいのものなんですけど、それを砥石で磨いでいたんです。
何をやるのかなと思って見てましたが、ある日の討伐の折りにパアーッと部落に突入すると、みんな逃げてしまった。
段々畑のとこの陰の所に老人夫婦だけが二、三組固まって隠れておりました。そうしたら、砥石で磨いていた兵隊が老人を一人ずつひっぱりだして耳を削ぎだしたんです、それを見て、私は思わず止めに入ったんです。
こんな老入たちにおまえは何をやるんだ。そしたらその兵隊は、同年兵ですから対等にものを言いますけど、向き直って何を言っている貴様、これらの子供が八路軍で今我々を射ってきたんじやないか,我々の戦友がそれでけがをし、また死んでいるんじやないかと。
当然この老人なんかは同罪だ、まだ殺さんだけいいんだと、耳削ぐらいお安いことだと言うて、血相かえて私の方に向かってくるような状態です。
これ以上、止めようがないということで、私はさっとその場を離れたんです。 耳を削ぐ、それも老人の。そんなこと出来るかって、皆さんに聞いてもそんな事とうてい出来ないし、ありえないことだと思われるんですけども、当時の中国では兵隊はそういう事をやっていた。
私も実はそんな事をやっているのは、自分らの部隊だけなのかと思いまして、この北支じやなくして、南の揚子江方面の中支、あるいはもっと南の南支の方にいた古い兵隊のところへお邪魔して、おたくら中国でどういう悪いことをやっておられました?と聞きましたらやはり同じようなことを言っているんです。私も、あっ、やはりどこでも同じなんですね、日本軍はやはり同じようなことをやったんだと思いました。
赤ん坊を谷底ヘ
行軍中のことですが、前の日の戦闘で一人の女の人を捕まえました。三十前後の若い人で赤ん坊を抱えていました。で、お決まりの輪姦をし、翌日の行軍、いわゆる山の稜線上を歩いて、次の敵を追っていくという行軍の中へその女を入れ、連れて歩いたんです。
段々と弱ってきました。 小休止、休みのおりにそばでぼそぼそ兵隊が「弱っているがどうしよう」と話をしてたと恩ったら、私のそばにいた兵隊は、女の人が抱えている赤ん坊をわしづかみにして谷底へ投げ捨ててしまった。
三〇メートル、四〇メートルの断崖絶壁のところでしたから亡くなっているはず。と、その婦人は同じように、そのあとをパッと追って飛び込んでしまった。もちろん亡くなってます。
それを見て、私自身もそうですけど別に罪の意識とか何にも感じないんですね。あっ、また死んでしまったかという程度しかない。
それほどに人間というものは、変わるのが恐ろしいんです。だから、最近の才ウム真理教ですか、あの事件を最初私がテレビで見たとき、あっ五五年前の我々の中国にいたあれとそっくりだと、そう思いました、瞬間的に。
人間はマインドコントロールされてしまうと、どうにでもなるんですね。ただ戦前の教育というものは、私がさきほど言いましたけど、小学校では奉安殿、日の丸、君が代から始まって、もろもろの教育をずーと一方的に受け、いわゆる差別の中でチヤンコロは別にあれは民族でもない、本当に下層民族だ。
朝鮮民族、これも本当に弱い民族なんだ。弱いから、日本はあそこを植民地にしたんだ、こういうふうに教えられるから、あっ朝鮮の人もあんなに弱々しいんだな、と結局差別で見てしまう。
だから、人権や差別の問題は、戦前の私らの姿、自分の体験したことから、今考えると本当に重要なことだと思います。今の憲法はそのことをはっきりと、人権ということを擁護しているんです。
沖縄ヘ
私らは中国に約四年間いて、散々悪いことをし、昭和一九年四月河南作戦という黄河周辺の大作戦があって、ここで四ヵ月間いろいろなことがありましたが、悪いことをやって、その年の八月上海から沖縄へ行ったんですね。
沖縄に行った場合に何を一番最初に感じたか。まだ一週間前に人を殺し、あるいは女の人を犯し、中国の人の家を住めないように破壊してしまう。そういうことをした兵隊が沖縄に上陸し、本当にあおーい空であおーい海で、緑がしたたるような何事もない本当に平和な、あーっ本当に平和だ、戦争のないことはこんなことか、そこで平和ということはなんてすばらしいもんだ、ということを身にもって感じたんです。
さて沖縄に上陸して、今度は兵舎というものがないのですから沖縄住民の方の家、民家に各分宿するわけです。すると、その日からもう沖縄の人の文化や生活に接するんです。
一番最初感じたことは、あっ、どっかこれは本土、こちらのことを本土、本土と沖縄の人は言いますが、本土と沖縄はどっか違っている。
それから言葉はみなさんご存じのように方言で何もわからない。で、ちょっと気がつきますと豚の飼い方、山西省では豚の飼い方はいわゆる人間の排泄物を食料にし、だいぶ広い場所が飼育場として石積みしてあり、いわゆる糞尿がそこにはいっぱいになっておるんです。そこで豚が飼われているんですね。沖縄の地方の農家でしたから、豚をちゃんと飼ってるんです。やっぱ同じ飼い方で、人間の排泄物で豚を飼っている。あっ、中国とそっくりで同じゃないかというとこから、ひょっとして中国の方からこう渡り歩いて沖縄の人がきたんかなー、というようなことを口には出さないんですけども、みなそれぞれ兵隊がそういうことを感じてる。
そこにまず第一に出てきますのは、さきほど言いましたチャンコロ、それが沖縄の人にも結局チャンコロ、それに準ずるんだというような気持ちを各兵隊は持ってぎたんですね。
そうしますと極限状態の戦場になってくると、もうもろにそれが出てくるんです。で、今言われるように集団自決、いわゆる日本兵に斬り殺された、食料を強奪された、今もいろいろなことが言われています。そういうのはいわゆる差別意識がずーっとつながって、中国で体験し沖縄に来て、あっ、沖縄の人もこうなんだということから、やってはならない同じ日本人同士がそういう状態になってしまった、と私は思っています。
もうひとつ細かいことを言いますと、当時沖縄はお米を作る場所が非常に少ないんです。だから、常食はさつまいもですね、おいしいいもです。さつまいもが常食で、お米はただ盆とかお正月に使うだけだと、沖縄の方が私に話してくれました。
食用のさつまいもはおいしい、それからタピオカという澱粉状にして、まあ片栗みたいなもんですけれども、それもものすごくおいしいのです。
私ら民家で、沖縄の人は、みんなやさしい方ですからご馳走なったりなんかして、沖縄の文化の一端を知りました。
沖縄は琉球王国であって、明治に人って沖縄処分で日本に併合というとおかしいですけれども、日本国になったという、そういういろんなもろもろのことがあったということを、我々小学校出は何も知らない。
沖縄ではこういう立派な違った文化があって、海洋国なんだよといろんなことを、軍隊で言ってもらえば、戦場であれほどの差別をするような意識はおきないはずなんだと思うんです。しかし悲しいかな何も知らされていなかった。
米軍上陸
私らは一九年の八月に沖縄の那覇港に上陸しました。 各地に分宿しました。私たちの行ったところは、那覇港から首里をもっと北上した宜野湾村、今の嘉手納飛行場のちょっと南の方なんです。沖縄というところは、東西に細長い島で約百二、三〇キロ、その三分の一以下、ここが主戦場なんです。三分の二以上のこちらは山が多くて、くにがみといいます。くにがみの方は日本軍が四、五〇〇〇名いたのですが、ゲリラ戦のようなことをしていたので、戦闘らしい戦闘というのはないはずなんです。嘉数というとこが私らの守備陣地になり、ここへ四月一日に米軍が上陸を開始した。
その前に三月二六日か、二七日に慶良間列島といって、こちらへんの小さい島、そこへ米軍が初めて上陸してるんです。
この慶良間列島では、今伝えられているあの集団自決が、何百人ってありますね。それから日本軍が惨殺したということも。この諸島では、小さい島が多いんです。
四月一日、無血上陸。これはなぜ無血上陸させたかというと、その前のサイパンとか硫黄島での水際戦術で、米軍が上がってきたうえで、砲撃で撃ちたたいたところが、お返しに艦砲射撃や何かやられて、砲兵の陣地がほとんどつぶされてしまったという体験があって、一応沖縄の場合は、上げるだけ上げさせて、地上戦を主力にしてやろうということで、無血上陸させたんだそうです。当時は私たちは知りません。上がってきたのを、私たちは見ているんです。
私たちは、上がってきたところの五、六キロメートル南のところの陣地てしたから、海を見ましたら、本に書かれているように海が見えないという船ばっかりなんですね。
それから、あのM4という大きな戦車が上かってきたときに、日本の戦車はM4から比へると大人と子供との違いがあって、最初M4戦車見たとき、二階建ての戦車だというふうに思いました。そういう戦車をどんどん上げて、最初は四個師団、そのうちに最終的には七個師団になったんです。
米軍はここを南北に遮断して、北の方へ二個師団、南の方へ三個師団を戦闘配備につかせて、北の方へ行った米軍は一番北、辺戸岬というのですか、ここへ四月一三日に米軍は、もう達しているんです。
上陸してから一三日、二週間で、もうここへ行ってるんてす。こちらの方は、上陸してから一番南まで行ったのは六月の末になってるんてす。たから、こちらか主戦揚て沖縄戦か始まるんてす。一日に上陸して、私らの部隊はたまたま三〇〇○メートルから四〇〇〇メートルのとこしか米軍の第一線と離れてないところです。
米軍に自爆攻撃
三日目から戦闘か始まりました。アメリカの戦闘は、まず朝八時頃から、一時間から一時間半、砲爆撃それから野重砲、ロケツト砲をメチャクチャに撃ってきます。
最初びっくりしましたけどね。本当にメチャクチャに撃ってきます。
中国ではそんなこと全然なかった。中国では、ただ迫撃砲弾くらいのもんで、あとはもう重機関銃とか軽機、小銃、手榴弾の戦闘でしたから。
アメリカの場合は違う、砲爆撃、飛行機は上から、こう機銃掃射、爆撃やりますからもう目もあてられんという状態の中で一時間か一時間半するとピタッとやんでしまうと、今度戦車を先頭にして、その戦車のあとへ米兵か二、三〇人ぶらぶらしなからやってくる。
それに対して、日本軍はどぅいう抵抗したかというと、木造で作ったー○キロ爆雷、中にはダイナマイトみたいなもの詰め込んであるんてすけど、それを抱かえ込んで陣地の前ヘタコツボというを前の晩に掘って、その中に一人あるいは二人が隠れて、隠れているというとおかしいけど、潜んでると、朝になって戦車が来た場合に二、三〇メートル近寄ったとき、タコツボから飛び出して、その急造爆雷を戦車のキャタピラの下へ投げ付けるんてす。
その繰り返しの戦闘なんてす沖縄は。米軍の戦車と日本の歩兵一人一人が、戦車にぶつかっていくのが戦闘の主体なんてす。これはもう自殺戦闘と言いますかね、死に行くのに、本当に成功率はー〇パーセントかせいぜい二〇パーセントまでなんてす。
米軍もそういう戦闘を知りますと、次の日からは戦車か来る場合は、地面を射ちながら進んで来るんてす。
機関砲で、バリバリ下を射ちなから、攻撃してくる。タコツボに潜んでいても、機関砲によって射ちぬかれて、結局飛び出すことか出来ないという状熊になってきた。
火炎放射器の恐ろしさ
あるいは、火焔放射器で、こ存じのように火を噴き出すやつ、それを中間から使いだしてきた。小銃とか機関砲とか、そういうものは瞬間的にパアーンとかクワーンときても、避けられる場合があるんです。
ところか、火焔放射器の戦車の場合は、八〇メートルくらいパァーと飛んてきて、広がる範囲は、三メートルから五メートルくらい広かっていくんてす。こう噴きますと、避けることは出来ないんてすね。そういうのはまともに噴きつけられると、もうベタべタゴム状のものがついて転げ回っても消えない、本当に黒焦けになって死んでしまう。焼け死にてす。
そういう悲惨な戦闘をしつつ、艦砲射撃を受けたり、飛行機でやられる中をわずかに歩兵が戦闘をやって、ニカ月間首里の線まてもったわけです。
首里の線になってきますと、これは本当の死闘になってきます。一つの陣地の私のそばでおきたことを申し上けますと、守備陣地は、台状の前に出ているところを両側くりぬいてあって、その中に中隊かいるわけなんてす。
前の方から米軍の戦車五、六台やってきます。で、両方のとこへ戦車砲を打ち込んで、穴 をつぶしちゃうんですね、入口を。
それを見て、我々兵隊は砲弾の間隙をくぐつて、その穴を中からシヤペル、小さな円匙というスコップを歩兵はみんな持っていますから、それで穴をあけて前の陣地に、また守備につく。
戦車があんじょう同じようにやってくると爆雷とか持って飛ひ込む、あるいはまたこちらの方で戦車についてくる歩兵を狙い撃ちして殺す。
アメリカ兵の「ママ」の叫び
アメリカ兵もね、弾が当たる瞬間だふんはっきり聞いたわけではないですけどね、ママー、ママーという、そういうのたくさん間くんです。
転けた瞬間にママー、ママーと言う、大声でやりますから、こちらとしてはその当時は、あっ、ヤッターという気で、心の’中ではもう本当になんといいますか、喝采を叫ふというような気持ちになりますけども。
息が、息が漏れます
ある日、私と五、六人、守備陣地の人口にいたとき、バシャッと音がした瞬間に直撃で土煙かモーモーとたち広がった。
となりの兵隊がファーという声を出し、土煙がおさまって見ると、二重県の上野出身の兵隊で、東上等兵が、横腹をちょうど三分の一えぐられてしまった。戦車砲にまともに打ち抜かれたんですね、腸なんかの内蔵がダラーと出ているんです。
衛生兵に息がもれます、息がもれます、と息をするたびにブツブツと血が出てくるんです。衛生兵がそこをきれで押さえて、穴ふさぐような状態に手当し、大丈夫だ、後方へ送るからしっかりせいと言ってました。一時間足らずしてお母さんっ、て言って本当にかぼそい声で亡くなっていった。
美酒美食に耽っていた軍司令部
そういう戦闘をやっている最中に、あとで知ったことなんですが、軍司令部や後方ではどんなことをやっていたのか。
一つの例を言いますと、長参謀長というのはその当時陸軍少将、豪勇で当時日本軍人の鑑といわれ、慕われている人らしいんですけれども、たまたま沖縄に参謀長としてこられた。
この方は非常にお酒好きで酒豪であって、それから料理は絶対兵隊の作ったものはあまり食べない。
普通将校には、兵隊がついて兵隊が料理したものを食べていたんですが、長参謀長に限って専門の板前を沖縄戦の最後までそばにつけていた。
酒はウイスキーが好きで、各国のウイスキーがダーツと並んでる状態だということを、生き残って帰った長参謀長の副官から、私は直に聞いたんです。
そのとおりです、とその副官の方は言われました。それを聞いた私は、前線であれだけ兵隊が転げ歩いたり、無残な死に方をしていたときに、後方の師団司令部とか、あるいは軍司令部というものはそんなことをやってたのかと怒りに震えました。
ですから五月三、四日の大反抗だとか言われるおりでも、他の師団の二個連隊半というものが、一時間足らずでふっとぶようなまずい戦闘をやっているんです。
なぜそんなまずい戦闘をやったかということを私なりに考えると、われわれが前線で転げ歩いて、守り守っている戦闘の状況を、後方にいる師団長とか参謀長、作戦に関係のある者が前線視察というか、見に来てないと思うんですね。
見に来ていれば、一時間足らずに五千名もふっとぶような戦争というのはやらないんです。同じ戦争をやっているといっても、違った面がいっぱいありました。
最前線で闘った兵士として
一九八三年、教科書問題でバァーッと沖縄戦の状況が暴かれました。
伝えられている沖縄戦というのは、日本兵が悪いことばっかりしてたんだ。子供を殺し、食料も強奪する、壕を追い出す、言うことを聞かなきや切り殺す。そういうことばかりやっていたんだというふうにずーっと伝わっていて、沖縄の日本兵は何してたんだということになりました。
最初から最前線で戦った私たちはそういうことは全然知らなかった。歩兵として最前線で九〇日間戦いの明け暮れで、そういうことは周囲に見たこともないし、まして前線のアメリカ兵と戦っている時には、沖縄の人はそこにはいないんです。さっき言いましたように、島尻の方に沖縄の人は皆疎開していました。
私は沖縄戦が曲がり伝えられていると感じました。
バスガイドの説明に唖然
皆さんが沖縄へ観光に行きますと、摩文仁の丘というとこに、各県の慰霊碑がずーっと並んで建っています。
その最先端の一番上に「黎明の塔」というのが、軍司令官と長参謀官の自決した場所に、慰霊碑として建ててあるんです。
その塔の説明を私は沖縄に行ったときにバスガイドから聞きました。
「く」の字形になったこの塔は、切腹した形が「く」の字形だから、その形をとって碑ができた。頭を下げた方は、実は牛島司令官の郷里が鹿児島であるから、鹿児島の方に対して、こう切腹して頭が下がっている、その碑の形が黎明の塔。
軍司令官は立派な方であり、参謀長も立派な方であった。だから、軍司令官は日本陸軍最後の陸軍大将に昇進された方ですと軍司令官のことを立派に褒めたたえるようなことをガイドさんが言った。
これは、私ら最前線にいた兵隊から見ると全然違うんです。それで、私はガイドさんちょっと待ってください。今、ガイドさんが説明されたことは、ガイドさんが勉強されてそういう説明されたか、あるいは会社からこういうふうに話せ、ガイドせいということで言われたかわからないけれども、私は二〇何年前、今この見えている前のあの台上、あの海岸線、そこを転げ歩いていた兵隊の一人。
その兵隊から言わせれば、もし軍司令官参謀長が立派だといわれるんだったら、なぜこの島尻の方まで軍隊を下げて戦う必要があったのか。ここには、二〇万とか三〇万という沖縄の県民の方が、いっぱい隠れて戦火を逃れていたことははっきりと分かっていたことなんです。分かっていながら、もう首里の線がダメだからこちらへ下げよといって、五月の末に全部、当時まあ二万とか三万といわれた日本兵が下がった。下がった結果、今言われているようなー〇何万人という沖縄住民の方が悲惨な戦場に巻き込まれてしまった。
私ら石兵団は首里の線で玉砕しようと思って戦っていた。ここで八〇パーセントの戦友は亡くなり、傷ついた。
五月二二日に下がるという協議があっだ時、私らの師団長は、下がらない、私らの師団は首里の線で玉砕します。
ここにはたくさんの戦友があちこちの洞窟に人ってます、それを見捨てて下ることはできません、ダメですといって反対した。
いや、一日でも持ちこたえなければいかんから下がれという軍命令でやむをえず、自分らの師団も付いて下がった。 下がったため、さきほど言いましたように、沖縄住民が悲惨な、今伝えられとるような沖縄戦になってしまった。
あのおり下がらなくて、首里の線で戦を終わっておれば、少なくとも一〇何万人の沖縄戦戦没者は、五万人とか半数以下に減っていたはずです。自分のみのこと考えて結局武人として立派に戦った、玉砕した。それを後世に残したい、その思いが先立っているとしか、私には思えない。
前線の兵隊が何人死のうが、何しようが、それはもう問題外、島尻で沖縄住民が五万死のうが、一〇万死のうがそんなことは何とも思っていない。自分らのそういうことが、それで達すればそれでいいんだ。そうとしか私は考えられないんですね。
軍隊は住民を守らない
戦争では、軍隊というものは、住民を守るもんでもないし、住民のために戦うものでもない。時の権力者とか時の体制が、あるいは時の都合のいいように戦争というものを起こして戦い、その結果については、悪いことはみな伏せてしまって、いいことばっかりだったと言って体制を温存する。
その基本に何があるか、差別です。一般の市民社会でも差別。軍隊に入っても差別。戦場になった場合、とくに差別がひどい、沖縄の場合がその筆頭ですね。
だから私はどこに行っても言うんです。今日本は経済大国とかなんとか言われて、本当に飽食。オウム教みたいなヘんてこな事件いろいろ出てきます。
今年はとくに一月阪神大地震があって、本当にみなさんブラウン管で、また現場へ行かれた方もあったと思いますけども、ああ悲惨だな、五千何人も亡くなられた、負傷者の方も多い。家が無くなった方が何方といる。ブラウン管で見てああ大変だなと思われる、これは当然なんです。
ところが戦争になればあんなこと、あんなことという言葉、私は絶対いけないと思いますけど、ああいうことは、もうほんの些細な、些細な一部分にしか私には見えないです。
戦争になったらあんなもんじやない。沖縄住民の人は、昭和一九年一〇月一〇日に大空襲があって、それ以後、毎日艦載機が来て、もうずーっと空襲の連続。
四月一日に結局アメリカが上陸したが、これは戦闘で、空襲よりももっとひどい。その連続が半年以上も十ヵ月間ずーっと続いて、その中に一家全滅したとか、亡くなってるとかたくさんあるわけです。
だから戦争というものは、本当に何もかも破壊してしまう、その人の人格も破壊してしまう。その人格も破壊してしまうような戦争にどうやって、一般の大衆を導くかというと、差別ということを土台にして、みな頭とか精神状態をその方向に感化するといいますか、もう異常なまでの感化。
だからオウム真理教が、ああいうエリート人が、なぜあんな馬鹿なことをやったのか、本当に不思議に思えるんですけど、いや、そうじゃない自分らが五〇年前はあのとおりだったんだなあと、私は最近つくづく考えています。だから、差別ということは、これは戦争を起こす元なんです。差別で、いわゆる社会体制を牛耳っていけば、簡単に戦争へみな導いていける。前の大戦が、戦争がそうなんですから。簡単に日本の、あの当時本土の人口は七千万か八千万といわれていたんですけど、みな戦争一色に突っ込んでいった。
戦争責任を曖昧にした一倍総懺悔
戦争が終わって、まず第一に考えたことは何か。内心では、ああ戦争終わってよかったなあ、と考えた人がほとんどなんです。 しかし戦後最初の内閣から出てきた言葉が、一億総懺悔。我々は戦闘して戦ったけど、本当に負けてしまいました、悪うございましたといって、一倍総懺悔で謝るといった方向にいってしまった。それが間違いの元です。 そういうように情報操作でうまくやって、結局あの戦争において加害ということをみな伏せてしまう。いわゆる被害、我々人民も一生懸命やったけども、結果は被害者だったんだ。謝ります、戦争に負けて謝ります。だから広島原爆についても、あんなひどいことがあって本当に被害者だと。
中国でいろんな私らがやったこと、加害のことは、日本の今の社会においてほとんど知られてない。実際には差別というものを根本にしたところから出発して、上からいろいろ言われることは、それは正しいんだ。正しくなくても、それに従っていくのが日本人なんだ、というようなことで慣らされてきた結果が五〇年の今日。この間五〇年の国会決議て、なんかわけのわがらんことをやる。
あんな国会決議やったら、やらんほうがましです、結局謝りができないという、その元に何かあるかといいますと、なんべんでも言いますけども、敗戦直後にきちっとした謝罪、戦争責任の所在を明らかにしなかった。それが根本にあります。
だからこそ我々は被害者であって、東南アジアは植民地だから、それを解放した戦争だ。中国は軍閥があって乱れてたから、そこへ行って日本軍は治安をよくしたんだ、そういうすりかえをして侵略ではないという声が、今だもって体制側から出てくるのです。
なぜ語るのか
私らみたいな兵隊経験した者が、村へ帰っていろいろ話をすれば、ああ中国ではそんな悪いことやったか、シンガポールでもそんな悪いことやったんか、比島でもそんなことあったんか、いわゆるニューギニヤでは人肉だ、戦友まで食べてしまったんか、ということを皆さんが知り、戦争とは何か、あの戦争は侵略であり、戦争は悪いことであり、その当時の体制側が謝罪しないということは、どこに根本があるんかということまで考えてもらえるようになればと思うんです。
話が長くなって非常に悪いと思いますけども、皆さんは本当に前途ある青年のかたですから、戦争というものがどういうものか、今は本はいくらでも売っていますから、その本を読んでいただいて、自分なりに噛み砕いていただき、どこに戦争の元があり、どこに何があって、こうなったかということを考えてもらいたいと思います。
戦争は一握りの権力者が仕組む
最近いちばんひどいというのは、ヨーロッパで、あの旧ユーゴスラビアでね。あそこに今、ボスニアとか、セルビアですか。戦い、民族戦争、戦ってますけど、あそこの本当の戦争をしている生の声を、こないだある本でちょっと見ましたけど、あれはいわゆる冷戦体制というものが、あっという間に崩れて、そのあと共産体制というものがグラグラッと崩されていく。
すると、共産体制で統治されたとこで、いわゆる次ぎなる権力者というものが、民族を正面に押し立てて、あるいは、また宗教を正面に押し立てて、わずかな権力者がそういう方向にむかって、セルビア、クロアチア、ボスニアですか、あれほど仲良くしとったとこが、隣の人と、殺しあいをやっている。
これはすでに一握りの権力者が、自分のためにやっているんだということがはっきり書いてますからね。民衆がみな犠牲になっているんです。テレビで今ボスニアがどうなっているか、どうか見てください。
本当に悲惨な戦争が、一週間に一回は必ずテレビに出てきます。そのテレビの裏側に権力者たちが何をやっているかということを、なんとかいうセルビアの方にありますね。ガル何とか、ときどき議長とか何かいうのが、頭ボサボサしたのが出てきますけど、ああいう輩が民族紛争だ、民族のために戦え、といって戦争を起こしたとしか思えないということをクロアチアの人、女の人ですけどもきちっと書いておられます。
だから、戦争はどうして起こるんだ。日本の前の戦争はなぜ起こったんだ。これは日清戦争、今年は一〇〇年ですけども、日清戦争以来一〇〇年にわたって、その間の五〇年、どういう状態に日本はあったのかということを勉強してもらえば明らかになる。
大変長くなって、本当にお疲れのところを、訳のわがらんようなお話をしましたけども、いわゆる人権を守り、差別のない社会ということは、一番我々が平和を望んでいく、生活していく、家族が団楽する基本になっていますから、差別、こういうことを本当に頭の中に置いていただき、差別をなくしてください。なくすることに努力してください。それをお願いします。ありがとうございました。
朝風102号掲載 2007.3月

詩 玉砂利
京 土竜
それは昭和十五年
皇紀二千六百年を祝し
中国大陸の奥地に果てた股肱の将兵を
「英霊」として天皇自ら合祀する
靖国神社秋の臨時大祭
天皇を乗せた御羽車は
全ての灯りを消した闇の中を進む
ラッシユ撮影も許されぬなか
報えるのはただNHKラジオ放送
実況担当は不世出の名アナウンサー和田信賢
参道に額つく人びとを眺めつつ
星明かりに浮かぶ御羽車を報える
「漆黒ノ闇ノナカ御羽車シズシズト
参道ヲ進ミ イマシモ・・・・」
そのとき
ひとつの影が立ち上がり
怒声とともに石礫が御羽車に飛んだ
「偽善者!」
っぎの瞬開
闇に潜んだ警護の憲兵の拳銃が一発
見事に額を射披かれた男は声もなく倒れた
怒声も銃声も 夜の静寂に吸われたか
拳銃の吐いた火も 闇に遮られたか
和田信賢の静かな声が荘重に流れた
「沿道ニヒレ伏ス民草 寂トシテ声ナク
タダ怖レ畏ミテ御羽車ヲ送ル」
撃たれた男の名は知られていない
玉砂利を染めた血が黒ぐろと残った
「玉砂利」補足解説
京 土竜
これは、詠われているとおりの日時に発生した事件です。そのころ、私の貧しい家には四球式の安物ラジオしか無く、雑音混じりの放送を聞いていました。
ここに出てくる和田信賢アナウンサーは、NHK入社後の最初の仕事として、野球アナウンサーでデビューしました。その頃、全国の野球ファンを魅き付けた「早慶戦」の実況のなかで、延長戦に入ったとき、ピンチヒッターがまだ振らないと安心して「折しも暮れかかる神宮の森の上、三羽のカラスが・・・」のところで、バッター強振。
慌てた和田氏は、「打ちました、打ちました、球はグングン伸びて、ホームラン……」とやってしまいました。
今ならご愛嬌でしょうが、当時は謹厳実直NHK,翌日から局には葉書が殺到。いわく三羽のうちの、どのカラスがホームランを打ったのか、お教え願いたい」
これに恥じた和田氏は、どのような事態急変のなかでも動揺しない習練を続けました。一九三五年四月、・ラストエンペラー・薄儀が来日した際、その実況放送を命ぜられましたが、そのとき軍部から出された注意通達で、「天皇には最高の敬語を遣え。皇后にはそれより少し下の敬語を遣え。満州国皇帝・博儀にはそれよりもう少し下の敬語を遣え。その皇后にはそのまた少し下の敬語を遣え。随臣の高官にはその下の敬語を遣え」という、有名な「五段階敬語」を要求され、三時間を超える予定原稿なしの実況放送を一語の言い間違いもなく果たし、不世出の名アナウンサーの令名を得ました。
この『玉砂利』はその五年後の事件ですが、新聞でもラジオでも、一片の報道もされませんでした。それは私の(旧制)中学五年生のときで、その二年前には級友の一人が自殺しました。学校側はなんの発表もしませんでしたが、彼には心から尊敬する兄があり、京都大学生でした。そして、彼は私より早く俳句に取り組んでいました。
この『玉砂利』に登場する男性は、アナーキストで、姓は宮崎と伝えられていますが、詳細な正否は不明です。
なにしろ当時は、クリスチャンまでもが「傾向者」「主義者」といった曖昧概念に一括され、ときには特高警察やら憲兵隊で拷問に逢った時代です。
なお、彼が叫んだ言葉は、詩中にあるとおり「偽善者!」と伝えられています。
朝風102号掲載 2007.3月

長崎の原子爆弾 -私の被爆体験記-
松浦 アヤ子
毎年八月になりますと、八月六日の広島、九日の長崎の原爆犠牲者慰霊祭が報道で取り上げられます。それはどのように進められているのでしょうか。戦後六十年ということは、現在の日本国民の大部分の人が、六十年前のことはなにもわからないということでないでしょうか。
慰霊祭を企画執行する市役所の職員の皆さんは六十歳以下の人であるのは当然のことです。六十年前のことは何も知らないまま行事を進めているのは仕方のないことなのです。
原爆による被害、それは実体験のある人にしかわからないのです。その人たちで慰霊祭に参加する人は何人いるのでしょうか。そしてこれから先、何人いるのでしょうか。
私は結婚以来、東京の自営商店での仕事に没頭しなければなりませんでした。その仕事は八月の旧盆近くが一番忙しく、長崎の慰霊祭には参列することができませんでした。今日、八十七歳になり、仕事から解放されても老齢のため一人での旅行などとても不可能な体になってしまいました。六十年前のあの日、そのことが日本の国から記憶が失われるということは、私が悲しいと思うだけでなく、それは絶対に失ってはいけないことだと思うようになりました。慰霊祭に参列できなかったことへのお詫びと、自分の記憶が失われない限り少しでも書くことが私の責任のように思えてまいりました。
☆
昭和十九年になると国家総動員の機運がますます高くなってまいりまして、長崎市役所から町内会に女子挺身隊員(十八歳以上の未婚の女性)が割り当てられ、私もそれに参加し、大橋にある三菱重工業株式会社長崎兵器製作所(通称、三菱兵器)大橋工場に事務係として勤務、主として事務用品や配給品などの管理の仕事につきました。他に九州各県から集められた旧制男子中等学校(五年制)、旧制女子高等女学校(四年制)の四、五年生からなる挺身隊員など、現場の酸素魚雷の製造にかかわる工員の仕事に従事する隊員が多数働いておりました。
☆
一応任期は半年で交替ということになっておりましたが、半年たっても私はふたたび選ばれて再招集となったのです。今度は大橋工場の近くの丘陵地に数年かかって造られていた住吉トンネル工場が完成し、私はそのトンネル内での事務係となり働くことになりました。トンネル工場は六本のトンネルからなり、内部はトンネルで接続され、数十台の旋盤や他の機械類が並べられて、多くの作業員が働いていました。ここでは主として朝鮮人が多かったと思います。私は女子挺身隊員の中では最年長者であったので、若い女子隊員たちの班長として、彼女たちの面倒を見ることになりました。
☆
八月九日は朝から警戒警報が発せられておりましたが、午前十時半過ぎになって解除になり、私たちは閉じられていたトンネルの入口を開けて新鮮な空気をトンネル内に入れ、同時にトンネルの外に出て一息ついたものでした。私も皆と一緒になって真夏の暑さの中、晴天の空を仰いでおりました。その時、突然にB29爆撃機が二機、上空を飛んでいるのが見えました。それまで長崎には大空襲というものは一度もなく、少数機の空襲が一度あっただけでしたので、皆は余り心配もせずに見ていたのです。それも空襲警報は発せられておらず、警戒警報すら、先ほど解除されたばかりなのでした。突然にB29から夫々落下傘が大きな箱のような物を吊るして落ちてくるのが見えました。空襲の爆弾とも思えないような二つの大きな落下傘を、私たちは戸惑いながらも眺め続けておりました。
☆
その時、トンネル内の私の働いていた事務室から、私の名前を呼び続ける係長の声が聞こえましたので、私は急いでトンネル内に入り、五、六歩ほど歩いた時でした。猛烈な爆発音が背後のトンネルの入口付近で発生、その時、係長の「伏せろ」という声を聞いたような気がいたします。伏せようとした時には、すでに私の体は吹き飛ばされていたようで、その時、私は顔から体全体が地面にめり込むような、というか、地面そのものが爆撃の衝撃でずれて動いて行くような感じでした。気がついた時は顔ごと地面に叩きつけられており、伏せった姿の私でした。伏せの状態から起き上がってみると体には異常はないようで、地面に顔をぶつけた時のかすり傷から血が、あちこちから吹き出ているだけでした。私の伏せった所をよく見ると、山型の鉄板のようなものがあり、私の体はその山型の鉄板にそっくり覆われていたことがわかりました。そしてその鉄板の上には、こわれた机や椅子の破片と一緒に数人の負傷者の、うめきながら横たわる姿がありました。
おそらくトンネルの入口付近にいた人で、外から中へ吹き飛ばされてきた人たちと思われます。私を直撃することなく、すっぽりと私の体を覆った鉄板が何であったのか、こんな奇跡はないと、戦後考え続けてまいりましたが、どうしてこうなったのか、わからないまま今日まできてしまいました。係長が私の名前を呼び続けたことと、この鉄板が私の運命を支えたことになります。
☆
爆弾の爆発は炎の赤い色を連想しますが、その時トンネルの入口付近には火事も見えず、むしろ白さや光線のような感じが強く、火災の恐怖は全くありませんでした。トンネル内では爆風が侵入しただけで、皆恐怖の姿でしたが、入口付近から吹き飛ばされた人以外には負傷者はいないようで、皆ただ沈黙を守って身動きできない状態が、いつまでも続いておりました。
時間の経過はわかりませんが、異様な姿の負傷者が自力で、あるいは助け合いながらトンネルの中に入ってまいりました。その人たちは住吉トンネル工場で働いていた人ではなく、住吉町には大橋工場で勤務する女子生徒挺身隊員の寮があり、非番で寮にいた女子生徒の集団と住吉町の住民の人たちと思われます。街の中の人たちはトンネルの中が一番安全な場所と、ふだんから考えており、またそのように指導を受けていたので、トンネルを目指してたどり着いたものと思われます。私と一緒にトンネルの外の空気を吸いに出たような人は一人もおりませんでした。おそらく即死したものと思います。トンネルに入ってきた女子生徒や街の人はすべて皆、重傷者であり裸の部分の皮膚はむけ、たれ下がり、ガラスの破片があちこちに突き刺さっており、脳味噌が飛び出している子どもの姿もありました。それはいままでに見たことも想像したこともない、手のつけられない状態で、私たちは何をしてよいのかわかりませんでした。
トンネル工場の全体にわたって百人以上の人が入ってきたり、あるいはあきらめて出て行く人もおりました。入ってくる人、出て行く人、人の動きが何時間も続いていたように思います。常時百人以上の重傷者が声もなく、苦しみながらそこここにたむろし、腰をおろしておりました。薬など全くないのと同じなので、その時、誰が言いだしたのかわかりませんが、工場には機械油がたくさんあります。その機械油を体に塗ってやれば痛みや火傷に効果があるのではないか、ということになり、私たちは皆で重傷者の体に機械油を塗る作業に熱中しました。そしてその後、三角布で巻いてやるのです。ぐったりと死の一歩手前まで迫っている重傷者に対して私たちは、ただただ休息の場所を提供することしかできないのです。そして多くの人が私たちが見守る中、次々と息を引き取り、あるいは絶望のあまりトンネルの外に出て行くのでした。
☆
時間の経過についてはわからないままですが、日没が近づいていた頃だと思います。三菱造船所や三菱兵器工場は海軍の管理下にありましたが、川棚や佐世保の海軍基地から救援のためにきたと思われる、海軍の軍服を着た医療隊がトンネル内に入ってきてから、急に治療らしいことが始まりました。私たち女性はにわか看護婦となり、その手伝いを始めました。もちろん、医療隊の人数では人手も薬品も足りません。長崎市より離れた医療施設に、海軍の兵隊さんによって運ばれて行く人を見送りました。
医療隊に続いて海軍の部隊がご飯をバケツに入れたのを大量に持ってきてくださいました。「おにぎり」を作ろうということになりましたが、水がありません。全員が右往左往して何らかの作業をしており、私は水のある井戸の場所を知っているので両手に二つのバケツをさげて一人で初めてトンネルの外に出ました。
☆
長崎の夏の日没時間は七時半頃ですが、もうほとんど夜になっていた頃でした。不思議なことに空襲は火事を連想するものですが、その時どこにも火事は発生しておらず、ただ闇の中でした。行く道々、死体が連続して目に入りました。爆撃より多くの人が亡くなっていることはハッキリわかっているつもりでも、それは驚くべき情景でした。焼死体というより、瞬時に燃え尽きた、焼け尽きた、もちろん、闇の中でハッキリとは分らないのですが、炭状とでも言えるような死体が、うつ伏せ、あお向き、膝まずいた状態、座った状態と様々でした。それまでトンネル内の多くの重傷者や死亡者の姿に接していたからでしょうか、その時私は何か予測していた情景のような気がして、何の恐怖感も起きませんでした。ただ生きている人のための水を早く持って行かねばの思いで道を急ぎました。井戸のある場所に辿り着いて水を汲み上げている頃、やっと海軍の兵隊さんが手伝いにきて下さいました。
☆
女子隊員を集めて「おにぎり」作りに夢中になり、ようやくトンネル内の全員に配り終えると、皆で食事の時間をもつことができ、ホッとして仮眠の時間を過ごすことができたのです。目を醒ましても呆然とした状態は皆、同じであり、記憶の外にあるようなまま夜明けを迎えました。
☆
八月十日の朝、先ずやるべきことは、と係長は私に声をかけ、係長と私の意見は同じでした。先ず女子挺身隊員を帰郷させることにしました。そして係長は私に班長として隊員(記憶では四十二名という数字があります)を引率して長崎駅付近まで行って、帰郷解散するよう命じました。
浦上に向う道路脇の惨状は昨夜私が見たのと同じ状態でした。いえ、昨夜の闇の中で見たのとは、それ以上に明らかに光線で瞬時に焼き尽きた惨状の恐ろしいまでの様相を示したでした。道路の脇に必死に逃れようとしたのでしょう。両側に点々と、あちこちに、大橋から浦上にかけて続いて亡骸が横たわり、ひざまずいているのです。
建物も人間も瞬時に焼け尽きている不思議さ、女子隊員は全員トンネルから外に出るのは昨日以来初めてであり、この悲惨な情景に声もなく足を速めるだけでした。
このあたりには牛舎や牛乳工場があり、牛や馬が裸の体を黒焦げにして横たわっているのが見えました。そして死んだ後に出したのでしょう、長い舌だけが生きているように口から出ているのが、あわれな姿でした。
大橋を過ぎたころ、市電の電車が横倒しになっているのが見えましたが、窓ガラスはなく、車体も鉄製の部分以外はガラガラの状態であり、その下には満員電車であったのでしょう、大勢の人が、原爆の直射された、表現することのできないような無残な姿のまま投げ出され、重なり合った状態で亡くなっておられるのが見られました。
浦上駅近くまで歩いた時でした。突然予告なしにまたもやB29が二機飛んでくるのが見えました。私は叫びました。「みんな線路の向こうの土堤に伏せなさい」。私たちは急いで土提に伏せましたが、そこは昨日の原爆の直射を受けた無残な姿の死者がそこここに横たわっている所なのです。B29が何をするのか、昨日と同じことをするのか、もはや私たちにはそれに対抗する術は一つもないことが、この死者の間に伏せっていることで自明のことでした。何が起きるのか、緊張している私たちのまわりに落ちてきたのは、大量のビラでした。私はその一枚を取り上げました。
「日本良い国、神(紙)の国、十日たったら灰の国」の文字が読めました。この文章は六十年以上経った今日でもはっきり思い出します。多くのすさまじい死者と重傷者を見てきた私たちにとって、その文字は余りにも刺激的、屈辱的な言葉に思えました。こんなビラを投下するB29など墜落してしまえ、私たちは恐怖の中にあったのですが、それは今や怒りへと変わっていったのです。何でこんなに大勢の人が死んでしまったのか、どうして亡くならなければならないのか。そしてトンネル工場で見た重傷者は今、どうなっているのか、これから先どうなって行くのでしょうか。九州各県から来ていた重傷の女子生徒たちはその後どうなって行くのか、自分の人生にこんな悲劇が生じようとは、本人も家族の人も考えられないことでしたでしょう。
そのあと大量の錫片が落ちてきましたが、これはずっと後になって教えられましたが、レーダー防止用の錫片とのことでした。
爆心地のトンネル工場から大橋へ、浦上へと辿り、やっとの思いで長崎駅の近くまで来ることができたのです。これから先、私たちはどうなるのか、あるいは家族は、皆の帰る家は無事なのか、と思いを巡らせたまま、一人一人が絶望感をにじませながら私たちは解散して、お互い別れを告げ合ったのでした。
☆
長崎市は三方が小高い山で一方が長崎港という海になっております。その山の斜面の森林が大きな円形となって黒く焼けているのがあちこちに何箇所もあるのですが、しかし山火事は発生しておりません。これも瞬時に焼き尽くしている状態なのだと思います。「瞬時に焼き尽くす」、これは原爆が落とされた状景を見てきた私の思いなのですが、何故こうなったのか、その説明はその時には私には不可能のように思えました。しかし私が「これは殺人光線だ」と直感したのは間もなくでした。子どもの頃、男の子が読んでいる少年雑誌の戦争小説に、殺人光線を主題にしたものがあるのを男の子から聞いて覚えておりましたが、私はこの原爆こそが殺人光線なのだと、戦後、思っておりました。もちろん、少年雑誌の殺人光線と原爆とは全く異質のものであったのですが、原爆こそが本当の殺人光線と言えると思いました。
私が何故この殺人光線にこだわるかと言いますのは、今日の戦争を知らない世代の政治家、知識人、もちろん一般国民、皆すべて原爆について一般的な知識だけで、その実態がどんなに恐ろしいものであるかについて、文字の上でしか知らないと思うからです。通常の一トン爆弾の百倍、千倍の威力と言っても、その威力は通常の爆弾とは全く違うものであり、私が書いた、焼き尽くす、「瞬時に焼き尽くす殺人光線」というところまでは想像できないと思います。実は体験記文集でも、科学者の知識でも、私の見た実感には触れていないようです。今までの被爆体験文集に書いた人は実際の被爆被害者ですので、自分の被爆体験以外のことにまで目が行かなかったと思いますし、外部の周囲の観察はできなかったのではないでしょうか。トンネルの中で救われた私の見たことは一部でしかないとは言え、書いてみました。
殺人光線が人間を焼き尽くし、燃え尽くされた死者の姿は実体験で見た者にしか、その実態、実展開は理解できないことと思います。政治家、知識人、科学者ですらも現在その実状に合った原爆被害の実態はわからないままのように思います。ですから「日本でも原爆保有のことを考えろ」と言うような暴言を吐く政治家が出てくるのです。
これから先の原爆は私が体験したものよりも、もっとひどい被害、それは世界の終りにつながるような被害をもたらすと思います。このことは体験者として、どうしても日本国民の皆様にお知らせしたいと考えております。
☆
当時は原爆について、私たち長崎の人でも知識は全くなく、放射能とか後遺症のこと、それに「死の灰」の言葉すら全く知らなかったのです。それで私は家に戻った後もトンネル工場の状況が心配で、誰に命令されたのでなく、自分の気持で八月十五日の終戦の日まで毎日、歩いてトンネル工場に通いました。この時、住吉町の女子挺身隊の宿舎に、一番に駆けつけたのですが、二階建ての女子寮は、二階は瞬時の焼失であり、一階部分に女子生徒さんたちの焼死体が並んでいるのが、悲惨と言うか、哀れでなりませんでした。おそらく、一階にいた人は重傷でトンネル工場に逃げのびることができ、二階にいた人たちは光線を浴び一階に落下して死亡したのではないでしょうか。それにしても昨日のトンネル工場に逃げ込んできた重傷の女子生徒さんたちは、どうしているのでしょうか。海軍の兵隊さんによりトラックで運ばれたのは見送りましたが、その後、病院に収容されたことは確かでしょうが、とても助かるとも思えないような容態であり、その情報を知る手段はその時には全く無いままでした。亡くなった生徒さん、重傷の生徒さんのご両親は年齢的に今日生存しておられることは無理とは思いますが、せめて重傷の生徒さんの中、何人かでも恢復され、後遺症をも克服されて生存しておられることを祈るのみでございます。
私は原爆の直射を受けたわけではないとはいえ、幸いなことに後遺症の発症もなく、今日まで生きてこられたことは全く奇跡という気がいたします。そしてその奇跡は爆心地被爆者の中でトンネルの中にいた少数の人だけの奇跡であると言ってよいのであって、今後このような奇跡は二度とないものと、人間は考えなければならないと思います。
私はその奇跡の生存者の一人として、私の知っている限りのことを日本国民の皆さんに少しでも知っていただきたく、今まで文章など書いたことはないのですが、少しずつ書いてみた次第です。
原爆の直射で広島・長崎で亡くなられた方は二十万人以上と言われておりますが、本当のところは当時のことを振り返って考えますと、全くわからないままで、おそらく、その数字以上であることは間違いないと思っております。そして後遺症で亡くなった方は十年以上、二十年以上も続いているし、何十年以内が後遺症の終りなのかは実際にはわからないままなのです。広島・長崎で被爆した方々の多くは、その地にとどまることなく、全国にわたって生活しているのです。果たして後遺症で亡くなられた方の数は全国的に把握できているのでしょうか。終戦後の被爆者に対する政府の対応は何十年経っても、全く何もできなかったのです。私自身ですら、被爆手帳を東京の港区役所から受けたのは約三十年前のことですし、その証明、手続きは私の場合でも、とても大変なことでした。それで全国には被爆の手続きをしていないまま亡くなった人は何十万人もおられると思います。
いったい、この戦争とは何であったのでしょうか。そして終戦の日とは何であったのでしょうか。おそらく何十万人という後遺症の方がおられたと思いますが、その方々には戦争は終っていなかったと思います。
すべての戦争で亡くなられた犠牲者の皆様に誠に遅くなりましたが、心よりお悔やみ申し上げ、ご冥福をお祈り申し上げます。そして、このような戦争が今後、絶対にあってはならないと、心より願いながら、この文を閉じさせていただきます。
