不三不四
松戸市 後藤守雄
中国の四文字成語である。日本語にはない。
中国語辞典には次のような訳になっている。
野卑な・不道徳な・並べ方も品がない。
わけのわからない・ろくでなし。
どこの馬の骨だかわからぬ奴。
まともでない・何ものか得体が知れない。
私はあの夏、ポッタム宣言受託のニュースなど聞かされないまま、湖北省の漢口をあとに京漢線を北上、行軍をつづけていた。
当時鉄道は、制空権を握った米軍にズタズタに切断され、長距離同一列車で走れなかった.夜間走れるだけ無蓋車で運ばれ、降ろされてからは徒歩行軍。夜が明けると部落に待避する生活の繰り返しであった.
つかれ切ってトボトボ歩く我々を見る中国人の顔が、それまでにない嘲笑に変わってゆくのが肌で感じられ、日用品の価格も北に進むほど高くなっていった。
マッチを切らしたのである店に買いに入った。しばらくして出てきた主人--
「日本人! 不三不四!」
そう叫んで、手元にあった日本軍票、たしか拾円札だと思う…まるめてローソクの火種から
札に火をつけ、私の鼻先につきつけてきた。
私はびっくり、買物を忘れて店をとびだした.
二年前の秋、小一月私は湖北省の襄樊(ジョウハン中国読みxian fan)を基点として中国へ四十年ぶりで足を踏み入れた。この街はあの敗戦直前、老河口飛行場奪還作戦の基地となったところで、今でこそ戦争の傷あとは表向き見ることはなかったが、対日本人に良い感情を持っていないことを如実に見せられた。
市の役人は、つとめて大衆との接触をさけ、車で市内を走るときはフル・スピードでつっきり、ゆっくりとは見せないようにしていた.監視?の目をさけて、早朝ホテルをぬけだして付近の市民の生活を見ようと、何回も外出をこころみたが、行き交う、とくに中年の女性からは、顔をこわばらせた冷たい視線がかえってくるので、遠出はできなかった。
帰路武昌に立ちよったとき、黄鶴楼を案内された。行列の割りこみを案内人が交渉してくれた。二、三時間も待たされている一般市民に申し訳ない気持ちが先だったので、私は直立不動の姿勢で最敬礼を整理中の中国兵にした.
と、中国兵はギョロリとにらんで…パーッとツバを足元に吐いた.
「日本人!・不三不四! 」
私は耳をふさぐ思いで列からはなれた.
朝風1号掲載 1988.2月

処刑場に燃ゆる怨霊の火
桑名市 近藤 一
昭和十五年十二月、北支山西省○県に警備駐屯中の独立歩兵大隊に入隊した。
四ケ月間の初年兵教育後半のある日、東南角城壁広場に集合、整列、前方三十米程のところ、立木を背に、後手にくくられ、目かくしをされた三十歳くらい、便衣姿の中国人二人、敵八路軍捕虜か初年兵の刺殺訓練のため、処刑するとか。
初めて生身の人間を刺すのだと思ったとたん、足先より全身にふるえが始まった。
「着剣!」教育助教の大声も耳に入らぬくらい。
最初の初年兵が声にもならぬ声で 「やぁ-」と一声、くくられている中国人の左胸にグサーと、「グェッ」と刺された中国人の口より発した声が我々の耳に飛び込んだ.
「次っ!」助教の大声も聞いたような、聞こえぬような、六番目か七番目か、私が刺した時はもう虫の息、頭をがっくり下げ、厚い便衣の胸元より鮮血がにじみでていた。まるで豆腐をつき刺したような感じてスウーと銃剣が突きささっていった.人を殺すことに何の罪の意識もなく・・・・。
入隊六ケ月後、一人前の歩兵として一等兵になった私は、東門衛兵勤務を命ぜられ、城壁上を動哨する羽目になり、東南角城壁下の処刑場を一日、十数回巡る事になる・上から見れば、今日処刑された生々しい死体、頭髪が半分ほど残っている死体、腐乱した死体、白骨化した死体、その数はどれほどだろうか。うず高く、野ざらしになっている死体の山、夜になれば野犬が十数匹、どこからともなく来て、死体をむしゃぶり漁っている.野犬だと判っていても、がさごそと死体を漁る音は、昼間見るともなく見たあのさまぎまな死体が踊りくるっている音に聞こえ、刺殺訓練のあの中国人二人もその中にいるのだと思うと、私の頭髪は恐ろしさの故に逆立っている感じ。
次の衛兵勤務は雨の日だった.暗闇の動哨は息をつめる。
「がさっ」と大きな音に、見てはいけないと思いつつ、つい目を見張って、「ひぇ-」と声を上げ思わず後ずさり。あの処刑場に、いくつもの青白き燐火が三ツ四ツ、いや二〇ほどが、ちょろちょろ、私の方へ迫ってくるではないか.逃げなくてはと思っても足が動かない。思わず「わぁ-」と大声を上げたつもりが声も出ず、全身がかなしばりにあったみたい。
後手にくくられ、無抵抗のあの中国人を刺殺したその怨霊の青白き火の玉は、四十数年経た今日でも夢の中にでて、あの中一国人の姿が去来する.
合掌
朝風1号掲載 1988.2月

中国慰安婦の身の上
島根県 川本 晃
昭和十八年、済南の工兵部隊に給与を受けてしばらく宿営した。
外出日になると兵は続々と汽車にて済南站に降りる。ライスカレーとビールで腹ごしらえを済ますと一様に殆ど例外なく慰安所に直行する。
相手になった中国女、顔を合わせたときまことに子細あるらしきの印象を受けた。どのように問いただしても彼女は話をそらして語らず、回を重ねること三回にしてようやく次の如きを語った。
私の集落へ突如日本軍が侵入し来たり、兄は捕まり他の十四・五人と共に穴を掘らされ刺殺、埋められた。
我等家族は運よく逃げのびて一ケ月後、戦闘も落ちつき帰ってきた翌日昼、戸口を叩き日本の将校と軍曹が入って来た。姉が外に引き立てられたので父が止めるため、とり縋ったところ将校が父を斬った。なおも引き立てられて大声で叫ぶ姉を軍曹が斬った。
璧に隠れていた母が飛び出そうとするのを私は懸命に引きとめた。
私は復曹を決して日本軍の慰安婦となった。
いまはそのときの日本軍二人の顔もはっきりしない。母はそのとき殺された方がよかったと言いつづける。今では私も生きる望みはない。しかし母を見るとどうにも決心がつかぬ。その母は毎日私の身の回りの面倒をみてくれている、と母を指さした。
四、五ケ月はその女に通ったが遂に体に接することはなかった.四十四年も過ぎた今、それがせめてもの救いでもある。
その女は会報に性病ありと載ったときから姿を見ることはなかった。哀れともおそれとも言い知れぬさびしさがつづいた。
中国各地に、「階級教育碑」と題する碑文に日本天皇制軍隊による「三光」を銘記し、不忘と書かれたものが数多くある。
朝風第1号掲載 1988.2月

孫呉開拓団の八月九日 苦悩への出発
町田市 村西 義孝
その日、国境の地・孫呉の空は雲一つなく染め上げたように青く、何処までも澄んで広野を吹き渡るさわやかな風が麦の穂をゆらしていた。
孫呉訓練所二中隊残留の私達四〇余名は、日課通リ起床して地平線の大地の彼方から真赤に昇る太陽に大きく息を吸い込み、間もなく訪れる秋の収穫の喜びを胸一杯にふくらませて朝餉の食卓を囲んだ。つい先月南満州撫順へ動員されて行った友の噂に花が咲き、今年の西瓜の豊かな実りにあかるい喜びの歓声が満ちた。
窓外のたわわに揺れる燕麦。紺碧の東の空に小さな機影が三機とんぼのようにこちらへ飛んでくる。二、三分もすると私達の訓練所の上空で、突如として爆音高く一機が舞い降り低空で爆弾を投下し上空へ舞い昇った。私達はその爆音の衝動にかられて飛び出した。蕎麦畠に直径十米の深い穴があけられ、柔かい草を食んでいた放牧の馬が二頭のけぞるようにして斃れている。
「練習飛行だろうか…」 「危ないなぁ…」友の声が聞こえる。関東軍の大演習でも始まっているのか…。いま飛び去った飛行機もそのためであるのか。友も私も南の地平線へ飛び去る暗緑色の機影を仰ぎみて手を振った。
突如、地平線の彼方から馬のひずめの音が聞こえ、乗馬の一団が叫ぶように声をからませて土煙りを上げて物凄い勢いで近づいてくる。
日本軍の一団である。電話が入る。ソ連軍と開戦である。私達は寝耳に水のようで動転するような衝動をうけ緊張と興奮は極点に達した。うめきとも、どよめきともつかない声があちこちから同時に上り、私は戦慄のような興奮が突き抜け心が昂ぶった。
伝令が飛ぶ。日本軍を満載したトラックがゴウーという音をたてて国境へ爆走する。あれがソ連の飛行機だったのか・・。敵機とも知らず手を振った自身のうかつさに、生々しい恐怖が私の心をゆすぶった。理解するには余りにも思いがけない大変事である。私は茫然として胸が震えた。青春の血が疾走し昂奮する。
駈走の日本軍が続々と国境愛軍(二字とも王偏が付く)へむけて進撃してゆく。ソ連軍を一挙にせん滅する関東軍の勇戦を期待する。日本軍が守ってくれるという信頼に私達の顔は明るかった。私達は軍用道路に並び、汗まみれで進撃してゆく兵隊にお茶を出し、信じて疑わない日本軍へ心から声援を送った。すぐ、手分して防空壕を掘る作業を始める。
三、四時間もすると、国境の方から風のような早さで数時間前に見送った乗馬の兵隊が引返してくる。唯ならぬ雰囲気である。
「早く引揚げろ・・」 「危ない・・」
「ソ連軍が攻めこんできたッ…」
兵隊の大声が聞こえる。その声は怒号に近いのだ。本気で信じられないまま私も友も呆然と立ちつくした。国境に近い愛軍の陣地が全滅したのである。戦慄が背筋をつきぬける。緊張にひきつった兵隊の顔を見つめて私達は声もなかった。
ソ連軍の進撃が始まった。前の満人部落で狼煙が昇る。一秒を争う事態に追い込まれた。平和な私達の楽園が修羅場に化した。無敵の日本軍。今はそれも空頼みに終った。中隊より四粁先の訓練所の本部へ集合が決まった。厩舎より急ぎ馬を引き出し整列して点呼をとる。二名足りない。瀬法寺、木谷がいない。遥かな野の果てに砂煙りがあがりそれがこちらへ近づいてくる。
「ソ連軍の戦車だ・・」
兵隊はむりにふり絞った声で怒鳴りながら乗馬で馳け去る。事態の急変を聞かされた私連は驚きと恐れを額にきざみ、右に左に足を棒にして声を嗄らして友の名を叫びつづけた。私達は思いのほか切迫した事態をさとった。宿舎の周囲へ満人の暴徒のわめきが潮のように押しよせてきた。時間がない。止むなく私連四〇余名は馬をつらねて本部へ馳けこむ。本部も喧噪を極め物情騒然、異常な混乱である。トラック三台に弾薬を積み込みその上へ味噌、米、塩を山積みし、その上へ病人と看護婦が満載で、エンジンの音を大きく響かせ黒い煙りがもうもうと立ち込めている。他の中隊からも乗馬で四、五〇名集まっている。トラックに乗れない病人もいる。
ヒユーンと弾が飛ぶ。敵が見えたぞ…の一声で廣場のどよめきが吹きとんだ。トラックから米と味噌を捨てる。たちまち暴徒の満人が群り奪い合う。先頭車はあえぐようにゆっくり動きだす。土煙が舞い上がる。先頭の車は又動かない。食糧や衣類の山が崩れ落ちる。弾薬を半分捨てる。やっと動きだした。私達は馬五、六〇頭を連ね、何処からか満人が集り冷たい刺すような眼差しで立ちすくみ私達に石を投げる。馬は吼えるように嘶く。
先頭のトラックがゆっくり動き出した。二台、三台は動かない。積載量が多いのだ。遥か地平線の稜線上視野いっばいの広さ、移しい黒点が等間隔に展開して現われてきた。敵の戦車群である。私達が汗して耕やした大地をソ連の戦車が蹂躪してくる。土煙を上げて無我夢中でトラックのあとを追う。トラックはエンジン全開でフルスピードである。敵の戦車の轟音が唸りをたてて聞こえる。むやみに心が急くだけで私は息を切らせてあえいでいる馬に、早鐘のような自分の心臓の音を聞きながら手が痛くなるほど鞭を打つ。
遥か孫呉の市街の空にも不吉な黒煙が昇っている。後方で爆弾が炸烈する。日本軍がソ連の戦車防止のため橋梁を爆破したのだ。振り向くと私達中隊の宿舎は真赤に炎を上げて燃えていた。後ろの方で次々と爆弾が炸烈する。砂塵で前が見えない。馬の手綱を握り、たてがみにしがみつく。目が痛い。前の馬が折重なるように斃れる。友は崖から転落する。我々のあとに日本兵が四、五名いる。潜伏して敵の戦車を爆破するらしい。転げ落ちた友はそのままだ。疾走するトラックを追う。
孫呉市街までの十五粁は長かった。私も馬も汗と埃で真黒である。駅には放心したような顔の日本人が渦を巻いている。肉親と別れ南満州へ行くのにこの人達は今この駅へ集まったのである。駅前広場は満人が走り兵隊も馳け、異常な喧噪の街と化している。駅舎と前の家が紅蓮の炎を上げてめらめらと火の舌を上げている。病人は半狂乱でわめく。煙と熱風が激しく吹きつけ、列車は荒々しく蒸気を吹きだしている。何も解らない子が声をかぎりに泣いている。長く繋がれた無蓋の貨車に家族と裂かれ、南満州へ避難する同胞の婦女子と病人がこぼれるように乗っている。身動きできない。割り込む病人もいる。右往左往する移しい人の群。狂乱の声をだして、人々がひしめいている。憔悴しきった真青な顔で幼児を抱いて、貨車に乗せてほしいと泣くように絶叫している婦人もいる。すし詰めの状態である。疾風が火の粉を捲いて地上を走る。貨車の周囲は阿鼻叫喚その声は重なり合って獣の咆哮のようで異常な混乱である。お下げ髪の乙女が瞳に涙をため馬上の私達を見上げている。身に迫る危険に追いたてられた人々は次第に数を増す。絶望に沈んだ若い母が蒼白にひきつった額に髪を乱し、両手にトランクを下げ幼な児にリュックを背負わせ、その児の手を引き呆然と立ちつくしている。屈強な男は一人もいない。大勢の満人が憎悪の眼でその人達を囲み口々に何かわめいている。包帯の色が白い。悲鳴と絶叫。南満州の最後の避難列車にひしめく絶望のどん底にたたき落とされた難民の群れである。この列車も何処までゆけるか解らないと言う。私は心の中で神に手を合わせた。
前線基地国境の友軍が総退却と聞いても、まだ私達に軍を頼る気持ちがあり、軍隊の街へ来たという安堵感があって、私達は休む間もなく市街を通り抜け、緑が濃く生い茂った草むらの細路を山の陣地へ馬をつらねた。夕闇が迫ってきた。一米ほどの狭い道を兵隊がぞくぞくと登ってゆく。私達も馬の背で登る。振りむくと、孫呉の駅を出た最後の避難列車は、婦女子と病人をこぼれ落ちそうに満載して、北満州の太平原に黒い煙りを残し弧を描いて地平線の彼方に消え去った。蛇の舌のような炎が市街の中心、薄明りの空にゆらめいている。無蓋の貨車の片隅の失意の母の胸できれぎれに泣いていた赤ん坊の声が脳裡をかすめる。
夕陽の残光はもう消えようとしている。三粁登ると急坂でこれ以上馬で登れない。淡い月光が木々に光を投げ、星が二つ三つ夜空に光っている。友も私も木の枝に馬を繋ぎ捨てた。市街をみおろすと点々と火炎が起き黒い煙が立ち昇っている。夜空を貫いて狼煙があがる。赤紫の数粂の光は不吉に光る。友の両瞳から涙が溢れている。私も沈黙の中で友と同じ思いである。北満の僻地の中隊に残した二人の友は来なかった。
その後、ソ連へ抑留され、兵隊と一緒に第二シベリヤ鉄道の建設、伐採の作業…寒さと飢えに泣き、凍土を拳でたたき、望郷に涙した二年…。
1988.11月 「朝風」4号掲載
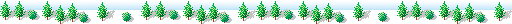
心に残る傷あと
大船渡市 平山 新平
毎年八月十五日が巡って来ると、心のうずきを感ずるのが、あのことである。
それは、終戦の年の昭和二十年八月十五日の昼近く、ところは、東シナ海勃海湾の入口付近と云うことになろうか、私は、日本水産の徴傭船第十一昭南丸(特設馳潜艇)の電信員であった。
過る半月位旅順のドックで修理を行い、昨日大連で、水・燃料を補給した後、今朝、青島に向け出港したのだった。
晴れた海面は真におだやかで、一瞬、戦争を忘れさせるものがあった。
その静けさが破られたのは、十一時十五分頃だったろうか。『配置につけ』の号令で艇後尾の爆雷投下機・投射機に兵員が待機するのを見て、今まで殆んどが対空戦闘だったのに、今回は対潜水艦戦闘だなと知った。
探知された付近に対して何個かの爆雷が投下され、こちらの船体がしゃくり上げられるような衝撃を感じた。
然し、手応えがないのだ。
向うが無事だとすれば、必らず次には魚雷攻撃があるに違いない。ない迄にも相手は浮上して攻撃してくるかも知れないのだ。そうなると貧弱な装備のこちらが叶う筈がない。
この間の二、三十分の緊迫感は今も忘れられない。食うか食われるかなのである。
ところが見張員のけたたましい叫びで、見ると一カ所、水泡が発見されたのだ。
再び、爆雷攻撃が再開された。そして次の瞬間、轟然たる爆発が起ったのである。
『やったァ』期せずして艇内に起る喚声。
やがて、艇内を点検の結果、各所に衝撃による被害個所が発見されたので、艇長の判断で、再び旅順に帰り修理をする必要があるということになった。
潜水艦撃沈、と云う戦果であってみれば、多少の休養を含む再入渠(ドック入)を期待する気持が艇内にあった。
反転した艇は、旅順に向けて航行を開始した。兵員室は、大変な戦果に湧いていた。
ところがである。根拠地隊司令部あての、戦闘報告を発信するため、艇長の命令で暗号化の作業している中に、位置を確むべき海図を見ている中に、現在地周辺の潜水艦情報に、我が方の潜水艦が行勤していることが分ったのである。そう云えば、逆にこの近くまで敵潜水艦が現われた情報は、報告されていないのだ。
もしや?疑惑の雲が拡がって行く。若し、あれが誤って味方艦だったらどうしよう?
艇長も悩んだようだ。兵達の浮々した騒ぎをよそに、艇長室と電信室は心重かった。
然し、事態は更に重大だった。
間もなく飛び込んで釆た『作特緊』電報で未だ曽って経験したことのない『終戦』-。
そのあとは、戦闘報告も発信されず、混乱と不安のまま漂流の如き航海が始まるのだ。
私の心に残る傷あとである。
「朝風」2号 1988.5月 掲載

乳色の壁の病院
沼津市 久田二郎
常徳作戦
昭和十八年の暮れ、中支派遣軍は 「常徳作戦」を発起しました。私が所属したのは第百十六師団(秘匿名「嵐」)隷下の工兵第百十六連隊でした。私は入隊してから一年半はどでしたが、まだ一等兵でした。体力も気力も乏しい、虚弱体質の兵隊でした。分隊のお荷物のような私でしたから、班長は私の扱いに迷惑をしたことでしょう。
意図的になまけたわけでは勿論ありません。仲間のほとんどは、奈良・滋賀・三重の、農漁村の出身者で、体格もすぐれていました。都会生活者であった私には、到底たちうちは出来なかったのです。いま思うと、自分の命を守って、、必死にみんなの後をついて行った、というのが実感です。去年、私はこんな短歌を作りました。「自分だけは死なぬと腹に決めていしかの日必死の我れがいとしき」
さて、常徳作戦が始まると、私達の嵐部隊(約二万名)は作戦の中核となり、戦闘部隊の最前線に配せされたのです。これは日本軍隊の通例で、置かれた立場(序列)が処遇に影響しました。と云うのは、この作戦は第十一軍への下命でしたが、補強の為に第十三軍から嵐部隊が抽出され参加したのでした。ですから我々は、雇い部隊の扱いで、危険な部処へやらされるのです。
常徳の街は「戦史叢書・防衛庁刊」に次のようにあります。
「湖南省の東部に於ける長沙に対して西部に於ける軍事・政治・経済の中心であり、重慶軍の補給 命脈のかかる所、また、我これを占有すれば南東方面に対しては長沙・衡陽の地を、西方に対して は四川省東堺を窺って重慶を脅威する戦略上の要衝である。」
反転、苦しい行軍
七個師団、四十五個大隊を投入して、苦戦の末に攻略した常徳城でしたが、重慶から続々と救援部隊が近付いてきます。戦い疲れた日本軍には新たな戦闘に入る余力はありません。すぐに反転(撤退)の行軍が始まりました。揚子江岸の沙市まで二百粁余の苦しい行軍でした。
在支米空軍の襲撃を避けて、ほとんど夜行軍でした。大部隊の行軍ですので、統制がとれません。だらだらと歩いたり、また時には走るような状態でした。大へんな埃が立っていたのですが、夜のことでそれも分からず、鼻や口に吸い込んでしまいます」 口はカラカラに渇きます.私は、細い棒を拾ってその先に、缶詰の空き缶をくくり付けて、それで道端のクリークの水を飲んだりしました。
発病、必死の行軍
そのうちに、腹が痛くなってきたのです。体じゅうが熱く、熱が出ているようです。そして下痢も始まりました。下痢はだんだん激しくなって、たびたび道を外れて田畑にしゃがみ込みました。見かねた戦友が銃を持ってくれました。下痢便は白く、中に血が混っています。体力は極端に落ちて、もうフラフラの状態でした。
行軍の後尾には重慶軍が迫って来ているようで、小休止も無く、暮れ方から夜明けまで行軍は続くのです。なだれを打つような行軍でした。このような時に、行軍に落伍したら、もうお終いです。端末の一人の兵隊を軍医が診察するなどは、到底望めないことです。
私はもう死にものぐるいになって、必死に歩きました。意識があるのかないのか自分でも分かりません。ただ足を前へ出すだけが精一杯でした。
その時、ようやくのことで部隊は目的地の沙市に着いたのです。私は倒れる寸前であったでしょう。あと半日も行軍が続いていたら、命は絶えていました。そして私は指一本を切り取られて、常徳街道の道端に埋葬されていたと思います。
野戦病院に入院
すぐに沙市野戦病院に入院しました。白いシーツのベッドと日本の看護婦を見た、わずかの記憶がありますが、そのまま意識を失ったのです。昭和十八年十二月三十日のことでした。
正月五日に病院部隊長の検診があり、衛生兵が私の顔を叩いたのです。そこで意識を取り戻しました。私は死の淵から這い上がったのでした。よくもこの生命力があったものと、いま不思議に思います。あとで衛生兵が、「お前は昭和十八年の最後か十九年最初の戦病死になると思った」と云いました。病名は、赤痢と腸チフスでした。
三十人程の病室で、内務班のような配置にベッドが並んでいました。二階でしたが、三階があったか記憶にありません。夜は二本の蝋燭の灯りでした。朝になると鼻の穴が煤で黒くなっていました。衛生兵は関東の部隊で、感染したりして死ねば戦死になるのだと云っていました。一人悪い衛生兵がいて、粗相をする患者を殴るのです。夜間に死者がでると飛んで来て、その私物をまさぐっていました。作戦問に徴発した金品が目当てなのです。
一人の兵隊の死
私の左隣りの兵隊は、病気が悪化して日に日に衰弱しました。ある日の朝、私に「僕の顔おかしいでしょう。もう駄目ですよ」と云います。その日の午後彼は死にました。自覚して死んでいく彼が何とも哀れでした。名前を忘れたのですが、新国劇の俳優だと云っていました。三十位の年齢でしたので夫人がいたかも知れません。遺族が判れば、彼の最後の様子を知らせてやりたいと思ってきましたが、四、五年前「新団劇七十年史」という本から名前だけは判りました。「丸茂三郎」という二枚目俳優でした。新国劇は解散して今は無いので、遺族は判りません。
病院での生活
私は幸いにも快方に向かいました。虚弱体質の私が瀕死の意識不明の状態から蘇生した、この回復カがあったのは不思議なくらいでした。自由に歩けるようになると、リハビリの為でしょうが、使役がありました。郊外の牧場から牛乳を運ぶのです。半分位のドラム缶に牛乳を満タンにして、相棒の患者と担ぐのです。引率の衛生兵が一人付きます。途中で一度小休止、衛生兵はドラム缶に顔を突っ込んで牛乳を呑むのです。我々にも呑ませてくれました。
この病院は街の外れにあって、元キリスト教会でした。外壁は一面乳白色で、そのあたりでは目立つほど綺麗な建物でした。沙市は大きな街で、日本の居留民も居ました。
退院の日のこと
三月の未、私は退院しました。三か月の入院生活でした。その退院の時、病院の門を一歩出たそのときに、胸に思ったことを、不思議に今も覚えています。
それは、そのときから四年程前、東京で観たフランス映画「格子なき牢徹」の中の一シーンのことです。感化院に入れられていた一美少女が、刑期を終えて出所の日が来ます。彼女は歓喜にあふれて感化院の門を飛び出すのです。これを不法脱出とみた巡察の警官が追いかけます。彼女は尚も走ります。ようやく捕まった彼女は、笑いながら出所許可証を見せるのです。ここは名場面と云われました。
このシーンを私は沙市野戦病院退院の日に、その門を出るときに思い出したのです。そのことを、五十何年経った今も覚えているのですから、人間の記憶というものは、時に奇妙な働きをするものと思います。
この綺麗な乳色の建物は、再びキリスト教会となって、沙市のあの場所に現在も有るのではないでしょうか。出来ることなら訪ねてみたいものと思っています。
朝風19号掲載 1997.3月

拉夫(らっぷ)
賀川市 佐藤 貞
野戦で兵隊が毎日持ち運ぶものは、兵器の外に食料品、調味料、医薬品、アゴを出した兵の装具などで各人が持つ量は莫大なものだ。行軍中、小休止の時に腰を下ろすと出発の時には誰かに起こして貰はなくては立てない程の重さである。そこで現地人を強制徴発して物を運ばせることになる。彼等には賃金は勿論生命の保証も与えられていない。これが拉夫(らっぷ)と言われる苦力である。
綺麗な小川があって故郷を思わせる谷底に一つの町が有った。この町を占領するには大分苦戦をしたそうだ。この小川をしばらく遡って行くと小高い所に部落があって我々はここに宿営した。この辺は既に警備地区になっていて戦場ではないから無茶な真似をすると憲兵に捕まるが、通過部隊はその場かぎりなので兎角出鱈目をやる。途中からひっぱって来た牛を殺して皆でたらふく食べて一夜を明かしたが、いざ出発になるとどうも荷物が多過ぎる。牛は食ってしまったので積むわけには行かない。兵は毎日の行軍でアゴを出しているから余計なものは紙一枚だって持てない。ぎりぎりのところまで持っているのだからどうしょうもない。あの頃は10日分位の食料を持っていたと思う。
野戦馴れしているヒゲ軍曹が何処かに出かけて、天秤に野菜を一杯担いだニーコ(中国人)を二人連れて来た。野菜を買ってやるからと騙して町から連れて来たのだそうだ。彼等が喜んでついて来たのが運のつきで、野菜も籠もおまけに自分迄徴発されてしまった。
泣きわめく彼等に有無を言わせず、いろんな荷物を天秤に担がせて出発した。実直な農夫で今日一日仕事をするから明日は帰してくれとヒゲ軍曹に哀願する。軍曹は馴れたもので、「好好、明天回去(よしよし明日帰す)」とか何とか誤魔化してしまう。なんとこれが道県の町に着く迄、十何日も重い荷を運ばされてしまったのだ。
いろいろと彼等の話を聞いてみると、戦争というものがつくづく嫌になる。朝、彼等は家族と別れてからそのまま何処かに行ってしまったのだから家のものはどんなにか心配していることだろう。彼等の名前なんか誰も呼ばず、一様にクリー(苦力)と呼ぶ。夜は逃げられないように部屋に閉じ込め、便所に行くにも銃剣を突きつけて監視する。行軍中は天秤と首を細引で繋いでおく。強行軍について歩けないと殴られる。歳をとっている私ら補充兵は割合苦力をいたわった。それで私らはすぐ苦力と仲良しになってしまった。古参兵は随分と残虐な真似をする。これについては書かないことにする。
兵は夜寝るのに毛布や天幕、雨外套などがあって服装もちゃんとしているので良いが、苦力は野菜売りに出たままの姿だから、寒くてたまらないようだ。不寝番に立って彼等の寝ている所に行ったら、海老のように曲がって、ふたり身体を寄せ合ってガタガタ震えていた。兵隊は皆自分のことに忙しくて苦力のことなんか誰も構ってくれないし、部屋にどじ込められた儘だから藁も菰も集めようが無い。可哀相になって藁を運んで来てやったら二人は非常に喜んで、「先生謝謝」と何べんも繰り返していた。故郷の歳老いた父を思い出した。逃げられないと分かると彼等は中国人特有の諦めからか、「没法子(仕方が無い)」と落ち着いて、兵から可愛がられるに努力する。徒に楯突けば殺されるから止むを得ないことだろう。
彼等のお蔭で中国語が大分分かってきた。古参兵のいない時によく彼等が、いつ帰して呉れるのかとそっと尋ねることがある。「俺には分からないから大人に尋ねろ」と言うと「大人不行、不行(偉い兵は
だめだめ)」と言う。余程古参兵が恐ろしいらしい。
この点で我々補充兵と苦力の共通しているものが有る。補充兵も苦力と何ら変わらない、否応無しにこんな遠い所までひっ張られて来て苛められながら何処に行くのかも知らないで毎日毎日重い荷物を持って行軍している。苦力にこの事を話すと、「あなたも私も同じだなあー」と言って長嘆息する。苦力を逃がしてやるわけにはゆかない。逃がしでもしたらあのヒゲ軍曹にどんな目に会うか分かったものでは無い。
戦友と良く苦力が羨ましいと嘆息したものだ。苦力は悲しくなると大きな声で「アイヨー、アイヨー」と号泣出来るが、兵はじつと歯を食いしばっていなければならない。苦力に「先生不行ナー」と慰められたことがある。同情の言葉のようである。古参兵のしごきに大声を出して泣いて見たいと思ったことが何度あるか分からない。いくさよりも古参兵の方が怖かった。彼等には思いやりが無かった。
この苦力は道県に暫く止まることになって要らなくなったので、僅かの米や塩を貰って帰って行った。物凄い山脈を超えて来たのだから旨くあの町まで帰ってくれれば良いと気づかった。貴重品のマッチを一個与えたらひどく喜んだ。この寒いのにマッチが無かったら途中の山では暖をとることも出来ないだろう。だがこの心尽くしも無駄だったのに後で気づいた。それは喜び勇んで私らに別れを告げたその日の内に別の部隊に捕まって、同じように重い荷物を担いで使役されているのを見た戦友がいたからだ。何とも言えない悲しい気持ちになった。恐らく広東まで連れられて行った事だろう。話しによると、一度日本軍に協力した中国人は中国人同士から裏切り者とされて殺されてしまうそうだ。嘘であって呉れれば良い。
どのみちあの町には満足に帰れなかったことと思う。
朝風27号掲載 2000.5月号

悪運つよく
沼津市 久田 二郎
衡陽という敵の拠点の大きな街を攻撃した。日本の野戦史上で旅順戦と共に最大の野戦と言われる湘桂作戦である。一都市を攻略するのに四十二日もかかっている。
私は無線通信兵であつたので戦闘には直接加わらず、後方の小高い山の通信所にいた。交信の時の他は任務は無い。食糧の支給が途絶えているので、何か食べられる物を探した。大きな沼地に蓮根が生えているのを見つけた。これはシメタと私は泥沼へ入り込んで蓮根を掘ることに熱中していた。その時、突然爆音がして、一機のアメリカ機が現れた。超低空で近付くと、私めがけて機関銃を撃ってきた。恐怖が背筋を走った。私は蓮根の葉の陰に身をひそめ、泥沼に身を横に沈めて首だけ出していた。プスプスと葉に刺さる銃弾の音、生きた心地は無かった。三回も反復しただろうか。飛行機は私を殺したと見てか、やがて去って行った。私は全身泥だらけ。どうやって洗ったか。飛行機には何回もやられたが、一人で狙われたのはこの時だけだった。この作戦の日本軍戦死は大本営発表で四千五百名。私は無線通信兵であったので命拾いした。軍隊のラクな部所を言う言葉に「一に通信、二にラッパ」がある。
湘桂作戦の前年に常徳作戦があつた。冬の戦いで、十ー月三日の暁に戦闘開始。この日は当時の祝日の明治節で軍隊はこんな処にも縁起をかついだ。
この戦闘開始の場所は、いま沼津市と友好都市提携をしている中国湖南省岳陽市の町外れであつた。
この作戦が日本軍の勝利に終わった時、敵の捕虜が三千人いた。私達の小隊がこの捕虜の監視の役についた。常徳の街は高い城壁に囲まれていて、その一角に捕虜を集めた。私たち兵隊は二人一組になつて捕虜の中を巡視した。私の相棒は同年兵の庄司賢一で、彼は私より七歳年長であり妻と二人の子供があつた。
ある日の昼どき、私は空腹をおぼえなかったので、庄司を先に食事にやり、彼が戻ってから私は城外へ出た。外壁の隅で焚火に当りながら私は飯盆の飯を食べていた。その時、爆音がして、かなり高い空に敵の飛行機が三機見えた。通過するものと思って見ていると、何か黒い小さな物が落ちてくる。爆弾だ!私は地に伏せた。瞬間物凄い爆発音がして、城内から黒い煙が立ち昇るのが見える。捕虜たちの騒ぐ声が聞こえる。これは一大事と、私は捕虜たちの所へ走った。来て見ると、捕虜たちの真ん中に大きな穴が出来ていて、その回りに三十人ほどの捕虜が倒れている。庄司は?と見ると、四肢ばらばらになって無惨に倒れている捕虜たちの中に彼も倒れている。
庄司は、額から上と片足の靴の半分を殺ぐように失つていた。即死である。砂塵を被った顔は化粧したように美しく見えた。昼食を私が先に食べていたら爆弾は確実に私の上に落ちたのだ。庄司は、私の身代わりになって死んだのである。
彼については、夫人の早百合さんにまつわる戦後の後日談があるのだが、次の機会に書きたい。
その常徳作戦が日本軍の勝利で終わった時、蒋介石の重慶軍が救援にやって来ることが判かった。日本軍には、これ以上戦う余力は無い。そこで急いで撤退することになった。昼間は飛行機に狙われるので、主に夜間の行軍が始まった。目的地は揚子江沿岸の占領地域、沙市である。約三首粁ある。
敵の救援軍の追撃と執拗な敵の飛行機に追われて雪崩を打つような行軍だった。冬の暗闇の道を、各隊が入り乱れて走るように歩いた。自分の部隊をはぐれたら、食料も何も切り捨てられる。敵地の中だから、行軍から落伍したら命はない。私はカを振り絞って必死に歩いた。しきりに口が渇くので、道端のクリークの水を飲んだ。
三日三晩も歩いただろうか。そのうちに、私は腹が痛くなってきた.下痢もしている、たびたび道端にしやがみ込んだ、行軍中の生理現象は、小のときは一町、大は八町先へ走って横へそれて用を足す。済むと丁度元の位置に戻れる。これを「小便一町、クソ八町」と言った。(ひどい話で恐縮)
私の下痢は益々激しくなる。白い便に血が混じっている。明らかに異常だが止どまることは出来ない。私は必死に歩いた。目はくらみ、ただ足を前へ出すだけ。疲労困感、どうにでもなれ、と思っていただろう。その時、我々の部隊は友軍陣地の沙市に到着したのである。あと半日も行軍が続いていたら、私は指一本を切り取られて、常徳街道の道端に埋葬されていたと思う。行軍中の兵隊が、どんな重病であつても、軍医の診察を受けるなどは望めることではなかった。戦時の兵隊の命は軽かったのである。
すぐに沙市野戦病院に入院した。病室に入って、白いシーツのベッドと、日本の看護婦を見た。そこで気が緩んだのか、記憶はそこ迄である。
その日は昭和十八年十二月三十日、私は昏睡を続けて、気が付いたのは一月五日、病院部隊長の回診があり、看護婦が私の顔を叩いたのである。よくも回復する体力があったものと思う。病名は赤痢に腸チフスの併発であった。クリークの水を飲んだりしたからだろう。
私は順調に回復した。私の右隣のベッドに、新国劇の俳優だった兵隊がいた。東京の話など交わしたが、彼は日毎に衰弱した。その日の朝、彼は「久田さん、僕の顔おかしいでしょう。もう駄目ですよ」と言った。午後、彼は死んだ。自覚して死んでゆく彼が哀れであった。私より四つ五つ年長だったから妻や子がいるのかも知れない。彼の最期の様子は私より知る者はいない。妻なる人がいるのなら知らせてやりたいと思った。
二年はど前、私は思い立って、彼の所属した新国劇(今は解散)の代表格の島田正吾へ電話した。九十才を出ている島田は、今も一人芝居で活躍している。電話にお手伝いさんのような婦人が出た。劇団の人で中国で戦死した人はいませんか、と聞いた。婦人が島田に聞く声が聞こえた。面倒くさそうな、しわがれた声が聞こえたが、話は進まなかった。午睡の時間でもあるのか。支那で一人戦死している。名前は丸茂三郎、二枚目の役者だった。聞き取ったのはそこ迄である。
この沙市野戦病院は元キリスト教会の建物で三階建て、乳白色の奇麗な鉄筋の建物であった。現存しているだろう。私の病室は二階で、五十畳ほどの広さ。真ん中に頭を寄せて二列にベッドが並んだ。電気は無く、夜は太目のローソクが二本灯った。朝になると鼻の穴が黒く煤けていた。
この病院は東京の衛生隊で、一人悪い衛生兵がいた。粗相をした患者を殴るのである。また夜間に患者が死ぬと、この衛生兵が飛んで来て処置をした。目当ては死んだ兵隊の所持品なのだ。兵隊は作戦間に手に入れた私物を持っている。貨幣や金銀の細工物などである。衛生兵はそれを探し出して懐へ入れていた。ローソクの淡い光の中で、私はこの様子を盗み見ていた。
朝風30号掲載 2000.8月

首切り
匿名
「初年兵‥徒手帯剣で集合」の号令で、慌てて集合し、その場で服装をなおした。○○軍曹が兵舎から出てきて、我々の敬礼に軽く会釈し、服装を一瞥した後、「馳足」の号令共に、先頭に立って走り出した。城内の南門の傍で馳足をやめ、空き地に引率された。
そこには十二名の支那服を着用した。農民と見られる者が、後手に縛られて座っていた。その各自の前には二米にも及ぶ穴が掘られていた。その穴は彼ら自らに掘らされた穴だった。ここまでくると、どんなことが行われようとしているのか、理解できた。憲兵軍曹が出て来て、やおら刀を抜いた。我々初年兵の他に、かなり多くの見物人があり、将校の姿もあつた。
映画のシーンの一片のように、おもむろに憲兵は刀に水をかけ、農民の後に立ち、何やら中国人に言った。「不用の返事と共に、彼の刀が一閃、農民の首は体を離れ穴に落ち、首から鮮血が迸った。憲兵は素早く足で胴体を穴に蹴おとした。次の者は、終始それを見ていたが、覚悟をきめていたのか、諦めたのか、一言も発せず同じ動作で穴に落ちた。
四、五人切った後、「誰か切りたい者は」の声に、見習士官が応じた。彼は自分の刀を抜いたが、多分、家伝の宝刀だったようだ。憲兵のように水をかけ、最上段に構えたまでは、芝居の花道を思わせたが、気合もろとも打ちおろした刀は、農民の肩から首にかけて切りおろされ、鮮血が流れたが農民はそのままで何か大声で喚いている。二度、三度きりさげ、ようやく穴に押し込んだが、伝家の宝刀も使い手によっては切れないようだった。憲兵は、まるで大根でも切るよぅに、手捌きよく残る者を片づけたが、彼にすれば衆人環視の中、得意満面だろうが、切られた農民はどうなのだろう。
帰る私達は、あの場面がちらつき、言葉もなかった。ニ、三日は、飯も喉を通らなかった。後で、あの農民姿の者は、スパイであると言われた。もし、中国軍が日本に侵攻したと仮定した場合、日本軍に不利な情況を中国軍に提供するだろうか。農民たちが「私は知らない。或は反対方向に行った。の情報をもらした。」即それは、スパイの名のもと、首を撥ねられる原因と知った。
この無法な行為は、中国に進行した部隊では、日常茶飯事であり、仮に、中隊に初年兵が入隊する度胸だめしとして刺殺させた事を考えると、この犠牲者のみで、一万人以上の虐殺があつたことになる。それにしても、彼ら農民は泣き喚きもせず、平然としていた姿が目に浮ぶ。
教科書を改訂、侵略でなく聖戦説を称える輩、国歌国旗を強要しはじめた最近日本の進路に不安を感ぜずにはいられない。
これでよいのか日本。もう一度考えてみる必要はないのか。
会員の投稿を拝見しております。色々と、ご苦労なさった情景が目に浮びます。本当にご苦労様でした。しかし、その苦労、もしかしたら、命と引き換えになったかもしれない。その貴重な体験を後世に語り継ぐ、大変意義あることと思います。だが、その体験をさせられた原因は何処にあつたのでしょう。また、誰が、何のために戦争に訴えたのでしょう。その根本を掘り下げた投稿が少ないように思われますし、是非、うけ賜わりたく思っております。
朝風38号掲載 2001.4~5月

慰問袋
金沢市 福岡 重勝
昭和十六年後半から十七年にかけて中国河北省唐山地区の駐屯地に於いての思い出である。
私は当時中隊の陣営具係助手を命ぜられN曹長の下でその任務についていた。陣営具とは駐屯地内の備品即ち机、腰掛、食器などの什器のほか携帯口糧(堅パン、牛缶などの非常食)又蚊取線香、殺虫剤、洋燈の油などの消耗品の総称であり、これらの管理、保守、整備の係である。故に演習に出ることもなく、衛兵やその他の勤務も免れて至極安泰ムードの軍隊生活を過ごしていた。こんな時我が中隊に内地から慰問袋が送られてきた。これも私の受け持ちである。隊長以下全員に支給されるのだが、大小、軽重いろいろでありこれを無造作にそして公平に配給するのである。
兵隊達にとつて慰問袋は大変有難く嬉しいものであり、誰もが歓喜雀躍して開封したものだ。中身はちり紙、ライオン歯磨き、便箋、石鹸、仁丹、遠足の友(ふりかけ)常備薬など日用品が多く、これらは何れも隊から支給があり不自由を感じない物品だが、内地からの真心こもった心暖かい贈り物だと思うと有り難さをひしひしと感ずる。そのほか安全カミソリセット(当時は貴重品)乾操バナナ、キャラメル、申又(サルマタ)ゴールデンバット(金鶉)、ハート美人(衛生具)など当たり外れもあり苦笑する始末である。特に嬉しいのは同封されている手紙だろう。文面は「兵隊さん、ありがとう・・・」に始まるお決まりの内容であるが、たどたどしい幼な児のものもあれば、古風な文面のお年寄りの便りもある。女子学生のものは喜ばれてこれが縁で文通を続けた者もいたようだが、後で悲喜劇も聞いた。
私は慰問袋の係として員数外のもの数個を自由に開封できる恩典(役得)もあり満足であつた。
又家族からの慰問袋もあった。私宛てのものの中に日用品に混ざつて郷土の新聞が入っていることがあり、大いに興味があつた。「東京日日新開」或いは「新愛知」である。日付の大分過ぎた新聞であるが懐かしかった。一面の戦闘状況棚には「我が皇軍00部隊は○月○日、中支の要衝00に進出して敵の大部隊と遭遇し激しい戦闘を交えた末、敵は多くの遺棄死体を残して退散した。我が方の損害軽微なり」とは大本営発表の何だか訳の分らない00づくしの迷文面であつた。
芸能欄には映画「白蘭の歌」長谷川一夫、李香蘭主演「五人の斥候兵」小杉勇、伊沢一郎出演など。流行歌欄には「梅と兵隊」田端義夫、「南の花嫁さん」高峰三枝子、「加藤隼戦闘隊」灰田勝彦、「蘇州夜曲」渡辺はま子などの懐かしい記事が掲載されていた。
この慰問袋も昭和十八年にはみられなくなった。内地も物資不足時代が到来して食料品や衣料は配給、切符制度となり、輸送手段もなくなり寂しい限りであつたが、郷土の皆さんの窮乏を思うと贅沢は言えなかった。
以上は今でも時折思い出す懐かしい想い出である。
朝風34号掲載 2000.12月

軍馬たちの末路
福鳥県 佐藤 貞
中国の野戦で軍馬の最後を何度か見た。脚を折ったのか泥濘のなかに遺棄された軍馬の脇を行軍したことがある。雨のなか頸だけを高くかかげて隊列について行こうともがいていた。倒れた軍馬は蹄鉄を外され手綱を切られて遺棄されるとか。恐らく安楽死させるに忍びなくて後続する部隊にそれを委ねて遺棄したのかも知れない。
また、私の馬は一晩うなつて病死した。横たわる馬の口には、どうしてもうまく末期の水を飲ませることが出来なかつた。何か良い方法が無かつたのかと今でも悔やまれる。
しかし本当の軍馬の受難は敗戦に始まった。それ迄は生きている兵器と言うことで大事に扱われていた。敗戦になつても何故か軍馬の引き渡しは行なわれず、寒くなつても広場に繋がれた儘だつた。餌不足で痩せこけ、氷雨の降る時などガタガタ震えて立つているのがやっとで、骨で尖った尻が十センチぐらい左右に震えていた。二合ほど入れたカラスムギのエサ箱を棒で押しやって与えた。エサを持って近づくと飢えた馬は狂ったように暴れて抱き込まれてしまうからだ。その僅かなエサも掻き寄せる前脚にひっくり返されて土に散り、口に入るのは幾らも無くなるがどうしようも無かつた。
嵐の晩に二頭盗まれたことが有った。足跡を辿ったら中国人部落の石畳で消えていた。飢えないですむだろうとむしろ安堵して帰って来た。夜中に密殺して食用にしたこともある。骨は土間に埋めた。固い肉を皆で黙々と噛んだ。冬近くになつて、やっと中国軍に接収された。
使役に出た戦友から、中国の将校を乗せて元気に歩いている馬を見た、と聞かされて涙が止まらなかつた。これで良かつたのだと皆と話し合った。私たちは何とか帰る事が出来たが、軍馬で祖国の土を踏んだのが一頭でもいるだろうか。私の地方は馬の産地だったので、軍馬の慰霊碑をよく見かける。その前に立つと、しばし合掌して哀れな軍馬たちに思いを馳せ瞑目する。
(この文は朝日ソノラマ、戦争、上巻に掲載されたものです。)
朝風33号掲載 2000.11月

上官にしごかれて自殺した兵達
福島県 佐藤 貞
私は戦地で自殺した兵のことや、苛められた兵のことが余り語られないと思っています。皆脛に瑕を持っているからでしょうか。
恨みをのんで自殺した兵士が沢山いる筈です。私が招集された昭和十九年から敗戦までの僅か一年半位の中国戦地で二人の自殺兵を確認しています。話に聞いたのは沢山有りますが確認は出来ません。未遂者は一人確認出来ます。
復員後、一人の自殺兵宅に行って線香を上げました。病死の通知になつていました。この兵は同じ補充兵仲間でした。本隊への追及中の出来事で、私は余所の班に使役に出ていて留守でした。自殺した仲間は池の脇で手榴弾で胸半分を扶りとられて死んでいたそうです。彼の馬が穴に落ちて引き上げるのに物凄い苦労をしたので、怒った班長は穴の脇に馬を繋いだ彼を酷くしごいたそうです。小柄だが本職の馬方で輜重車を曳かせるのが凄く上手でした。泥濘の悪路を一気に駆け上がっていた彼も、余りのしごきに死を選びました。
もう一人は余所の隊の兵で、私は火葬の使役に出て大きな木の下で焼きました。彼は将校当番で、何か不都合な事でこの将校に酷くしごかれたようです。この若い将校は泣きながら「そんなに死ぬほど辛かつたと思わなかった」と詫びていました。この将校と私ら使役の兵だけの寂しい茶毘でした。
自殺兵の恨みは誰も知らないのです。自殺と知ったら親兄弟はどんな思いをするでしょうか。理不尽な制裁に我慢出来無くなつた兵は自殺を選ぶのです。逃亡する兵もいましたが、私の隊には幸いいませんでした。
よその隊に派遣されたとき、朝の点呼で逃亡兵何名と言う報告を聞いたことがあります。さすが自殺兵何名と言う報告は聞きませんでした。病死か何かにして報告したのでしょう。誰にも訴えることが出来ない苛めなのです。同僚も見ていてどうしようも無いのです。止める者が誰もいないのです。
あの当時兵を苛めた所謂上官は今どんな家庭を持っているのでしょうか。きっと良い親やお爺さんになっていることでしょう。戦争とはそう言うものなのでしょう。彼らの懺悔を聞いてみたいものです。
朝風39号掲載 2001.6月

私の従軍記録
酒田市 友野 九郎
前号による私達が敵前撤退したことにより、敵は一挙に攻撃を強めて来たので、私も新たに兵器を支給され別方面の敵に再攻撃を開始したが、その時に普中作戦に出動中の連隊主力が、急遽救援の為に帰還し敵の背後を攻めたので、敵は一挙に崩壊して撤退されたのは幸いであつた。
私ら前線の兵隊稼業は呼吸つく暇もない程忙しい。戦闘から帰ってやれやれと思っていたら又も出動準備するよう命令があつた。第一次普中作戦が八路軍の執拗な隠密行動戦法に振り回されて、何の成果も得なかったその腹いせに、それに対する復讐が目的の第二次普中作戦が出動となつた。
即ち私達を救援に帰った我が連隊が又引き返すことになった。敵側ではこの戦闘を百団大戦と称して大成功と報じている。我が中隊も再び出動することになり、私は第一小隊第一隊に編成され初めて本格的な作戦の出動であつた。第一次作戦での失敗は八路軍(共産軍)が住民と密通して日本軍の行動を流してる為と判断し、周辺の住民と家屋を総べて抹殺する戦法であった。この恐るべき凶悪なやけくそ戦法には唯々驚くばかりで、人道上許しがたい大罪であつたが、私もやはり傲慢な日本軍の一人で、皆で渡れば恐くない気持ちであつた。
私達の中隊は某騎兵連隊長の指揮下となり、山西省中央部全体に点在する八路軍が隠密行動している地帯での追撃作戦であった。何時もながら我が部隊の裏を行く巧妙な敵は、約一ケ月間の作戦中で一度もその姿を現さないのは、住民からの情報によることは明々白々であつたことから、地域の住民とその家を一斉に消滅戦法となった。先ず最初の目標は最も敵に密通しているらしい大集落へ行った処、住民達が大勢集落の入口にて湯茶の歓待で迎えてくれた。
(何時の作戦でも住民は総てが逃避して姿を見せたことがないのでこれは大変珍しい光景であつた)
部隊はその歓待に答える如くその集落に入場して停止するや、支隊長は各中隊の命令受領者集合が伝達された。さては大休止かと安堵していた所に、中隊の命令受領者の某伍長が顔色を変えながら中隊長への伝達は、「この集落が八路軍の密通している拠点なので、この住民を皆殺ししてから総ての家を焼き払う」という厳命であった。この悪魔のような突然の命令には如何に傲慢な日本軍兵士でもこれには呆然となつてしまった。
この異常な命令には私達はやはり人間として良心の呵責により、部隊全体が唖然なり躊躇してた処へ某支隊長が駆け付けて、「何をくよくよしている、これは軍の命令だから早くやれ」と物凄い剣幕で叱咤されたが、あの殺気に満ちた勇ましい支隊長の馬上姿が今も鮮明に浮んでくる。
この命令に従い部隊が一斉に行動するや、この集落は忽ち阿鼻叫喚そのもので、住民の泣き叫ぶ声、それに逃げる者等々、あの地獄の如き状態は、現在も頭の奥にこびりついて離れない。さて私達の分隊も嫌々ながらも実行しなければならないけれど、狭い集落内で日本兵と住民が入り乱れた大混乱では、とても行動し得ない状態だったので、他部隊の行動を呆然と眺めていたが、分隊長は直ぐ隣に在った茅屋を焼き払うよう指示された。
しかしその家内には足の悪い老夫婦が居住していたが、これをどうするか分隊長と古兵達と思案した結論は引き出して射殺するのが面倒だから、在宅そのままで四方から放火して、老夫婦諸共焼き殺す残酷な方法であった。この鬼の如き非道な仕打ではあるが、殺気に溢れている時点では冷静な判断はとても不可能で、どんな悪でも皆でやれば恐くない集団心理が作用し、無意識のうちに古兵達と行動を供にした自分を恥じている。あの地獄絵の如き状態でも相当数の住民が難を避けて逃げる状態が見えたが、その住民達があの残酷非道な日本兵の仕打ちに対しての憎しみ、それに地獄絵そのものの状態を、終生どころか末代まで語り継ぐことであろう。今もって良心の呵責に心を暗くしている私の余生でる。このように約一ケ月間に亘る作戦中は、住民が逃避した集落を次々と焼き払いばかりの作戦であつた。
山西省一帯は草木が生えない赤土地帯なので、住宅に必要な木材をどのように求めたろうか。その日の生活に支障している状態の中では、恐らく何代も何代も若労に苦労を重ねて出来た住家であろうと思うと、人道上許し難い大罪を犯したことになる。以上のような凶悪な行為は決して我が部隊だけではなく在支駐留の日本軍全体の体質で、その罪は万死に値する大罪であつた。
約一ケ月間の作戦が終了したその足で、大きく方向転換して次は北支の正規軍相手の作戦であつた。そのように敵に欺かれながら風呂もなく蚤と虱と南京虫と同居しながら東奔西走約三ケ月間作戦が終了したのは十二月の末であった。落ち着いた所は険しい山懐ろに在る集落で、炊事をするにも深い谷間まで下り、支那人を雇って天秤棒にて担き上げる状態では、とても私ら初年兵が風呂などは夢の夢であつた。このようにして昭和十六年の新年を迎えた所に、内地から現役の初年兵が派遣されてきた。ところが私のような軍隊嫌いな者が初年兵教育の助手を指名され、その教育中は作戦や討伐には出動免除とは幸運であった。
朝風45号掲載 2001.12月
