病院船有馬山丸
熊本県 川口 静雄
やっとの思いで生きのびた。 昭和二十年末、昼食後身の回りの物を持ってテントの前に集合した。ここはマニラの南方カルンバンにある日本人捕虜収容所である。
何事が始まるのか、俺には丸きり判らない。見ると十字を付けた箱型ジープが待っている。六人ずつ乗り込んだ。小さな窓が三方にあるだけ。何台有るかも判らない。これからどこへ連れて行かれるやら不安になる。
動き出して途中町中で何回も止まると、現地人が車を囲んでは大声でどなる。石を投げつける。
「ジャパニズハタイ、ハタイ」 (日本人死ね、死ね)
と、感情をむき出してくる。車の運転台の米兵が時々大声で叫んでいるが収まらない。やっと車が発車したので安心した。しかし、これからどこへ連れて行かれるやら不安は益々つのる。
キャンプを出て二時間位、何となく湖の匂いがしてきた。波止場のようだ。皆もぼちぼち話し出した。マニラ港だ。相変わらず現地人の感情は悪い。何も俺たちが悪いのじゃない、軍が悪いのだ。何のためにこの地に来たのだろうか。時の権力にたてつく者はなく、どこかで死ぬ覚悟で国を出てより一年半余り。思えは短い期間ながら長い苦しい悲惨な日々が続いた。
車が止まりドアが開いた。
「さあ皆さん、ご苦労様でした。私達はあなた方を内地から迎えにきました。安心して車から降りてて下さい。」
と、日本語である。今までの不安な気持ちが急になくなり次第に喜びに変わった。
車から降りてみると、黒い船体に赤十字のマークの付いた病院船・有馬山丸が横付けしている。
「有難うございます。内地へ帰られるのですね.」
「そうですよ。」
これまで生きていて良かった。これで日本へ帰れる。家はどうして、父母はどんな思いだろう。次々といろいろの事を考えたら、とたんに体からいっペんに力が抜け、タラップの下にくずおれてしまった。やっとの思いで船内に入った。ここまで来る時はすし詰めだった船内も今は広々として青畳が敷いてある。皆なつかしげに手でなでている。
いつしか船は出港しているようだ。誰いうとなく甲板に出てみた。潮風が、はだにここちよく当る。波打ち際の椰子林が続く。遠く見える山々、その谷間を流れる河原には、幾千人の同胞が雨に打たれ、供養してもやれずにいるのかと思うと何ともやりきれない思いだ。
生きて再び帰れるとは思ってもみなかった。運命のなせるわぎ、再び訪れることもあるまいこのルソン島に多くの兵士たちが眠っているのだ。夕日を背に受け、去りゆく島影に別れを告げるかのように、いつまでも見いっていた。
五日後、我々は浦質に下船し東京第四陸軍病院へ入院した。
戦後四十二年、若かりし青春を大きく狂わした戦争。未だにフィリピンの山野に眠る同胞のご冥福を祈るのみです。
今日迄生きて来られたのも何かの「お加護」だと心に決めている。
朝風1号掲載 1988.2月

戦艦霧島、南海に消ゆ
東京都 山田 太吉
後甲板水線下、十数米の左舷発電機室が私の戦闘配置であつた。軽やかな「タービン発電機」の回転音のみが聴こえていた。約四万屯の快速戦艦霧島の主砲三十六糎砲八門からの射撃音と艦の振動が微かにこの機械室にも響いていたが、やがて静まり返り時が流れた。戦況を時々伝えていた艦内高声令達器も途絶えていた。
艦底の戦闘持場でその任務を果たしていた私と部下三人は、つい先程まで米艦隊と砲戦を交えていた戦況に不安感を覚えてきた。私は数米の「モンキータラップ」をよじ登って中甲板へ状況偵察に上がって見ると誰l人見かけない。前方艦首に通ずる隔壁扉を開こうとしたが、艦の防火防水を任務とする運用科の兵員が、かねて備えの角材柱で開閉が出来ない処置をしているようだつた。
これはただごとならじと引き返し、部下三人と共に後甲板上部へ脱出しようと試みたが、すべての「ハッチ」は開閉不能である。やむなく、後部士官私室の舷窓鉄扉丸窓を開いて、漸く身体をくねらせて抜け出し、上部へ脱出することが出来た。後甲板はと見れば惨憺たる交戦のあと歴然。至近の夜間砲撃戦のため、主砲は仰角零の水平射撃のため甲板上は敵弾命中の通過した溝の跡さえあつた。そんな中で必死の救助作業が展開していた。
我々は昭和十七年十一月十四日、ガダルカナル島の敵飛行場を砲撃する任務を与えられ、霧島は随伴の巡洋艦、駆逐艦数隻と共に昼間の敵機来攻を避けての夜間強襲であつた。待ち伏せていたとも思われる米艦隊と狭水道でも、予期せぬ彼我入り乱れての夜戦であつた。或る艦は敵艦と二〇〇米近く接近、辛うじて衝突を回避するほどの舷々相摩す戦いであった。巡洋艦と思われた敵は、図らずも四十糎砲搭載の新造戦艦サウスダコタと新鋭の戦艦ワシントンであつた。
夜戦を得意とする味方駆逐艦の、縦横無尽の見事なる魚雷攻撃戦など、二度と再び起こることも思われぬ戦い、海軍に身を投じて、初めて乗り組んだ霧島も、夜来の戦闘で艦上戦死八十有余名、沈没に際し艦と運命を共にした戦友百十余名、全乗組員約千五百名中二百十余名の尊い命が失われた。
霧島の主砲で傷ついた敵サウスダコタは、その後、味方駆逐艦の魚雷で撃沈。ワシントンは追撃を逃れ長蛇を逸した。一方、霧島も舵取装置破損に加え、敵新鋭戦艦二隻の至近戦で四〇糎弾を約十発、二〇糎弾約四十発を被弾し、上甲板の戦闘機能は失したが、主軸機械と罐室は損傷も浅く運行可能だった。しかし、如何にせん舵破損とその予備たる人力舵取室も浸水し使用不能のため、も早やこれまでと、艦長は自沈用の「キングストン弁」の開放を命じた。
これより先、総員退艦の命令が出て前部上甲板に集合、軍艦旗を万歳三唱裡に降下した。艦は左舷に急傾斜、救助駆逐艦の横付け作業もままならない。上甲板に立つこともできず、私は移乗の暇もなく急傾斜する右舷の艦隊をすべるが如く暗夜の海へ投げ出された。巨艦沈没の際、その渦流に巻き込まれることを警戒、必死で二百米位を泳ぎ遠ざかつた。艦底を上部にその赤腹を露呈した霧島は、火薬庫爆発による二度に及ぶ大爆音と共にサボ島の海底深く栄光の勇姿を没した。時に昭和十七年十一月十五日の〇一二五だつた。私は、その時、千人針を腹に巻き褌一つ軽装で泳いでいた。その周辺を浮遊していた戦友は期せずして「霧島万歳」の声にどよめいた。
約二時間くらい暗夜のソロモン海を漂流、幸い味方駆逐艦を望見、泳いで艦へ引き揚げられ救助された。敵弾による破片で足部に戦傷出血の信号兵かと思われた若者は、人間の生への執念とも思える力泳で、私と前後して救助されたが、「あ-助かったのだ」という安堵感から程なく甲板上で絶命した。
あの海戦より光陰流れて五十五年の歳月がたつ。
ソロモンの海でも肌身離さなかった千人針は重油に黒ずんだまま、今でも我が家の箪笥の中に眠っている。
朝風29号掲載 2000.7月

戦時回想
市川市 三神 銅太郎
ビアク派遣隊
人生には忘れられない出会いが有り、忘れる事の出来ない思い出も有る。私にはあの前線での出来事が強烈な思い出としてその一つ一つが今も鮮明にマブタの裏に焼きついて居る。それは戦局とみに悪化した昭和二十年に入った何月頃か今記憶が定かで無いが、アンボン島の我が隊から戦雲垂れこめる西部ニュウギニヤのピアク島の飛行場へ派遣隊を募った。戦友と別れたく無いのは誰の心も同じだ。そこで各班から二名ずづ指名する事にし班員を集めた。
皆しばし顔を伏せ沈黙した。その時二十才そこそこの若い志願兵上がりの兵長ともう一人の兵が私が参りますと申し出た。残り十三名の兵が安堵の表情を浮かべたのは申す迄も無い。そして準士官の隊長とも四十七名の派遣隊が編成され、忠臣蔵の四十七士だと戦友達が勇気づけてこれが最後の別れに成ろうとは知るよしも無く漁船での戦友達の無事で着く事を帽子を振り乍ら励まし見送った。
あれから一ケ月もたったろうか。そのころ私は戦闘指揮所に情報員として勤務して居た。ある日の朝、ビアク島派遣隊から緊急電が入った。『戦艦ヲ含ム有力ナ敵艦隊本島沖二遊弋チユウ』の短い電文であった。我々は戦友の安否を気遣った。当直将校から電報はまだか、まだ電報は無いかと本部の士官達は元より、兵達も非常に心配したが音信なくその日も暮れた。翌朝待ちに待った派遣隊からの電文が届いた。
『昨終日艦砲射撃ヲ受クモワレニ人的被害ナシ、敵ジョウリクノ公算大ナリ、ワレ戦闘ハイビ完了』以上の報であつた。
戦闘配備完了と甚だ勇ましい報告で有るが、我々航空隊はいわば非戦闘員で有り、派遣隊には破損した飛行機から取りはずした七・七ミリの機関銃が一丁と全員に足らない小銃が有るのみだ。しかし戦友の身を案じつつも、あの島には砲などを有する(雪)部隊の呼称をもつ強力な弘前歩兵部隊を主力に海軍陸戦隊その他など相当数の戦闘員が居ると聞いて居るので最悪の局面まで考えて居なかった。
その後なんの連絡も無いのに隊幹部はもちろん、我々戦友達をも心配させ苛立たせた。そして今日も暮れようとする夕方待ちに待った電報が入った。『テキ攻撃熾烈ニシテワレ防戦ノイトマナシ、タダイマヨリ通信機ヲ破壊シ、コレヲモッテ、ホンタイトノ連絡ヲ絶ツ、ホンブヨリノゴ指導をカンシヤシミナサンノ武運長久ヲイノル、ダイ一〇三コウクウタイバンザイ』これでいま死を向かいつつ有る我等仲間達との最後の絆を絶った。私は復唱しながら情報綴りに記載していた。字が涙で霞んだ。
当直将校に報告すべく『当直将校』と言う前に私に背を向けて「報告はせんでよい」と力なく言われた事を今も忘れた事が無い。
勤務を終え夕食時も誰一人として一言も発する者も無く、ただ黙々と食事を終え、皆はやばやと寝床に入り毛布をかぶって泣いた。つい一ケ月前まで寝食をともにして居た明るい友が皆に代わつて私が参ります、私も参加させて下さいと、二十才の二人の若者は夕飯を喰ったろうか?喰う間も無く空腹のまま死んだかと思うと不憫で成らなかった。
あの犠牲的精神の若者が現世にあったならどんなにか社会の為に尽くされた事で有ろうと思う。勤勉な日本人の英知と弛まざる努力によってあの敗戦の荒廃から見事に立ち上がり、今日の様な経済大国と成った。平和がいつ迄も続きます様に。
記録に出ない特攻隊
戦局も押し詰まった二十年に入り、東部ニュウギニヤ戦線も悲報が相継ぎ、ついに東京二十五師団と弘前二十六師団の配備する西部ニュウギニヤへと主戦場が移りつつ在ったある日、米艦隊ビアク島に接近の報に時を経ずして私の居るアンボイナ、パテムラ飛行場へ○戦の一隊が飛来して来た。
特攻の命令は夜十時から十二時の間に来た様に記憶して居る。その間隊員達はトランプ等をして時間を過ごし、十二時を過ぎてアァ今日も一日延びたか等と冗談を言い合い寝に就いた。特攻の命令は伝達者である当直将校と当直の先任衛兵伍長を衛兵が先導し三名で来るので外部の足音にも神経を使って居た様だ。そして二、三日後だつたろうか、ビアク島攻撃のアメリカ艦隊へ突撃命令が下った。薄暗い電球の下に整列した隊員達の緊張した顔が青白く見える。我々整備員達も手早く服装を整えて整列した。
命令の伝達者で在る当直将校の心中もいかばかりだったろうか。おもむろに海軍中尉何某、海軍少尉何某と何れも学徒兵出身者の五名の隊員が指名され、明朝四時出撃する事に成った。その隊員達の為にと整備員達は勿論、それに関係する者は寝に就く者は無かつた。私の隊では他に聞く様に燃料は片道で無く、エンジン不調のため他の基地へでも飛べる様にマンタンにした。
昨日から眠る事の無い隊員に眠気をもよおす事の無い様にと覚醒剤?の注射を済ませ、出撃前の暫しの時間戦闘指揮所前にたむろして居た隊員達は、いま一時間半後の死を目前にして気負ったところも無く淡々として非常に冷静で有った。むしろ隊員達の気持を思い、沈んで居る我々整備員達に冗談を言ってアベコべに励まして呉れたり(後の事を頼みます)とも言われた。
そして簡単な出陣式に別れの杯を交わし、自分の愛機に向かった。南国の夜明けは早いヤシのコズエが白く明け染める頃、本部より『手空き総員特別攻撃隊員見送りの位置に付け』の号令と共に滑走路に全員が整列して『帽振れ』の号令に一機また一機と最後の別れに、手を振りハンカチを振り、或いは敬礼をしながら轟音を響かせ飛び立った。我々は帽子も千切れんばかり振りながら心の中で攻撃の成功と生きて帰って呉れと祈る様な気持ちが入り交じり何とも言えないやるせ無い思いだつた。そしてゴマ粒の様に小さく成り、遠く遠く南溟の雲の彼方に消え再び帰る事が無かつた。
今年も又八月十五日がめぐつて来た。毎年の様にテレビに映る神風特攻隊が物凄い弾幕を突いて敵艦隊に突入の光景を目にする度に、あのラハの飛行場から飛び立った特攻機を思い出し、思わず心の中で「当たれ、当たれ」と叫び涙がにじむ。
十年も前に慰霊船でご一緒に成った年老いたご婦人に船中で私にはアンボンと言う処で忘れられないこんな事が有りましたと特攻隊を見送った事を話したらその方は私の息子も特攻隊で戦死しました、唯ニュウギニヤ方面とだけ知らされて居ましたが、息子は貴方達に大切にして項きお見送りして頂いた事と思います。どうも有り難う御座いますと丁寧にお礼を言われた事が有る。
私は戦争を美化する気持ちも賛美する等と言う気持はヒトカケラも持ち合わせて居ない。今年八十三才、もう人生の終幕が降りる順番が廻って来たあの悲惨な戦争を伝える残り時間はもう残されて居ない。
戦後五十六年、平和な時代が続き自由と繁栄を謳歌して居るが、今日の繁栄は祖国の為に散った尊い犠牲の上に立って居る。
戦前までは「おしん」の時代が続き、戦後一時期低開発国として国連から援助を受けた事も有る。日本は富士と桜を代表する様に美しい国だ。しかしこの美しい国の為に命を捧げた英霊を冒涜する様な政官界の腐敗は今にして国民が自覚せざればローマ帝国の様に栄えて滅びるで有ろう。
朝風43号掲載 2001.10月

水筒の水で命を狙われた
横浜市 小沢 政治
それは敗残兵生活中のことであるが、自分の部隊は、師団への合流作戦の行動中、夜半に全滅し、私は戦車に追われて崖から飛び降り奇蹟的に助かった。
それからは、単独行動の生活をしていた時のこと、ある壕に潜り込んでいたが、日中は各所に米軍陣地があり、残敵討伐で巡察兵がやってくるので、暗い壕の中で戦死者と共に横になっていた。
若干の手持ちの乾パンもあり、夜は撤収していった米軍陣地跡に行くと、残していった戦時食の缶詰めや、梱包されたままの日常食、チョコレート・ビスケット・タバコ等が手に入ったので、空腹に悩むことはなかった。
だが飲料水だけは手に入らない。これは何処に隠れて住んでいた敗残兵でも同じであった筈。或る月夜の明るい晩であった。敗残兵仲間の情報で聞いていた東の方向、小さな丘の下に壊れた水槽があり、底のほうにはまだ水が残っているとのこと。そこで米軍陣地を警戒しながら捜し求めた処、見つけたが、丘のほうから撃ってきた。だがすぐにやんでしまった。水槽の中に飛び込み、砲弾で破壊された瓦礫の岩石がゴロゴロあったが、その隙間に溜り水があつた。持ってきたカラの水筒二本に詰め、たっぷりと飲んでから這い上がり、元来た方向へと歩き出した。
もうこの当時は兵器や武器は、手榴弾すら持っていなかった。米軍に見つかった処で抵抗すべき武器は何も持っていなかった。この辺は激戦場の跡なので草木は一つもなく、砲弾で破壊されたゴロ岩の大小がゴロゴロしてあった。
元の壕方向へ見当を付けながら歩いていると、暗い中から目の前に急に三人の敗残兵が現れた。彼等は背嚢も付け銃も持っていた。
「この辺に水槽はないか」と聞いてきた。「どこにいるのか」とも聞く。自分はこの南方向の下で壕の中で一人だけで潜って生活していると答えた。「水を持っているようだが何処にあるのか」と聞く。そして、「その水を半分よこせ」と云う。東方向の水槽のある方を指差して水のある処を教えた。「米軍陣地はあるか」と聞くので「撃つてきたが、すぐやんでしまったので攻めてはこない。大丈夫だ」と云ったのに、その水槽の方えは行こうとせず、三人で何やら話し合っていたがやがて去って行った。
その方向は私が教えた自分が住んでいる方向に去っていくではないか。「水槽方向は違うぞ」と教えてやろうと思い、どのへんを歩いているのかと、地面に顔をつけて月明かりでよくよく見ると、前方の岩の向こうに上半身を出している三人の姿があった。よくよく見ると、銃口をこちらに向けているではないか。私の来るのを待ち構えているのである。咄嗟に危険を感じた私は反対方向に飛ぶように走り去り、遥かに大廻りをして元の壕に戻っていった。
あのまま知らずに、のこのこと歩いて壕の方へ向かっていたら、彼等の餌食となり水筒は奪われて、屍は近くの凹みにでも投げ込まれたであろう。米兵の弾に当り、どこかの敗残兵が一人あの辺で死んでいたぞとなり、私の人生は了っていたのである。
あの辺には友軍の兵の戦死体が、あちらこちら、転がっていたので、やがて米軍がブルト-ザ-で寄せ集め、ひとまとめにして一ケ所に片付けたことであろう。盛り土をして用地とし、飛行場にしたり道路にしたり、宿舎用地としたりしたであろう。
戦死体は地下深くに永遠に眠ることに成ってしまったのである。
後日談になるが、戦後、遺骨収集団が度々あの小さな硫黄島に渡島するも、未だに二万余名の玉砕将兵が、八千名きりしか見つかっていない。ご冥福を祈ります。
朝風46号掲載 2002.1月

火炎壕よりの脱出記
神奈川県 小沢 政治
敗残兵として住み慣れた壕は、遂に米軍に発見され、火炎放射機を吹き込まれて、壕内通路に敷きつめたように置いてあった小銃弾箱に火がついて、焔をあげて炸裂し始めた。
午前中、一人の米兵が覗き込んでいたが、その内に銃を入口に立てかけて、中腰になって入ってきた。入口近くには、手榴弾を投げ込まれても、奥までは転がって来ないようにと、通路に岩石を組み、防止垣が築いてあった。それを首を縮めて跨いで入ろうとして、尻がこちらに向いた時、もう不在の真似をしていても駄目だと思い、三八式歩兵銃で撃った。当たったかどうか、判らなかったが、米兵は、ものすごい大声の悲鳴をあげて逃げていった。勿論、入口の銃は頂いておいた。
攻撃に来ることと覚悟はしていたが、いきなり火炎放射機を吹き込まれるとは思って居なかった。入口にダイナマイトをしかけて閉鎖し、生き埋めにするであろうと思っていた。近くの壕は、この作戦でやられていたので。このため壕の奥の方に逃げていた。この壕は、奥は行き止まりであり、入口近くに横路があり、突き当たりには、出口ではないが、どうやら出られる穴が開いていた。
奥には、どこの部隊の兵だか知らないが、2・3日前に「行くところがない、夜明けも近いが、潜るところが見つからぬ」と言うので、この壕に一時入れてやることにしたところ、2人だと思っていたら、7・8人が入ってきた。銃を持っている者もおれば、何も持ってない者もいて敗残兵そのものであった。壕奥には米俵が積んであり、一同はその上に乗って横になっていた。この時、防毒面を持っていたのは、私だけだった。入口近くより炸裂している火炎が迫ってくる。その前にガスが襲ってきて息苦しくなり、私は急いで防審面を装着したが他の者は濡れ手拭いで鼻を押さえているのみである。
これでは永く保つわけがない。苦しみ始めた。炎は近くに迫ってきた。ここに居ては焼き殺されてしまう。と思った私は、意を決して、通路入口近くにある横路の先にある抜け穴から、脱出する気になった。入口近くまでの通路は、焔が一面であり花火の如く小銃弾箱の炸裂音がバンパンともの凄く、この焔の地獄の中を、しかも素足で駆け抜けたのであった。
横路へ飛び込み、抜け穴へと近付いた。穴口近くは土砂で滑って登れない。正規の出口には、米兵がいるであろうから、行けば撃たれるだけである。懸命に登り、ようやく外に出た。平地まで飛び降り、目の前の分隊壕に飛び込んだ。
ここは、戦闘中の戦死者を詰めた小さな壕で、中は戦死者の山である。この中に、もぐり込んだ。周囲を巡回警備している米兵も、戦死者には手を出さない。夕方になったら引きあげていった。この戦死者の方々により、私は助けられたのであった。
その思いを忘れてはならぬと、戦後、遺骨収集団員で渡島、この壕を、やっと見つけて、壕内に入ったところ、何年か前の収集団員が収骨したのであろう、壕内の隅に当時の履物、地下足袋の底のゴムの部分のみが積んであり、きれいに片付いていた。
千鳥が渕墓苑に行かれたのだと推察することができ、私の心の重荷はおりて、ホツとした。ご冥福を祈り、壕を出た。
この時同行していた元陸自教官、今はOBで団員の一員を焔の通路壕内へ案内した。
通路の天井に無数に刺さってある弾痕をみて、一発も当たらずに、よくこの中を通り抜けられたものだ、と感心していた。
私には、神のお加護があった、としか考えられない。
奥に居た者は、どうなっているかと行つてみたところ、白骨の御柱と化していた。
あれ程あった玄米俵が一つもない。地表をよく見たら、米粒が見つかった。足元を鼠がチョロチョロしている。永い間に、この連中が食べ尽したのだと察しがついた。
私の脱出穴ロの近くに、一柱が見つかった。あの時、私の後を追ってきた人が一人いたのだと、この時、判ったが、あの時は気か付かなかった。ガスにやられたか、炸裂小銃弾にやられたのか、誠にお気の毒でした。ご冥福をお祈り致します。
朝風48号掲載 2002.3月

火焔壕よりの脱出記(2)
横浜市 小沢 政治
壕洞穴に入れてもらえず、生きのびた。火焔の壕内より脱出し、戦死者の屍の山にもぐり込み、死の運命からは生きのびたが、素足で脱出したため下半身は火傷、足を引きづらなくては歩けない。何も持ってはいない。ボロ被服を身につけた敗残兵では何処に行く目的地とてない。部隊はすでに北地区で全滅しており俺一人生きていても仕方がないと考えた。死のう、自決しよう、と。
島の全土は占領されてしまいこれから先、援軍が来ることはあるまい。海に飛び込み死ぬことにしようと思い、丘を下り、トボトボと痛い足を引きずり乍ら、夜の古戦場を歩き出した。
海岸方面に向かう。右や左に低い丘があり所々に独立岩盤もあった。この谷あいのような所を歩いて行くと、点々と右や左に洞穴や壕口があった。どこの入口に立つても、中に敗残兵が居た。「食糧持っているか武器持っているか」と聞く。何も持っていない負傷兵だと判ると「ダメだ、早くたち去れ」、何処の洞穴でも入れて
くれない。次々と歩き、海辺近くまで来てしまった。
東の空が、うす明るく成ってきた。よく見る、この先は海岸に打ち寄せた芥の山である。夜が明ければ丘の上の陣地から狙い撃ちにされることは当然だ、と判り抜いていた。海水の近<まで行き内陸側を背にして岩盤の下へ座り込む。前の芥をかき寄せ集め、芥の中にもぐつた形となった。
この時、同じような運命の兵士が一人現れた。二人で向き合い足を組み合わせて芥を被ぶり、再び夜の来るのを待つことにした。明るくなり陽も高く揚がった頃昨夜歩いてきた内陸の方向から日米両軍の撃ち合う銃声が聞こえてきた。日本軍の銃声が絶え、米軍の銃声のみとなる。再び少し近くで又同じような銃声次に一方的な米軍のみの銃声。昨夜通ってきた谷あいを次々と米軍が残存兵の掃討で海の方へと近づいているのだ。昨夜入れてくれなかった壕が次々と討伐され、壊滅してしまったことが、銃声で推察できる。
この間、銃声の絶えている時、足を組んで前にいる友が手真似で「一服吸ってもよいか」と云っている。私は「ダメだ」と手を横に振った。この時背にしていた岩盤の上を横上目で見たら、米兵の姿、下半身が見えるではないか。海を背にして銃を横抱えにして今戦闘してきた方向を見ているのである。これを彼に指を差して知らせた。
米兵にしてみたら、足元の芥の中に敗残兵が二人いるとは判らなかった。気がつかなかった。昨夜あのどこかの壕が、親切に入れてくれたならば、私の運命は、あの谷で了りであった。又「タバコを吸ってもよい」と合図をしてたならば、運命はそこまでで、芥の中に二体の屍が浮いていたことであろう。
ここでも私は生きのびた。そして、この平和ボケの世に生きて居ます。
朝風49号掲載 2002.4月

匍匐前進で死地を脱出*火炎壕よりの脱出から続く*
横浜市 小沢 政治
神山海岸の水隙で芥を破り、陽が暮れるのを待っていた敗残兵に、やがて待望の夜がやってきてくれた。さあどうしようか。とにかく砂地の処に出ることにする。水際伝いに西方面擦鉢山方向に歩き出したらば前方右方向、つまり内陸側から丘が海方向に延びている。この丘の上に米軍陣地があつたのだ。
月の明かりで判ったのだが機関銃が撃ち込まれてきた。思わずその場に伏せた。斃れたとみたのか撃ってこなくなったので、又、元の方向へと逃げたが、何としても砂地の原を突破して内陸側の戦場跡の瓦落多岩石のある処まで行かねばならない。隠れる所潜む所がこの海岸ではないのである。二人で、どうすべきか話し合っているところに、どこからか一人の兵が現れた。彼はこの兵と何やら話合っていたが、あの丘の裾を伝わり内陸方向に進めばよいと言う。私は、それは危険だと言ったが、あの陣地からは足元の下の丘の裾は見えぬ筈だから大丈夫だと言う。二人はそのうちに私をおいてスタスタと行ってしまい闇の中に消えた。暫くしてから機関銃が撃ちだし、照明弾が揚がり、手榴弾も投げ込まれているようである。小一時間もしたろうか。
静まったところで私は、この砂地の原を内陸に向けて匍匐前進で抜け切ることに決めた。前進するうちに、あちらこちらに戦死体があるではないか。少しずつ進めば丘の上から見えるであろうこのゴロゴロしている戦死体の一体が多少動いても、前進しても、あの丘の陣地からは判るまいと自信がついた。ある一人の死体のそばを通り抜けた時、触ってみた。突っついてみたが反応はなかった。日なかの戦闘で戦死されたのであろう。動かないし声も出していない。
月の明かりが邪魔になるがどうにもならない。動きが見つからぬようにと、ひたすら砂の匂いを嗅ぎながら前進するのみであった。相当な時間が過ぎ去っていることはわかる。あちらにもこちらにも戦死体はあつたが、ひたすらこの間を抜けて前進した。
瓦落多岩石の丘の裾が近いとみた処で意を決し、素早く立ち上がり一目散に突っ走った。気が付かなかったのか撃ってこなかった。砲弾で崩れたのであろう岩石の間に飛び込んで身を隠した。行く当てはないけれどもヤレヤレ、これでなんとかなるぞと岩石の間をぬって、内陸へと一歩一歩掴まりながら歩き出した。暫く行ってからあの二人はどうなったことだろうと考える余裕が出てきた。多分あそこでやられてしまったのではないかと思えてきた。一人は二宮という所の出身で後から来た他の一人は、その土地の造幣局が勤務先とか話し合っているうちに意気投合しよそ者の私には「行くぞ」の声もかけずに消えてしまったのだ。
人間、死に直面すると藁をも掴む気持ちが働き、心動くものであることを知った。友情も何もない。そのとき生き延びればよいのである。この敗残兵生活で、頼りになるのは、この自分だけなのだとつくづくと実感した。
これから先々のPW収容所生活でも、復員後の慰霊祭の会合でも、合う事が無いあの人は、やっぱりあの丘の上からの攻撃戦火の中に斃れたのであろうと思っている。生と死の別れの運命は、紙一重の差どころではないと思う。戦争の犠牲者よ、安らかにお眠り下さい。
朝風51号掲載 2002.6月

一宿一飯*匍匐前進で死地より脱出から続く お世話下さった壕*
横浜市 小沢 政治
匍匐前進で、ようやく死線を抜け切ったものの、瓦礫の山の中にいても、夜が明ければ米軍陣地からか、又は上空を低く飛ぶ偵察機トンボのような、あの軽飛行機に、必ず見つかってしまう。何処に行こうか、どうしたものかと考えながら、よたよたと歩いているうちに、どこからか闇の中よりスーツと一人の兵が寄ってきた。
この人は小銃も持ち武装もしている。「何処に行くのか」と聞くので、昨夜までのことの概要を話すと「故郷はどこか」と聞くので「横浜だ」と言うと「俺の叔父も横浜にいる。弘明寺という寺の近くだ」と言うので「その寺は自分の通った小学校の近くだ」と答えたところ心が通ったのか「夜明けが近い。この先にある砲兵隊の壕に入れてもらおう」と歩き出したので追いていった。
我が壕に入るが如く、ある一つの大きな岩石を横に除くと壕口があった。彼が先に入って行くので後につづく。奥の方にローソクの灯りが見える。近付くと何かの箱を机の替わりにして、白い鉢巻きに血を滲ませて仏像の如くデンと座して一人のボスらしき人がおり、背後には陸軍の服や海軍の服を着用している兵が、ぎっしりと居た。包帯姿の者が多いようであった。
「どこの兵隊だ。どこから来たのか。米軍陣地はどの辺にあるか」と聞く。これらについては彼が答えていた。「負傷しているのか。していなければ一晩だけ泊めてやる。その入口の近くで寝ておれ」と、奥の多数の人員の中には入れてくれなかった。敗残兵にとって、この場合の一晩とは、外に太陽が昇っている間だけのことである。土の上だがゴロリと横になり一眠りできた 外は暗くなり敗残兵の一夜は明けたらしい。「そこの二人、こっちへ来い」と呼ばれた。「もう暗くなった。出て行け。食糧はあるのか」と聞く。「無い」と言うと、小さな缶話めを一ケづつ<れた。「入口の岩をよく乗せて行けよ」と言う。
外に出た彼は「我が部隊の方へ行ってみる」と、スタスタと歩き出し闇の中に消えて行ったここで又単独となってしまった。自分の身は自分で処置しなければならないのだ。俺は、組織的部隊からは外れ、一人きりなのだ。北地区の兵団への合流作戦で全員玉砕後は、生きていてはおかしい兵なのだと、この時しみじみ感じた。自決すべきではないかと。
手に持っていたか缶詰一ケは開ける道具もないし、その術もない。空腹は感じなかつた。これは生きるための緊張感がそうさせたのであろうか。死ぬか、どうして生きてゆこうか、とか。まとまらぬまま、何処をどう歩いたのか何となく我が部隊の陣地居住壕方向と思われる方へ歩いていたらしい。何となく住み慣れた壕の近くの丘や谷間が似ていると思える処を歩いているのに気が付いた。やはり間違いない、この谷間だと自信がついてきた。夜が明けぬ内に、どこかの壕口を見つけようと考えて歩く。だが、どこの分隊壕でも総出撃してしまった後なので、生きている兵は誰もいない筈だ。もしかしたら負傷兵が生きているかも知れない。各自に手相弾を自決用に渡されたのだから生きてはおるまい。でも、生きていてもらいたい、自分に都合のよい方に考え願いながら壕口を捜し歩いた。分隊壕は各所に見つかった。
あのとき、自分が焼き出された壕の、その後のことが気になった。あったあった、中は暗くて判らないが、両手で両脇の岩壁をさわり乍ら、一歩づつゆっくりと奥へと進んで行った。
この日から、一人だけの本当の生き残り敗残兵生活が始まったのである。米軍は、一度攻撃して焼き尽くした壌であるから、同じ部隊ならば、やっては来ないと思っているだろうと、自分勝手に都合よく考え、安心して住むことにした。
朝風52号掲載 2002.7月

一人ぼっちの敗残兵生活*一宿一飯から続く*
横浜市 小沢 政治
数日前に焼け出された中隊壕内の、真っ暗な土の上に腰をおろして、落ち着いて考えてみた。よくぞあの壕で泊めてくれたものである。でもキッパリ一泊で出された。あの時は恨んだが、食べ物を心配してくれて、小さな缶話一ケでも与えてくれた有り難さ。あの壕もあれだけの負傷兵がいたのでは、食も水も推持していくのは大変であろうに、よくぞ泊めてくれたものだと、出されたときの恨みは消えて、感謝の気持ちにと変わった。その壕に永くおいて貰えたならば、私の運命はどうなっていたか、今でも分からない。
それは、戦後約四十年、或る年のこと、遺骨収集団員として渡島し、この一宿一飯のお世話になった壕をやっと探し当てた。地形がまったく変わってしまい、近くに野砲隊の弾薬庫が見つかり、この丘の裾を掘削して行き、壕ロの崩れらしき所を探し当て開口したところ、出入口が見つかり、平坦な通路で結ばれている。(私はここに一泊させてもらったのだ)
壕内は火炎放射機で攻撃されたらしく、壁も内部のガラクタ物品もすべて黒焦げであるが、人骨は一片も無い。あれだけいた負傷兵が何処へ消えたのか。最後の突撃で出陣した、としか考えられない。
収集団はこの壕では収骨作業は期待外れとなった。復員するまでの各収容所では、この部隊の壕に居たという人には一人も会わなかった。あの負傷兵は、各部隊の斬込み隊員が負傷し、本隊に戻れず、どこか近くの壕にでもと、夜の明けぬ内にと急遽避難したところではないかと考えてもみた。陸軍野砲隊の壕であるのに海軍兵の姿も見たし、あの辺りは、斬込み隊の向かう目標地点でもあったから…。
「一人ぼっちの敗残兵生活」の題名からは大部外れましたが、元の壕内生活に戻します。
一番困ったのは飲料水と食糧を手に入れることですどちらも決死の覚悟が必要です。
飲料水の入手には、苦労というよりも、毎回が決死の覚悟を必要とします。出撃後の空き壕内に、マッチをすり乍ら危険物を踏まぬように、気を配りつつ入り込み、残置の水入りドラム缶を探すのですが、ある時のこと、狭い通路で焼かれた後のガラクタ物の上を踏み進むうちに、グジユ、グジユと足元で音がする。この辺に水が湧いている処があるのかなァと思い、ガラクタを足で掻き分け探すうちに、屍の腹の上に乗つていることが分かった。申し訳ないことをしたと、すぐに飛び退いたが、この後は地下足袋に死臭がしみつき、どうにも臭くて履いておられない。奥まで行ったが、目的のドラム缶は無かった。
時には小さな壕でもドラム缶があり、底の方に残り少ない溜り水らしきものがあり飯食の蓋で掬い上げ、水筒に入れて持ち帰る。褌の布端で漉して飲むのだが、漉し切れず、口の中でジャリジャリしている。鉄錆び臭いのは初めのうちだけで苦にならない。砲撃された地下水槽の底にある溜り水は、屍体があれば、そこを除けて汲んでくる。汲む前に先ず腹一杯飲んでと、カブリと口に入れるのだが、喉のところでボーフラがムズムズやっている。戦闘前から兵士仲間では、ボーフラが生きて居られる水は大丈夫だと言っていた。地下水樽の残り水を汲みにくる敗残兵がいると分かり、米軍は近くに陣地を築き、近寄れなくなった。そのうちに大きく破壊されてしまった。
道路の凹部の溜り水を入手する方法があつた。月夜に道路に出て、地面に顔をつけて遥か向こうを見るのである。水のある所は光っている。軍用車両は来ないか。近くに陣地はないかと十分に警戒し乍ら近付くのである。この水も、布で漉しても口の中はジャリジャリする。夜になると何処からともなく集まる処、敗残兵銀座と名の付く小山があった。ここで仕入れたのだが、よい方法があるときいた。それは道路の溜り水を汲み取り、手早く持ち帰る方法であった。それは毛布を持参してゆき、その水の上に乗せて吸い取らせるのである。これを担いで帰り、壕内に来てから二人で向き合い絞るのである。出てくる水を銀名水と言っていたとか。(島で一ケ所のみ洞穴内に滴が落ちる処があり、この水のことを平和時代から島民の方はこう称していた)と。
次は食糧の入手方法だが、炊事場跡を見つけて、使い残りの箱の中から乾パン、時には缶詰が見つかることがあった。一回見つければ一人で食べるには暫く食い伸ばしすることが出来た。米軍野戦陣地の撤退跡が運良く見つかると、食べ残した缶詰、開けてない缶詰、野戦食の食べ残し、その他いろいろ使い残しが手に入った。これは大助かりだったが、こんな旨いことばかりは無かった。撤退跡だと思い込み近付いたら撃ちまくられ、どうやら逃げ切ったこともあり、夜盗賊はいつも命がけである。
敗残兵銀座について・・玉砕後の僅かの生き残り兵は、組織もなにも無いままに、各部隊の出撃あとの空き壕に一人二人と住んでいた。武器もないのでゲリラ戦も出来ないのである。野良犬みたいなもので、飲み水、食べ物をあさり歩くだけの動物に過ぎないのだった。これらが夜になると且つての激戦場の玉名山の一地区に集まってきている。遠くからでもタバコの火の光が見えた。もうこの頃は、米軍の照明弾も上がらないので真っ暗である。どこから聞いてきたのか、連合艦隊が近くまで来ているとか。近いうちに潜水艦が我々を救出に来るとか。戯いもない話を開いていると、東の空が薄明るくなってくる。いつの間にか一人二人と消えて壕に戻っていく。ここは情報交換所でもあったが、役に立ったニュースは無かった。
銀座まで来る途中に昨夜は仆れていた兵士を見たが今夜は小岩石片を被せて小山になつていた。何らかの本人の持ち物が乗せてあり、米軍が死者に対し懇ろに葬ってくれたのであろうと思い乍ら、通り過ぎていた。この頃の友軍は、そこまでは心に余裕もなく、やれないことで、やがては「あすは我が身も」であったのだ。
この頃の心境は、今、生きているのが、いけないのだ。いつまで、こんなことをして生き伸びることやら、生きていても仕方がないが、やがていつかは、米軍の弾に当り死ぬことであろうが、「その時は苦しまずに死にたいものだ」と「心の中で念じていた。
朝風53.54号掲載 2002.8月 9月

敗残兵がPWキャンプヘ *一人ぼっちの敗残兵生活から続く*
横浜市 小沢 政治
ある日のこと、真っ暗な壕内の出口が急に明るくなったのは、太陽の光が入ってきたのだった。積んであった岩石の一つが除かれたためで、どうして壕口が分かったのか、足跡を辿って来たのか、それとも犬を連れてきたのか、それは知るところではないが、この場所は、ある丘の下部に艦砲射撃で砕かれた岩石の大小が積み上がり盛り上がっているのだ。その内のある一ケを取り除くと、猿の入れる位の穴があき、これが壕の出入口であったが、故郷への土産にと戦利品漁りに米兵が開けたのであった。
壕内は入口から滑らかな下り坂となっていて、中間には石垣を天井近くまで積んでおいた。何を投げ込まれても、撃ち込まれても直接奥の方までは来させない計画のもとに、仕上げた苦心の工作であった。覗き込んでいた米兵は、入口の積み岩を除き、大きな穴にしてから、銃を片手に入ってきた。この石垣と、壕の天井との間は、いくらも空いてないのに、銃を壁に立て掛けてこの空間を利用し石垣を跨るようにして、先に尻をこちらに向けて入ってくるのではないか。入って来られたら、捕まるか殺されるか、人生の終わりだと覚悟は決めた。壕内に残っていた銃は使えるかどうか、半信半疑で尻に向けて引き金を引いてみた。当ったのか、どうかは分からなかったが、もの凄い悲鳴を上げて飛び出していった。カービン銃は置いたままにして。
この銃は必ず取り返しに来るだろう。その時は、何か投げ込まれて、それが我が最期の時だろう、と覚悟はしていたが、小一時間位したら壕の外で人声がしている。その内に、顔は出さず、見えないが、下手な日本語で、「戦争は終わった。出て来なさい」と、同じことを二、三回繰り返していたが次に人が替わって、今度は上手な日本語で同じことを言い、「お-い、俺は工兵隊の00だ。話があるから出て来いよ」と「撃つなよ」と言ってから顔を出し、覗きこんでいる。日本人の顔だ。同じことを言うので、一応入口近くまで出て行くことにした。「工兵隊の00だよ。知らないかなあ」と。工兵隊員は各部隊に壕堀りの指導員で出ていたので、知人が多くなっていた筈である。「とにかく、もう戦闘は終わっている。収容所にも大勢居る。米軍は殺すようなことはやらないよ。大丈夫だ。こんな処にいつまでも入っていないで出て来いよ。被服の新しいのをくれるし、三度の食事も出してくれるよ」と。私はこの工兵隊員は知らない人だが、何だか全部は信用できなかった。
「一晩考えさせてくれ」と言ったところ、壕外にいる人と話し合っていたが、「では明日、今ごろ必ず来るから、今夜は外に出てはいけないよ。この入口の外にはトタン板を敷いたから、歩けば音がする。前の方には機銃陣地が出来たから、出れば撃たれるから」と言い残して去って行った。
この壕は他に抜け穴があったのだが、今は鑑砲で崩されていて埋まっていてしまい脱出出来ない。外に出れば撃たれるし、鼠捕りの篭に入ってしまった鼠も同様だ。昨白までは勝手に外に出たり、陣地だけは近付かないように気をつけていれば、何処へでも自由に歩ける身であったのが、もうこれでは捕らわれの身だ。どうしたものかこの時は心の中で半分以上は彼の言う事は信用していなかった。何処かに連れて行かれ、捕獲した日本刀の試し斬りにされると考えていた他のことは考えられなかった。
どうしたものかと悩んでいるうちに、いつの間にか寝入ってしまったらしく、予定通りに呼び出しはやってきて「お-い」という人声で眠りが覚めた。やっぱり来たかと思った。「出て来いよ」と言う。覚悟を決めて出てみたら、明るい太陽のもとでの壕外は、珍しい別世界に来たように映った外を歩くのは夜だけだったのだから、土竜が地上に出たようなものである.眼の前には米軍兵士数名と将校一名が居た.
戦利品の日本刀で、試し斬りされるならば、この世の名残りにと思い、腰の水筒の水を飲み干すつもりで、口にもっていったところ、前に立っていた将校に、いきなりこの水筒を叩き落とされてしまった。飲ませまいとしたのである。地上に転げ落ちた水筒からは、真っ黒なドブ水が流れ出していた。命をかけて手に入れてきた水だったのだ。暗い壕の中で、なめるようにして大切に、飲んでいた命の水なので、色には気が付かなかったが、褌の端の布では、よく漉せてないことは分かっていた。
将校は腰に着けていた自分の水筒を外し飲めと言って渡してくれた。これはアメリカ軍の水だと思い乍ら飲んだ。飲み終わったところで、持ち物を出せと言う。ポケットにあった乾パン半袋と、拾った米軍のマッチ箱、自分の腕に着けていたが動かなくなった時計、これも指差している。出せと言っているらしい。身に着けていた物、持っていた物は全部取り上げられたが、故郷を出るとき持ってきた神社仏閣のお守り札入れの小さな袋は、気が付かないのか何も言わないので、腰のバンドに着けたままにしていた。これが後々まで只一つ、我が身と共に戦場を歩き回った友であり弾の中、死線をくぐり抜けて来た友なのである。よくぞ自分を守ってくれたと、感謝の気持ち一杯である。
米軍は汚い水筒の水は飲ませなかったので、「殺しはしないナ」と、何となく分かってきた。海の方を指差して「歩け」と言っているようなので、トポトボと歩き始めた。細い道の土手にお白粉花が一輪咲いていた。花を見るのは暫くぶりなので大へん懐かしく、立ち止まって見ていた。お前もあの砲弾の中をくぐり抜け、よくぞ生きていたナと、頬摺りしてやりたかった。「歩け」と肩を叩かれた。先方の岩かげに赤十字マークの付いた車が停めてあった。乗れと言う。野戦病院にでも連れて行かれるのかと思っていたら、着いた所は西海岸の砂地、天幕小屋の周囲にはバラ線が張りめぐらされてあった。
まさしく捕虜収容所である。出入り口の扉は、木の枠組みでバラ線で出来上がっている。入ると左に小さな天幕小屋があり、この前で虱のついた懐かしの軍服ほか全てを脱がされて、米軍兵士用の中古作業服が支給された。服には大きくPWのマークがペンキで入れてあった。天幕小屋の中には机と椅子があり、事務室か管理室なのであろう。日本語の上手な米兵と、PWの服を着た通訳係らしい者が居た。部隊名、氏名
を言えという。この通訳人らしきPWは、そばで助言するつもりか、「ウソは言うなよ。後藤又兵衛とか荒木又衛門なんて言ってもダメだぞ」と。部隊名は本当のことを言ったが、氏名は咄嗟に気がつき、上の一字を飛ばして次の一字のみにしておいた。(後で判ったのだが、相当数の者が、偽名を使っていた)
深いことは聞かれなかったそして第一キャンプに連れて行かれた。責任者に渡すでもなく、入口に立たせておいて行ってしまった。中の者に聞いたら、奥の方に責任者?が居るとか。人々をかき分けねば行けぬので、その場で大声で「中迫兵の沢です。よろしくお願いします」と言ったところ、奥の方から声あり、「今ごろノコノコ出てきやがって、もうお前の場所は無いよ」と、「もっと壕の中に入っていろよ」と、余計な奴が入ってきた、と言う投げやりの言葉である。前に居た二人がつめてくれて、「このすき間に入れ」と言つてくれた。現代風に言うなれば、野犬狩りをして捕らえてきた犬を小屋に投げ込むようなもので、小屋の中は猿族のようにボスも居ないし、組織化されてもいないPWの服を着た、野犬のような集まりなのであつた。
支給になった給食用の米軍野戦食缶詰め一人二ケは、先輩PWが有無も言わせず、「これと取り替えろ、よこせ」と一ケを自分の好みの缶と取り替えて持って行く。取り揚げられぬだけ良いとしておくしかない
幕舎内は灯は無く外灯のみ。夜間に外にある便所に行けば元の所が判らない。日中は作業も何も無く、時により何処かの壕の呼び出しに、使うのか、呼ばれて出て行く者がいた。バラ柵の向こうの天幕は将校だけのPWが居るのだと聞いたが、姿も見えないので、本当に居たのかどうかは判らなかった。
朝風55号 56号掲載 2002.10月 11月

西海岸の収容所へ*敗残兵がPWキャンプへより続く*
横浜市 小沢 政治
西海岸砂地にあった収容所には十五日問くらい居て、グァム島の収容所に送られましたが、この間に、ある壕に敗残兵がいる、投降の呼び出しに日系二世の米軍兵が声を掛けても出てこないので、一緒に行ってくれと、ジープに乗せられて瓦礫の岩石がつづく丘の中程の所に連れて行かれた。一瞬、殺されるのではないか?と思った。寂しい戦場跡だった。やがてジープは止まり、目の前の壕内からは煙が立ち昇っていた。消防用ホースが二、三本挿入してあった。火炎攻撃や海水注入攻めをしているのであった。
「ここは自分の居た壕ではないので中のことは分からない」と言ったら「ジープの中に居ろ」と言われ車から様子を見ていたが、その内に収容所へとジープは戻った。
次の日、全身ずぶ濡れとなった日本兵が六人ほど収容所に連れられて来た。あの壕の中の人達である。まったく惨めな姿であり、よくぞ頑張ったと叫びたくなった。
その後また、ある日のこと、工兵隊員のPWが、二世兵に呼び付けられた。摺鉢山の麓の深い壕に五名位居るとのことで、例の呼び出しに使われるのである。やがて戻ってきたので、「どうしたか」 と聞くと「隣の小隊長以下が居た。現況を説明すると、一晩考えさせてくれ」と言う。米軍は「明日また来るから」と彼等に伝えてタバコやチョコレート飲料水等を置いてきた、と。彼は「夜は外に出ないように。撃たれるから」と言い残して去ってきたとのことであった。
翌日、彼は再び呼び出されて、ジープに乗って出掛けて行った。戻ってきた彼は、肩を落とし、がっかりした顔をしていた。「どうであったか」と聞くと、全員車座になって、自決していた。近くに米軍の行為に対して深謝すると記した紙片が置いてあつた、と。
日本語の上手な米軍将校や、二世の米軍兵士から、我々は次のようなことを、よく言われたものである。あなた方は十分によく戦った、それでよいではないか。もう戦闘はおわったのだ。これからの日本を再建して行く為には、若いあなた方が必要なのだ。捕虜は恥ではない。一番敵に接近した人として尊ばれる人なのだ、と。
だがこの五名の方々は、生よりは死を選んだのでした。ご冥福をお祈り致します。
歳月は、これから五十余年流れ、最近のお話に移ります。旧厚生省主催の遺骨収集団の中の調査員が、摺鉢山の麓を探査中に壕口らしき所を発見しました。よ見直したらば、正しく壕口でしたが、上部の岩盤が崩れてくる気配あり、それでも内部を覗き少し入った所、危険物が一ばいで奥には近付けない。不発弾をはじめ黄色火薬、ダイナマイト等散乱しありて、どうやら工兵隊の壕と判断できたと。いろいろと検討の結果は、あの五名が最期を遂げた壕であろうと推定、次回に危険物を自衛隊危険物処理班に処理作業を先行してもらい、五名の方のご遺骨収集作業に入る予定になっております。
この五名の方々は、米軍に「一晩、考えさせてくれ」と申し入れたその後は、どのようなことを考え、どのような意見を交したことでしょうか。心の奥の奥では、祖国日本に帰りたい、生まれ故郷に帰りたいという、細い僅かな望みもあったことでしょう。
死ぬことは、お国のため、忠義だと徹底教育された旧日本軍人精神により、死んで忠義を尽くすという最期の手段を取ったのでしょう。尊い死であったわけですが五名の合議は当時の思想としては、まったく正しかった。そして米軍に礼状を残して自決していったことは、日本武士道精神に合致したご立派な行為であったと思います。
軍人勅諭の精神が先行したか、戦陣訓のあの一行が脳裏を駆けめぐつたかは、知る由もありません。
朝風57号掲載 2002.12月

激戦場よ、さらば *西海岸の収容所へより続く*
横浜市 小沢 政治
戦火に倒れ散って行った戦友よ、すまない、サヨーナラ。地獄の硫黄島よ、サヨーナラと心の中で唱え乍ら、黒い砂をザクリザクリと踏む。ああ、この西海岸は上陸してから初めて踏む砂だ。この砂地も二度と歩くことはあるまい。凄くて酷い地獄だったが去るとなると何となく一種の寂しさを感ずる。あの丘の方で誰か呼んでいるのではないか。丘には誰かまだ居るのではないかとあの北進合流行軍で部隊は全滅してしまった、俺だけがこうして生き残り、歩いている。これでよいのかしら、だが俺には弾が当らなかったのだ。おかしい、不思議だ、なぜなのか、こんなことを思い乍ら、下を向いて黒い砂の上を歩いていた。
眼の前に船首を開けた扉の船にはや先頭は扉を踏んで車輌甲板に乗り込んでいる。二列縦隊で入り、そこで座り、甲板にゴロ寝であった。砂地の天幕内よりは周囲の間隔があり、ゆったりしている。やがて扉は締まり、うす暗くなり、もはや島の丘は見えない。船は動きだしたようだ。何処に連れて行かれるのか判らない。
噂が流れ始めた。フイリッピンの山の中で砂糖黍の取り入れをやらされるのだと、いや、もっと南の無人島に連れて行かれるのだとか。その内に米軍野戦食の缶詰が支給された。便所と水飲器は中甲板にあるという。「どうにでもなれ」という気になり眠りに入ったり、起きて食べ残りの缶詰を平らげたり。私語を交わさず静かになった時が夜間だった。
どの位の日時が過ぎたのか気にもせず判らなかった。誰かが警備兵に「この船はどこへ行くのか」と聞いたそうである。グァム島に行く、もうすぐ入港するとのこと。PWのキャンプもあるということを聞き出したらしい。
幾日か過ぎたある日のこと。上陸だという。一旦上甲板に集まってから下船する。船は立派な岩壁に係留されていた。海の水は青く澄んでいて美しかった。港内には空母から大小色々の艦艇多数が碇泊していた破損しておるような艦船は見当らなかったさすがに戦勝国の港だなあと、しばし眺めていた。
下船したPWはトラックに乗せられて丘の方向へと走る。どこにも戦火の跡らしき所は見当らなかった。こんな山の中で何かと思ったが一行のトラックは止まった。丘の中腹辺りである。前方にバラック棟がバラ線柵の中に建ち並んでいた。周囲は広くとってあり、四囲は緑の濃いジャングルである。
ここの食堂は柵外の一棟で、炊事係はPWである。米飯に副食とまあまあ結構な食事であり、出口の処で甘味品か又は果実の何かしら少々だが渡してくれて、三度の食事が楽しみになってきた。暫くぶりで口にした本当の味噌汁の味、うまかった。故郷を思い出す味だった。甘味品のドロップの数個も懐かしく、これを食べたのは、たしか日本も平和で一般社会生活の頃であったと思う。
作業はなく毎日ゴロゴロしていて時々石積みに何名か呼び出されるだけであった。この石積み込み作業に出たことがある。トラックに乗って山奥の白い岩石の砕いてある所で、手運び出来る程度の重さと適当の大きさの石をトラックに乗せて持ち帰るのである。PWは収容所前で降り、車はそのままどこかへ去って行く。この白い岩石のある山に向かう途中、同じような山道を左折したり右折したりと方向板や標識もないのによく判るものだと感心して乗っていたら、あった、あった、各十字路の角隅に頭蓋骨のみが一ケ、三ケと置いてあるのだ。いづれ日本兵の頭部であろう。日中なので白く丸い物は判り易く目につき易い。死んでまでもこのように利用されていては仏様となっても浮かばれず、天国にも行けないお気の毒なご遺骨だとトラックの上から見てはいたが、PWの身ではどうすることも出来ない。今でもあれは、その後どうなったかと思い出される。
朝風58号掲載 2003.1月

硫黄島遺骨収集団
横浜市 小沢 政治
玉砕地帯探し
師団総攻撃の時の別動隊の玉砕だと称されている所なので調査に行ってくれ、と遺骨収集団調査班員での在島中のこと、旧陸軍古参軍曹で奉仕団ではベテランのこの方と共に北地域を歩くことに成った時のことである。
あの海岸線は三段になっているから、出発前に聞かされていた幹線道路を歩き、この辺かと思われる所からジャングル内に入り込んだが、迷い込む第一歩となった。
歩き乍ら目印にと、枝を折っておいたり木の幹に疵をつけながら進んだ。よく歩いたがそれらしき所も見つからず、そろそろ帰舎の時刻も近づいて来たので、一旦、幹線道路に出ることにした。
道路と思われる方向に歩いているのだが、一向に道路に出られない。その内に、枝の折られたところ、木の肌に庇がある樹木が現われる、進む内に絶壁の如き丘が現われて、登れない。どうやら今まで同じ所をぐるぐると廻っていたようだ二人は焦り出した。助けを求めようとしてもその手段は無い。やがて帰舎せぬことが判っても夜間になったのでは探しようもないだろう。明るくなってから、ということになるだろう。それでは二人は何処かで野宿せねばならない。考え込んでしまう。
大木に登る
この辺りの高めの木に登り、周囲を見回すことがよいと気づく。木登りの得意な私は、すぐ近くの少し高めの木に登った附近は何処を見ても道らしき所は無い。青い木の芽が一面だ。
見えた。遥か遠方に星条旗が見えた。あそこは北地区に駐留する米国沿岸警備隊宿舎の所だと判った。
ジャングル脱出
方向を決めて、密林であろうと、岩壁が現われようと進路を変えず、廻り込みはせず、一心に突き進んだ。相当歩いた時に、目の前の木々の問から道らしきコンクリートの平面が現われた近づいたら道路だと判った。どうやらこれは隊内の何処かだと判ってきた。
ジャングルを出ようとすると、何処からかセパード犬の大きな奴が五匹ぐらい一塊りとなって、吠え立てるのであるが、ジャングル内には入って来ない。飛びついて来ない。ただ吠え立てるだけである。これでは出られない。杖で撲る真似をするのだが、平気で吠えている。出られない。暫くしたら平服の隊員が一人やって来た。彼が一声かけたら吠えなくなった。
遺骨収集団員であることは知っているらしい。こちらに来いと手招きするので、ついて行くと、食堂らしき建物に案内された。腰掛けていると、その内に両手に大きな缶を持ってやって来た。よく冷えたオレンジジュースであった。サンキューと一声云っ頂き、ぐんぐん飲み干した。次にカウンターらしき処にあるコーヒー給湯器を指差して、飲めと云っているらしかったが、ジュースを大缶一パイ飲んでしまったのでもう入らない。一休みしてから、お礼を云って屋外に出た。先程の犬は向こうの方に居たが、こちらに寄っても来なかった。
宿舎内では遅い帰りに皆さん心配顔でいたところに入って行ったが、迷ったとは云えなかった。この古戦場の玉砕跡は未だに見つかっていない。
朝風78号掲載 2004.10月

続・硫黄島全滅 60年前を偲ぶ(其1)
横浜市 小沢 政治
よくぞ、あれから六十年間も、生き永らえてきたものだと思う。この頃では生還者も残り少なくなり、戦場を語れる人も、その時のことを心の底から、今だから云えると前置きして話をする人も少なくなり次々と召天されて行か心に寂しさが一層募るばかりです。
これで戦争も最後の年になるのだとは知る由もないが、昭和二十年のお正月、私はやがて玉砕となる硫黄島で、激戦場となる玉名山の麓、南東地域の神山海岸台上、小高い丘の下部に横穴を掘削した小さな壕が、わが分隊壕であった。砲弾が前方に一発落下すれば、人生はこれでハイそれまでよ、となる運命の処に居住していた。航空機の爆弾はいつも飛行場方面なので、これでよかったが、艦砲射撃の時は、大きめの、近くの中隊壕に逃げ込んでいた。日中は殆ど在隊して居ることはなく、連日の如く陣地構築か勤務、何処かの部隊の壕掘りか、船からの荷揚げ作業、飛行場が爆撃された跡の穴埋め使役等で休日は無かった。
夜の不寝番や衛生勤務は無かったのが大助かりであったが、その必要も無かったからであろう。半数が海没で人員不足でもあったからか。
こんな状況出も、お正月は休みで、粉末の餅が少々と小さな缶詰が三人に一ケ、乾パンが数個加給された。餅の粉末は後刻、炊事係りが集めて、水っぽい粘った餅らしき固まりが一口位と化し、渡された。この時につくづくこれが戦場の正月というものかと思い知らされた。
この日も、「定期便」大型機の編隊の爆撃はあった。「そうか、彼らにはクリスマスはあるが正月は関係ないのか」と改めて考えさせられた。こんな正月を思い出し乍ら、いま炬燵の中でこれを綴り、来る
べき正月用品を摘まみ喰いし乍らお茶を畷っている。平和が続く日本を有り難いと思う反面、六十年前に祖国のためを思い逝くなられた方々に対し、本当にお気の毒でした心の底で呟きつつ走馬灯の如く脳裏を走り去りゆく、あの戦場を思い浮かべております。ご冥福をお祈り致します。
朝風81号掲載 2005.1月
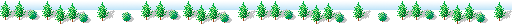
続・硫黄島全滅 60年前を偲ぶ(其2)
横浜市 小沢 政治
全滅の地獄と化す戦場となった初日は、この二月十九日、米軍が南海岸に上陸作戦を開始した日です。
十日前後あたりから、偵察機による情報として、大輸送船団が北上している、進路方向はこの島に来るとは確定できないが北上中との情報を聞かされた。これを聞いた時、遂に来るべき時が釆たのかと、みな覚悟を決めたかのようであった。急迫した様子もなく、慌てる者もいなかった。「陣地につけ」の命令が出て、それからの居処は、住み慣れた居住壕ではなく、狭い陣地内の僅かな空間地に、毛布も敷かずのゴロ寝であった。砲側隊員の一部と通信班員は、陣地に居住ではなかった。これは任務の都合上であると思われた。その内に北上船団は当方に向かって来ることが判然としてきたと聞かされた。いく日かして、朝、目覚めて南海上の遥か水平線を眺めた時、どんよりした天候であったが、その内に黒点が点々と見えてきたと思ったら、次第に大きくなり、船であることがハッキリしてきた。いよいよ釆たナと思った。ここに至るまで、いつものように大型機編隊による定期空襲便は、お休みでは無かった。洋上を埋めつくした船舶は、手前の方が戦艦であった。やがて艦砲射撃が開始された。従来の艦砲と異なり、飛行場のみを狙う砲撃ではなく、至近弾の音は豆が弾けるような音もしている。
この弾雨の中を居住区の炊事班からだと、トリ肉を煮付けた品を飯盆に入れて我が観測陣地に届けてくれた兵士がいた。指揮班には中隊長と少隊長が陣地で任務についていたからであろうか。よくぞ此処まで無事に到達できたものだと感心すると同時に、有難く、二、三片の甘く煮付けたトリ肉を頂いた。今までは乾燥野菜(芋の蔓)か、乾燥南瓜を、粉末正油で煮付けたものが少々で、玄米飯と共にこれが毎日であった。在島中に魚は、イワシの目刺し干物三匹を支給されたのが一回のみであり、このトリ肉の三切れは大ご馳走である。
布陣前に部隊の周辺を歩き廻っていたニワトリが居た。島民の方が本土に引き揚げっる時に、そのまま置いていったものであることは分かっていた。所有者は居なかった。ある時、大木の根元の雨露穴の中に、このニワトリが入り込んでいるのを見つけた。捕らえようとして手を出したら喰いつかれた。動かない。出ようとしない。逃げ出さないのである。それは卵を抱えている、温めていると判断した。分隊に戻り円匙(シャベル)を持ち出し、これで押えておいて腹の下を見たら卵が沢山ある。これはよい物を見つけたと、内心は大喜びであった。全部ポケットに入れて、分隊に戻り、農家出身の先任に見せたら一ケ割って見ていて、「これはダメだ。雛(ヒナ)になっている。食べられない。戻しておいた方がよい」と云う。残念だが仕方がない。元に戻しておいた。これが後日になり、親ドリが先頭を歩きヒナドリは縦一
列になって、ジャングルの中に入って行く一行を見た。一家のお出掛けだな、と眺めていた。それきり姿は見なかった。この飯盆内の肉は、あのご一家の肉であることは、食べた後で気がついた。木の技に止まるメジロを、丸太棒を振り上げて、叩き落とし、食べたことを思い出した。
こんなことを思い出している時でも、上空は艦砲弾と小型爆撃機の編隊が、沖の方から飛来し、島の上に釆てから分散、一機ずつ前方の上陸予定地の前方に当たる林の木々を瑞の方から、一株ずつ根元を狙い爆撃、命中すると根元の方が上向きになり倒れる。林はやがて原と化した。頂には編隊も飛来してこなくなった。林は上陸作戦には、障害物だったのか、それとも、陣地があると推測したのか、一兵士の私には今でも判らない。
二月十六日から始めた艦砲射撃は二日でやめて、三日目からは朝から上陸作戦の如き、艦船の動きがあった。後で米軍の戦記を読むと、掃海作戦であったとか。これを見欺かれた日本軍側は、今まで沈黙していた海軍の砲陣地、摺鉢山の麓と東南海岸の各砲は一斉に発砲した。緩慢に行動していた艦船は大慌てに、沖の方へと引き上げて行った。この陸地からの砲撃で砲台(陣地)の所在が米側の知るところとなり、沖にある艦船からの攻撃が集中して、全滅に近い損害を受けてしまった。この時の摺鉢山は砲撃の地煙で、姿が見えない程であった。夜間でも砲撃をやっていた。あそこに居る部隊の方は生きていないであろうと思はれた。
二月十九日の上陸作戦の時まで艦砲撃は全島に及んだ。空母艦は見えなかったが、沖の上空で編隊の帰艦絶と、飛来する組の交替もよく見えた。艦砲も、食事時刻らしき時にはピクリと止み、静けさが戻る。この静けさの中から、陸地では友軍の何やらの声と音が聞こえて来た。艦砲射撃が始まると、村部落の鎮守の森でお祭りの太鼓が乱打されているように聞こえてくる。海上面は見えず、艦船と輸送船で埋めつくされていた。夜は海も暗いが、夜間戦闘中、気がついたが、夜でも灯を落とさず、墟々と輝くように碇泊している二隻を見た。病院船であろうと思はれた。
傷つけば病院船に運ばれる米軍兵と壕の中で唸っていて、手当ても十分にしてもらえぬ日本兵。勝ち戦さと、負け戦さのこの差、これが玉砕という名のつく戦争で会った。後方に艦船群のついている米軍、それも上陸の時は、煙幕を張り、先発隊はやって来た。沖の大型艦船の間から湧き出てきたのではないかと思われる程の無数の小型上陸用舟艇群である。一斉に白波をかき立て、水際に向かってやってくる。見事というか、壮観というのか、一っ時、報告も忘れて、見入ってしまった。煙幕の薄れた頓には、舟艇は到達していた。艇首から兵員が飛び出して来ていた。砂地なので足元がもぐるらしく、走れぬらしい。ノソリ、ノソリと歩いているように見えた。艇によっては固まって一団となり、上陸くしてくるのもあった。暫くしてから車両か戦車らしきものが、上がって来る。これは東に向かうものと、摺鉢山の麓に向かうものとあり、こちらに向かって直進して来るのは砲台鏡(眼鏡)には入らなかった。この頃には友軍の各砲列の砲弾も猛烈に弾着して、砂煙りを上げていた。それでも上陸の軍団は続いていた。観測兵としての私は超多忙であった。観測に気をとられ、報告量が少ないと叱られた。
持てる弾を撃ち早くせば、後の補給の無い守備の我が軍は、食糧も水も絶対量が大不足のこちらと、撤退跡の陣地には、缶詰其他食糧が放置してある米軍である。単発銃で射撃の日本軍、それも全員には渡らず、腰だめで連射してくる相手には抗し切れない。万歳突撃だけが最後の武器では勝てなかった。今、考えてみるに、あの作戦で勝利して島を守り抜いても、太平洋戦争には勝てなかったと思われる。
一途に祖国のためと覚悟し、死んで逝かれた方々のご冥福を衷心よりお祈り申し上げます。
朝風82号掲載 2005.2月

続.硫黄島全滅六十年前を偲ぶ(其3)
横浜市 小沢 政治
記述は戦闘の実相と相違
公刊戦史と一般の出版物、戦記物等の本に出ている、第二旅団は、昭和20年3月8日夜半、米軍に対し総反撃を敢行して全滅とありますが、南地区の海軍部隊約八〇〇名、陸軍部隊では一部に中止命令の届かなかった部隊では敢行されたと聞いております。
三月初旬、旅団長千田少将は3月8日18時を期し、南地区の各残残存部隊に、最後の総攻撃敢行を下達したが、3月7日、第一〇九師団司令部より、攻撃を思いとどまりあくまで持久の、説得電命を受け、次に北進して師団司令部に合流せよ、の命令を受信、これにより3月13日夜、神山海岸台上・レモン軍畑に集合となりました。
旅団長以下の救出作戦
玉名山地区にあった旅団司令部は、壕内に閉塞された中迫撃第三大隊に救出命令が来て、各中隊等から約20名の決死救出隊が編成され、3月9日夜半、重囲を突破して救出に成功、大隊壕群一帯に収容できた。
近接の白兵戦
3月10日から12日まで中迫撃壕台上の西地区に米軍が来襲、壮絶な接近白兵戦闘を交え撃退した。13日は敵の攻撃は無かった。合流のための北進夜行軍。
同日夜に入り、旅団長以下レモン草畑に集合、南地区の生き残り残存兵で約四五〇名と云はれております。夜半に出発。東、海岸沿い辺りで夜明け近くとなり、自然洞穴又は、壕跡等に入る。同日夕暮れに再び夜行軍で、少し内陸側を進行、あとで知ったが、この時、三分進に移行していたとか。後続の兵員の少なくなっていたことには、気が立っていた。
我が中隊は内陸側より第一層目崖上を前進、夜明け前に崖下の洞穴や壕口に分散して入る。(この時、海岸方向の第二層目と、第三層目崖上や崖下に旅団主力や部隊が分散して入壕していたとは知る由も無かった。ここは温泉浜丘の台上とのこと)
明るくなった頃、米軍が来襲。壕口前の小広場や、崖上から攻撃され、小隊長戦死をはじめ相当な損害が出た。
夕暮れとなり、米軍は引き上げて行った。暗くなり生き残り兵が整列。道案内兵を連れた中隊長が先頭になり出発す。暗夜の中を、砲撃跡の瓦礫の多いジャングル跡らしき所を進む。やがて案内兵が「ここの土手の坂の下が目的の師団壕である」と中隊長に告げる。小休止の命令が出た。
再び出発命令で歩き出して数分。周囲の丘より一斉射撃を喰う。雨の如く来る弾を、近くの大きめの独立岩石の周囲を巡るようにして除けていた私は、一旦射撃が中断した間を狙い、側方の雑木の散在する原のような所に飛び込む。弾を追って来なかった。
前方に小さな豆灯が見えたので、目的の師団壕から洩れてくる灯と思い込み近付いて行ったら、それは米軍の戦車群であった。逃げたが追って来た。夢中で走りに走った。崖の端に釆ていた。銃床で岩石を砕き乍ら、一歩ずつ崖璧を背にして降りにかかった。戦車は近くまで来ていたが去って行った。元に戻りたいが、この姿勢では、戻りようがない。
自決を覚悟して、大切な銃を投げた。月の光で真下の前方は、砂浜に打ち寄せる渚で、白波が糸の如く見えた。
これから先の敗残兵生活は、既に『朝風』誌に投稿した通り。
旅団長の自決
温泉浜丘の台上の各洞穴や壕口に入っていた兵員も全滅に近く、旅団長は壕内にて自決された。
壕外に鉄帽で土を掘り埋葬したと証言する人がおります。北進部隊の尖兵長、将校一名、兵一名が師団壕に辛うじて到達できて報告。師団長は最も信頼する千田少将以下混成第二旅団の戦況に鑑み、もはや万策冬き、最期を飾る兵団総攻撃を決意したと云われている。
三月十七日は命日
師団壕内では、本土にお別れ電文を打ち、無線機を破壊し、出壕したのがこの日であり、全島の殆どの将兵の死をこの日にしたということを、開戦近くのある日、本土に公用で飛んだ兵団の小元参謀が、戦後復員局で硫黄島関係の事務を務め、この日にしたと何かの本に青いてあったのを覚えております。
朝風84号掲載 2005.4月号

生き地獄さながらの彷徨三ケ月(上)ミンダナオ島のジャングル
谷口 末廣
(平成三年十二月末日記)
はじめに
第二二三飛行場大隊での思い出はつきないが、なかでも忘れることの出来ないのは、肝心な食糧が欠乏し、大隊が止むを得ず少人数単位に分散した昭和二〇年六月下旬以降の思い出である。私は六人の部下(戦友)と共に、大隊との連絡を絶たれたまま、飢と病魔におそわれながら、山岳奥地のジャングルを彷徨し、同年九月下旬に投降したのであるが、この三ケ月間にわたる餓死線上の彷徨は、正に生き地獄そのものであった。以下にその一端を書いてみたいと思う。
分散直後の惨劇
大隊が分散した直後の二~三日は、各班比較的近い所を彷徨していた。分散して二日目の夜明け、わが班の近くに野宿していた同じ中隊の後藤軍曹が、手榴弾を抱き、大きな炸裂音と共に自決した。
私より年長で温厚な人であったが、飢餓の苦しさに耐えかね、敢て死を選んでしまった彼の心中如何にかと、泣けてしまった。
その翌日、ジャングルの中で遇然出会った上田伍長から、同じ中隊のN曹長が兵四~五名と共に、大隊保管の食糧を襲撃し、警備している将校と兵を殺害し、乾パンを奪い逃亡したと聞き、骨肉相食むそんな馬鹿なことがと驚愕、言葉も出なかった。(復員後N曹長でなくS兵長だったと聞く。)
分散直後のこの惨劇に、私も班員も大きなショックを受け、食糧のないこれからに大きな不安を抱いた。そこで私は皆んなに、如何に飢餓状態におち入ろうとも、理性を失なわず生き抜かねばならない、そのためには肉親の情をもって結束し、助け合って行くより外に道はない。これからは軍曹も二等兵もない、皆んな家族として助け合っていこうと話し、約束をした。そして一日も早く畑を見つけようと南の方向を目ざし、山並みに潜入していった。それ以後、わが班は大隊の戦友と全く出会うことが無く、孤独な彷徨を続けることになった。潜入の方角を間違えたのだろうか、出会ったのは日本兵の屍と豹兵団の小集団三組だけであった。
日本兵との恐るべき出会い
日本兵と最初に出会ったのは、分散してから二〇日余り経った頃であった。道の脇に五~六人が輪になってしゃがんでいた。久し振りに日本兵に会う懐しさと、畑の有無が聞けるかも知れないという期待感をもって近づいて行った。輪の中を覗いてみると虫の息の兵が倒れており、その爪を剥がそうとしていた。
「まだ生きているではないか」とたしなめるようにいうと、「ここまで連れて来たがもう限界です。どうせ死ぬほかないので、せめて遺骨代りに持ち帰ってやりたいと思って」といった。私には次ぎの言葉が出なかった。倒れている兵には聞こえているのかいないのか、剥がされる痛さを感じているのかいないのか、目頭に小さな涙の玉があった。これも極限状態における戦友愛なのかも知れないが、剥がすも地獄、剥がされるも地獄。この辺に畑は無いということで、吾々は少しでも先にとそこを去った。
二回目の出会いはそれから二週間位い経った八月三~四日頃であった。吾々は殆どの者が杖を頼りにしか歩けないほど衰弱し、疲労していた。これまで二回畑に出会ったが、何れも先行の日本兵が収奪したあとで、トーモロコシの茎とか、掘り起こされ干からびたさつま芋の蔓しか残っていなかった。しかしそれが吾々には貴重であった、トカゲとか蛇のように逃げ足の早いものは捕獲できなくなり、蛙を捕えると大喜びする状態であった。
それどころか、置き去りにされ野たれ死にした日本兵の屍に出会うと、何か食べ残した物は無いかと雑嚢や背負袋を掻き回すほど飢えていた。思わぬ残し物に助けられたり、破れた靴を交換したり、死人に物を献ずるどころか、逆に屍から物を戴くという状態になっていた。
誰だったか一人が、おい日本兵がいる、といった。少し小高くなった尾根のようなところの木の根元で、三人が飯盒を抱えて何か食べている。あの向側に畑があるのかなと期待しながら力を振り絞り、這うようにして近づいていった。「貴様等は何部隊か」と先方から問いかけて来た。吾々の部隊名をいい、この辺に畑があるか、君達は何部隊か、本隊はどの辺にいるのか、などいろいろ聞いてみたが肝心な畑については、この辺には無いもう少し先きに行けばあるだろうといった。
吾々はがっかりした。そして一人が、吾々は昨日から何も食べていない、この通り餓死寸前だが、君達は食糧を持っていて羨ましいよ、と、少し分けてくれないかといわんばかりにいった。すると豹兵団の歩兵だといった三人は小声で何か話していたが、中央の兵が「そうか、昨日から何も食っていないのか、少しだが分けてやろう」といった。吾々は地獄で仏に会ったような気持ちになり、「有難う恩に着るよ」といって、いざりながら彼等に近付いた。肉の臭いに喉が鳴った。野草と肉の煮込みを中盒に分けてくれた。久し振りに口にする肉、噛みしめるいとまもなく喉を通り越してしまった。
何の肉か、大トカゲ、猿、それとも鼠かと聞いたが、彼等はうす笑いを浮べながら「何でもいいじゃないか」と敢えて教えようとしなかった。吾々は礼をいって歩きだした。三人の大きな笑い声が後ろをおっかけてきた。
暫く進むと道が二つに別れ、一つが浅い谷の方向に通じていた。小川があるかも知れん、水を飲もうと降りていった。谷川が見え近づいて吃驚仰天、飯盒炊飯の跡がありその側に足の肉を削がれた日本兵の死体があった。辺りには血がどす黒くしみ込んでいた。一人が声を震わせながら「こん畜生、奴等だな、叩き延ばしてやろう」といきり立った。皆んな這うようにして元の通に戻った。そして二~三人が彼等の方に歩き出した。
「おい待て、彼等は銃をもっていた。逆に血祭りにされたら大変だ。」と止めた。歩きながら、若し彼等三人の仕業だとしたら吾々もその肉を……と、再び地獄に呼び戻され吐き出したい気持ちになった。
狂鬼化した三人と餓死寸前の六人、戦争とは一体何なんだろぅか。
(つづく)
朝風88号掲載 2005.8月号
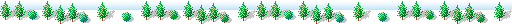
生き地獄さながらの彷徨三ケ月(下)ミンダナオ島のジャングル
谷口 末廣
(平成三年十二月末日記)
狂鬼の兵に出会ってから一〇日ほど過ぎたが、畑にも日本兵にも出会わなかった。最も衰弱のひどい杉山君が死んで早く楽になりたいといいだした 「馬鹿いうな、奥さんや子供のことを思い出せ」と励ました。しかし皆んなからも、班長は、神は絶対に吾々一家を見殺しにはされない、もう一日もう一日と引っ張ってきたが、もう限界だ、畑探がしを続けているうちに野たれ死にしてしまうより、山を降りて米軍と戦い戦死した方がましだといいだした。私も迷った。
よし、明日もう一日探して見つからなかったら戦死の道を選ぼうといって寝た。
翌日、その日も遂に見つからないまま夕暮を迎えた。突然、その日の先頭を歩いていた水上君が「あっ〃やられている」と叫んだ、見ると四肢をバラバラにされた日本兵、私は、むごたらしい死体に目をそむけながら、これは土民かゲリラの仕業に違いない、とすればこの近くに畑がある筈だと連想した。
夜、約束を破って済まんが、明日もう一日だけ探して見ようじゃないかと頼んだ。皆んなから、またですか。これで六回目、本当に明日だけですよと念を押された。
眠れないまま夜が明けた、今日は昨日と反対側の斜面を探してみることにした。太陽が頭上近くになった頃、先頭を歩いてくれていた前田君が、班長、畑のようだといって指さした。見ると木の問隠れに青いものが見える。皆んな一斉に畑だ〃と嬉しさの声をあげた。私は心の中で、やっぱり神は見捨てなかったと喜び、奇跡を感じた。
皆んな藤の大きなトゲに服をとられながら這うようにして畑を目ざした。一時間半位で着いた。青青と繁ったさつま芋畑で、半分程は掘られていたが、半分残っていた。皆んなは着くやいなや掘り出した。誰れの目にも嬉し涙が浮んでいた、掘った芋の土を服でぬぐい、そのまま餓鬼のようにむしゃぶり食った。満足そうな笑顔と笑い声が溢れだした。
突然、「誰だ〃この畑は吾々のものだ、直ぐ出て行け、出て行かないと射ち殺すぞ」と大きな怒声。思わず芋蔓の問に伏せた。頭をあげて見ると、畑の向側に一〇名位いの兵がおり、三人が此方に近づいて来た。そのうちの一人は少尉だった。私は挙牛の礼をし「飛行場大隊の者でご覧の通り餓死寸前、一ケ月半振りに漸くこの畑に出会い、これで助かったと喜んでいるところです。当分この畑において下さい。」と哀願した。少尉は「君達に食べられると部下の食糧がそれだけ減る。君達は君達で自活できる畑を探がせ」 「それでは一週間お願いします」 「馬鹿いうな」の押問答、同じ日本軍ではないかと腹の中は煮え繰り返ったが、結局、明日の正午までに出るようにといって去った。
私は皆んなに「聞いての通りだ、軍隊は階級がものをいう、今晩と明日の午前中に腹の中を先づ一杯にし、彼等に気付かれないように背負袋に出来るだけ詰め込んで出よう」といった。このようにして待望の芋畑を見つけた喜びは、一瞬にして泡のように吹き飛んでしまった。
翌日、出発しようと思ったが、背負袋の芋が重くてとても歩けない。よし、ジャングルの中に隠くしておいて、後で取りにこようと、ジャングルの中に持ち出したり、場所の目印をつけたりしているうちに昼になってしまった。
少尉が督促に来た。その時、久し振りに敵の偵察機が上空を旋回しだした。発見されないようにジャングルの中に身をひそめ様子を伺った。何時もエンジンを止めて旋回するのに堂々と、しかも低空で旋回し、やがて芋畑めがけて紙片をばら撒き去った。拾って見ると、日本の降伏と投降勧告を書いた、こ存じの伝単であった。
日本の全面降伏など誰も信じなかった。これは敵さんの苦しまざれの謀略で、騙されてなるかと、逆に元気づいていた。私は本当かも知れないと思ったが、口には出せなかった。少尉にお礼をいって未練の芋畑を出ていった。(投降後、芋畑に着いた日が八月十五日で、出ていった目が八月十六日だったとわかった。
その後のこと
米軍機からのビラを見てから投降するまでの一ケ月余りの問にも色々なことがあった。
投降を頑なに拒否するもの、柔軟な考えを持つもの、成り行き委せのもの、人の心はみな違う。しかし私には六人全員を無事帰還させる責任があった。どのように説得したかを書くと紙数が余りにもオーバーするので割愛するが、九月末日、揃って投降した。唯残念であったのは、収容所の時も復員の時期も夫々別々であり、復員後も住所不明で、あらゆる手をつくし漸く住所が判明した時は、既に時おそく水上さんが昭和五二年、吉良さんと杉山さんが同五六年、前田さんが同五八年に不帰の人となられていた。(大東さんは今なお所在不明)誠に残念至極、謹しんでご冥福をお祈りすると共に、ご遺族の方々の、こ多幸をお祈りし、思い出の筆をおく。 合掌
朝風89号掲載 2005.9月号

餓(ガ)島の生き残り 斃れた兵の胃の内容物を食う
北茨城市 石森 武男
《渡辺氏が言った「本当に食ったんだ」と。》
『朝風』八・九月号に載った谷口さんの“彷徨三ケ月”を拝読して、友人の壮絶な話を思い起こした。
私は某炭鉱の労働組合で会計監査をしていた時のこと。抗外側から私、坑内側からは元陸軍軍曹の渡辺久男氏が出て、二人で監査作業を行った。作業は私の家と彼の家と交互に使用して、作業を終えて息抜きの晩酌をやった。
当然、話題は戦争の話。私はソ連抑留の話。渡辺氏はガダルカナルの壮絶な体験談である。彼はガダルカナルの数少ない生き残りで、上陸後、食糧の補給はなく、兵隊は飢え苦しんだ。上官は戦死していないし、渡辺が指揮をとった。
「米軍が上陸して兵糧攻めにされた。我が壕には生き残りが数人。食糧は皆無。身辺の草や木の皮まで食った」
彼の話は続く。
「敵弾に斃れた兵の胃袋を割っさばいて、消化してない内容物をそのまま食った!! そんなのは序の口だ。それからだよ!!」
「銃の音もしなくなった。何日も食う物がないから、水ばかり飲んで生きていた。敵を前に、その水も手にするのは命がけだった」
「夜の露を舐めて渇きをいやし、瓦礫に溜まった雨水を飲んで、空腹にふらふらしながら、食う物を求めて徘徊した」
「ある時、部下の一人が徘徊するうちに、『近くにいた生存者から、肉を分けて貰った』と言って持ってきた」
「部下は『何の肉だか言わなかった』と言っていた」
「とにかく火を起こして煙が立たないようにして飯盒で煮て食った」
「空腹だったせいか、とてもうまい肉だった」
「それに味をしめて、次の日も貰いに行った」
「何の肉か相手はやはり教えなかった、当方からしつこく追及されてやっと白状した」
「いまどき、何の肉があるって言うんだ!!… 考えてもみろよ!! だいたい想像できるだろう。お前らだって飢え死にしたくないだろう。誰も生きる為だ。神も仏も見ているさ!!」
「その男は、殺害を否定しようと必死だった。男は、『何かの本で読んだ事を実行しただけだ』と強気なことを言っていた」
「弱って死にそうな奴を拳銃で撃つ。息の根が止まるのを待って一斉に肉の塊を切り取る。そしたら次の標的を選んでおくのだ」
「負傷者でも抵抗する奴は殺らない。でも、標的がなくなると狙われた。抵抗できない弱っている奴ばかり襲われた」
「顔見知りの者が餌食になった時は、さすがに戸惑った」
「最後の部下が出て行ったきり、戻ってこなかった」
「狙われるのは自分だけになった」
渡辺氏はその恐怖をこう語った。
「いつ襲われるか分からないから、夜も昼も眠れなかった。そして幻覚症状に陥って死ぬのを待つようになった頃、米軍に拘束されて生き延びた」
このような強烈な話が私の耳に焼き付いている。
「でも人間の肉ってすっぱいとか、にがいとか昔から聞いていたが、あれはウソだ」と語った渡辺久男氏が他界して久しい。
了
朝風91号掲載 2005.11月号

弱兵戦記(10)
ほし静岡県 秋元 実
わたしは四年五か月軍隊にいましたが、その間、上官から、戦争の現状や所属する師団各部隊の配置、作戦の目的、内地の状況、米英支軍の兵力装備・戦術、現地人の生活・風習・動向などについて、いっさい、教えられたことはありません。
要するに、日本の軍隊の明治以来の方針は、「兵隊には、何も教える必要はない。兵隊は、ただ、上官の命令・指示に従って、忠実に動くロボットであればいい」ということでありました。
わたしたちは、新聞もラジオもなく、いっさいの情報から遮断された遠い南方の孤島に何年も置かれながら、師団司令部や部隊の上官から何も教えられることなく、ただ、どこからか流れてくるうわさを頼りに、自分たちの置かれている状況を辛うじて判断して、生き続けたのでありました。
☆
わたしたちは、ビルマを占領し、ビルマに駐屯しながら、ビルマ語の教育を受けたことなく、ティモール島に上陸し、そこに二年九か月いて、ティモール人の言語のマレー語やテトン語を教えられたことがありません。
日本軍のやったことは、ただ、占領地区の住民に、日本語で日本人の信条と文化、生活様式を強制したことだけでありました。
☆
つんぼ桟敷におかれた外征部隊についてもうひとつ言えば、日本軍には、作戦地域の正確な地図がありませんでした。
たとえば、あの惨憺たる敗戦をしたガダルカナルに地図かなく、例の川口部隊の悲劇は、そこから生まれました。
一木支隊の壊滅後、川口清健少将の指揮する、歩兵五個大隊・兵力五千の川口支隊は、地図のないジャングルの中で道に迷い、作戦開始時刻に間に合わなくて、戦史に巨大な汚点を残したのでありました。わたしが三年近くいた小スンダ列島のティモール島にも、地図らしいものがなく、いつか戦友会のとき、中隊長の後藤大尉に、米軍が来ていざ戦闘になったらどうするつもりだったのですかと尋ねたら、苦笑いするだけでした。
☆
東アジア諸国民を白人の不当な支配から解放して、みんなで仲良く暮らす大東亜共栄圏を作るんだなどとカッコイイことを言いながら、異国を軍靴で踏み荒らした日本軍は、大陸と南方諸島のいたるところで、非戦闘員たる地域住民の虐殺事件を引きおこしましたが、その最大なものは、昭和十二年末の南京事件で、その次は、シンガポール占領時の華僑虐殺事件です。
☆
昭和十七年五月、ビルマへ行く途中シンガポールへ上陸して、郊外の兵端宿舎で輸送船を待っているとき、わたしたち新兵は、一度だけ、引率の見習士官に外出を許されて、戦闘終了後の街へ出かけたことがあります。
わたしは、異国の文化や風景に異常な好奇心を持つ文学青年でしたから、その貴重な外出時、中国風に原色ゆたかな華僑の衝をさまよったり、インド人が住む裏町を覗いてみたりしたのでしたが、そのとき、わたしがふしぎに思ったことは、日本兵のわたしを見る街の住民たちの目に、なにかおびえたような、暗い影があったことでした。
人のいいわたしは、そのとき、日本軍は、植民地シンガポ-ルをイギリスの圧政から「解放」した救世主だと信じていたので、市民がおびえた日でわたしを見る理由がわからなかったのでした。
☆
国民は知らなかったけれど、太平洋戦争開始直後、山下奉文中将指揮下の日本軍は、マレー及びシンガポールで、実に大量の住民と、降伏したイギリス兵に対して、情け無用の虐殺をやっていたのでありました。
当時、日本軍将兵は、戦争のやり方や捕虜及び非戦闘員の異国人の処遇について、国際的なルールのあることなど、問題にしていませんでした。
そして、さらに、そのころの日本人には、中国人を 「チャンコロ」と呼び欧米人を「毛唐」と呼んだり、植民地の朝鮮や台湾の人々を、被征服者として下に見たりする、夜郎自大のうぬぼれがありました。
特に、昭和十二年の本格的戦争開始以来、日本人には、中国人を「敵」と見る固定観念ができて、そうした日本の戦闘部隊によって、中国人であるがゆえに「スパイ」と見られ、「反日分子」 「抗日思想者」と見られた無実の華僑などが、シンガポール占領以前、すでに、マレー半島の二か月に近い進撃の間、捕虜になったイギリス兵同様、日本軍によって、多数虐殺されているのです。
わたしの所有する資料によれば、その数は、マレ-半島北西部のペナン島で約二千人、半島のマラッカで約三千人、半島南端のジョホールパルで、二千人以上とされていますが、その他、いくつかのマレー人部落が、日本兵によって、虐殺的被害を受けているということです。
☆
二月十五日、シンガポールを占領した第二十五軍は、英軍捕虜を管理するとともに、敵視している華僑の粛清を始めました。「粛清」とは、怪しいと思われる人物を、死刑によって抹殺することです。
当時、近衛・第五・第十八の各師団から兵力を出させて組織した「シンガボ-ル警備隊」の隊長になった歩兵第九旅団長河村参郎少将は、二月十八日、第二十五軍司令部から、「敵性と断じたものは、即刻厳重処分せよ」という指示を受けると、大石正幸中佐の指揮する第二野戦憲兵隊と協同して、短期間に、華僑の粛清を実施しました。
☆
当時のシンガポールの市民は約八十万人で、そのうち約六十万人が華僑と見られていましたが、警備隊と憲兵隊は、考えられる限りの残酷非道のやりかたで、特に、成人男子の華僑を根こそぎ検束尋問し、怪しいと見れば即刻トラックに乗せて連行して、山上や海岸に並べて機関銃で撃ち殺したり、数珠繋ぎにして海中に突き落として、溺死させたりしました。
この事件は、戦後、極東国際軍事裁判で厳しく審議され、南京事件などとともに、大きな国際間題となりました。
このとき、不法に殺された華僑は、あるいは五千人と言われ、あるいは一万人と言われて定説はないけれど、わたしの調べた範囲では、一万人前後という説が多かったように思います。
☆
戦後、イギリス軍の管理下で行なわれた戦犯裁判で、警備隊長の河村少将と憲兵隊長の大石中佐、憲兵の十数人が、死刑となり、他に、警備隊の将校五名が、終身刑となりました。
☆
このシンガポールの華僑虐殺事件については、たくさんある関係図書の中で、当時、読売新聞の従軍記者として現地にいた小俣行雄さんの著書「続.侵掠-太平洋戦争従軍記者の証言1」(徳間書店)に、一番詳しく具体的な記述がありますが、わたしは、それを読むたびに、かつてわたしが所属した旧日本軍の、あの悪名高いドイツ軍に劣らない残酷な体質を感じて、激しく臓腑が痛むのです。
☆
さらに、もうひとつの感想。 戦後、シンガポールは気軽に行ける観光地となり、平成十八年の現在までに、おそらく合計何百万という日本人が押しかけたのではないかと思うのですが、例えば、虐殺された華僑の子孫が、そうしたチャラチャラした日本人の観光客を見て何を感じたか、それを思うと、戦中派のわたしには、なにか、いたたまれない思いがしてくるのです。
☆
軍隊には「脱柵」という言葉があります。宿舎の柵を越えて禁止された場所へ行くことで、見つかればもちろん厳しく処罰されます。
しかし、そのとき、わたしは、軍隊以外の人間の世界、軍人以外の普通の人問に飢えていました。
夜になると、この高台の住宅地にチラホラともる灯の群れを見ると、わたしは、人間の肌を感じさせるその暖かさに抵抗できませんでした。
ある日の夕食後、わたしは脱柵して、宿舎の近くにある、西洋人の閑静な住宅地を歩きました。そこには、童話の本の挿絵に書かれているようなスマートな洋館が、白ペンキで塗られた低い柵で囲まれた敷地の中、前庭に芝生を置いて立ち並んでいいます。
舗装路を下って行くと、一軒の二階建ての満洒な家から漏れてくるピアノのメロディが、耳を捕らえました。それは、軽快なスイング・ジャズでした。音楽にも飢えていたわたしは、思い切って玄関に立つと、呼びリンを押しました。
ピアノの音がやみ、だれかが玄関に近づく気配かしました。ドアが開き、中年の白人女性が、疑い深い目で、わたしを見ました。わたしは一礼すると、たどたどしく英語の単語を並べて、日本の兵隊だが、ピアノのスイング・ジャズに惑かれてここまで来てしまったと事情を述べ、できれば、二、三曲聞かせてほしい・・・とつけ加えました。
長身の女の表情が和らぐと、「どうぞ」と言いました。
招き入れられた部屋は応接間風で、絨毯を敷き、ソファを並べてありました。貧しい日本の若者のわたしにとって、この豪華なインテリアは、もう夢のようでした。
女は、コーヒーを入れてくれ、その異国風の匂いが、また田舎者のわたしの肺腑に染みました。
女はわたしに心を許したらしく、やはりコーヒーに口をつけながら、ぽつりぽつり話し始めました。
自分は、ユダヤ人だということ。もう永いこと、シンガポールに住んでいること。二年前母を亡くして、今、宝石商の父親と十五歳の妹と三人で暮らしていること。今夜、父親は商用で出かけていて家にいないこと。
わたしは、異国の女性が英語で話すそうした身の上話を、ソファに身を沈めながら、なにか、夢見る思いで聞きました。
黒い髪のこの中年の独身女性は美しくなかったけれど、やはり、異性の強い体臭を持ち、その瞳に、なにか深い色彩がありました。
女は、話し続けました。シンガポール島を揺さぶった戦いの日々、震えながらジャズのレコードを聴いていたこと。妹と音楽を聴いていると、ふしぎに心が落ち着いてきたこと。
☆
女は立ち上がってピアノの前に座ると、軽々とジャズの小曲をいくつか弾き、わたしは、それに陶酔しました。三島の中部第十部隊に閉じ込められ、メシより好きな音楽から遠ざけられてから、初めて聴く新鮮なサウンドとメロディです。
やがて、二階から、ひとりの少女が降りてきました。これも黒い髪とスラリとした肢体を持ち、しかもかなりの美少女で、わたしは、反射的に立ち上がっていました。
中年女は、「妹よ」と言って少女を紹介し、ピアノでなにか弾くように促しました。少女は素直にピアノに向かい、指を鍵盤に滑らしました。
わたしは、あっと思いました。少女が弾き始めたのは、なんと、童謡の「夕焼け小焼け」だったのです。
伴奏をつけられ、さまざまに変奏されて展開してゆく故国のメロディは、熱帯用野戦服を着てソファ-に座っているわたしの全身に染み、わたしの魂を揺さぶったのでありました。
☆
軍隊は戦争する集団で、兵隊がそこで唄わされるのは、弱兵の士気を鼓舞する、明治以来の勇ましい軍歌です。
屯営や野外演習で軍歌を唄わされてきたわたしが、思いがけず、シンガポールで巡り会ったのが、異国の少女がピアノで弾く、郷愁の童謡「夕焼け小焼け」でありました。
そして、その夜、ユダヤ人母娘の奏でるピアノによって、僅かに、平和愛好文学青年の本姓を回復したわたしは、その三日後、六十五名の戦友たちと中古の輸送船に乗せられ、マラッカ海峡を北上して、野戦重砲兵第三連隊が駐屯する、ビルマのラングーンを目指すことになるのでした。(つづく)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
谷田川・註
音楽や文学を愛し、何よりも人間らしい感情を必死に守りつづけようとする秋元さんを感じつづけて読みました。
そして「軍隊は戦争をする集団」という「実感」を、戦場へ行って体験する前にわかって欲しいです。
それが私たちの運動です。より端的に言うならば、「軍隊は人を殺せる人間につくり変えるところ」です。
ベトナム戦争のとき、一人の黒人兵が、「兄弟よ、故国へ帰ろう。これ以上人を殺すことに神経マヒしないうちに」と呼び掛け、世界の隅々迄大きく報道されました。殺すことへの麻痺の第一歩は「憎しみ」です。
その「一歩」の背中を押したがるのはいつもマスコミと、ある種の政治家です。
朝風94号掲載 2006.2月号

私の戦争体験
元従軍カメラマン 潮田 三代治
◆航空母艦「瑞鶴」
瑞鶴に乗船した日は一八年の何月だったか?
日本には開戦時、八~九隻の航空母艦があったが、ミッドウェー海戦で、アメリカが、手ぐすね引いて待っていた海戦だっただけに、殆どの空母が、被害をうけた。
この海戦で、虎の子だった『赤城』と『加賀』は沈没した。無傷だったのは『瑞鶴』だけで、瑞鶴と同格の、翔鶴はじめ他の母艦は、飛行甲板等に大なり小なりの損傷を受け、連合艦隊としては大変な損害をうけた。
瑞鶴に乗艦した報道班員は、私一人だったので、記事を書き、写真を撮り、映画を撮り、と一人三役の仕事をやることになった。
瑞鶴は、排水量三万トン近く、飛行甲板300m、搭載機は、戦闘機、艦攻(艦上攻撃機)艦爆(艦上爆撃機)が各30数機づつ、合計100機を搭載した。乗員は2500名。
実践になると、全艦に緊張が張りつめる。飛行甲板には、前方、中央、後方の、三カ所にリフトがあり、飛行甲板の下の格納庫から、一機ずつ上がってくる。
発艦する時、『艦爆』は450キロの爆弾一発を抱え、『艦攻』は、魚雷を一発腹に抱え、エンジン全開にして艦を飛び立って行く。
『艦爆』は、目標敵艦の真上から、ほとんど垂直に近い、85度で急降下、爆弾を投下後、全力で操縦桿を手前に引く。引けないと、そのまま敵艦に体当たりして自爆する。
『艦攻』は、波頭すれすれに、水面を這うように目標敵艦の横っ腹めがけて進み、魚雷を目標敵艦の直前で投下する。
作戦により、飛び立った100機が、半分しか帰艦できない事もある。彼らの大半は体当たりして消えていった。攻撃を終わり、各機は母艦に着艦すべく上空を旋回して待つ。最初に隊長が着艦すると、一〇秒間隔で着艦する。
300メートルある飛行甲板のうち、後部、約100mから後方に、五本のワイヤロープが張ってあり、着艦する機は、後輪のそばに下がっている、カギのようなフックを、五本のうちの一本のロープに引っかけて着艦する。高度な技術を必要とした。
空母のパイロットは、陸上で、定着訓練(飛行場に白布を張り、その中に、前輪と後輪を、同時に着輪する三点着陸) の訓練を繰り返してきたベテラン揃いなので、とは言っても、風が強ければ波も高く、飛行甲板は、上下左右に遠慮なく、動く。
最初の、一番機が着艦すると、待機していた整備員がとびだして、フックからロープを外す。リフトで一機づつ、下に降す時間がないので、機を飛行甲板の、最前方に固定する。
固定した機と、五本のワイヤロープの間には、前方に固定した機を守るために、バリケード(ワイヤロープの網)を二か所に立てる。フックがロープ引っかけられなかった時は、バリケードにもろに衝突する。衝突した機は、パイロットを引っ張り出し、機は海中に捨てる。
十秒毎に着艦するので当然失敗者もいる。失敗したパイロットは重傷か、即死するかだが、すぐに看護兵の手に渡る。だから二番機以降の機は、決死の思いで着艦しなければならない。
私は、母艦が全速で走ると、飛行甲板が長くなり、航空母艦の飛行機は、簡単に発艦、着艦できるものと思っていた。この様に壮烈な着艦が繰り返されているとは、乗艦するまで知らなかった。
いくら大きな艦だと言っても、二五〇〇人の集団生活となると、いろんな事が起こる。
海軍では一個分隊が、十四~五名で編成されている。この分隊の中で、人のものを盗むとか、こっそり配給以外の、水を使って、洗濯したとか、悪いことした隊員が、一人でもいると、一個分隊全員が、甲板に整列させられて、〃日本精神注入棒〃と書かれた、樫の木の棒で、隊長が全員の尻を殴る。
私は、暴力を肯定はしないけれど、現在の日本に、どこを捜しても、この〃日本精神注入棒〃はない。入間成長する過程で、一度だけでもこの棒のお世話になる、必要があるのではないかと思う。
ちなみに、水の使用だが、空母に乗艦中の、士官を除く隊員は、赤道直下と言えども、一日に配給される水の量は、食器ほどの器に一杯、一リットルもない水で、歯を磨き、顔を洗い、体を拭く。
現在、米軍空母は、飛行甲板にもう一つの、斜め飛行甲板を備え、二番以降の着艦磯は、失敗しても、バリケードがないから、着艦をやり直すことができる。五〇年前とは言え、どうしてこんな簡単なことが、考えられなかったのであろうか。
◆ガダルカナル島の撤収作戦
『瑞鶴』 に乗船中、ガダルカナル島の、部隊撤収作戦『退却』が始まり、空母『隼鷹』と『瑞鳳』が、撤収部隊を援護のため、出動することになり、自分は『隼鷹』 に乗艦することになった。
『隼鷹』は二四〇〇トンで、開戦時は商船『神原丸』として、建造中だったのが、急遽、空母に改装したもので、十七年五月に竣工、四八機を積んでいた。
ただ、商船構造なので、艦内も隔絶してないし、外側の鉄板が薄く、魚雷が命中すれば、一発で轟沈する儚い運命にあった。敵に発見されれば、真っ先に空母が狙われる。
ガダルカナル島は、九州の124連隊が、守備をしていて、米軍が、海、空ともに完全に制覇されて、日本軍は、数千名の兵隊へ補給が続かず、ほとんどの将兵が餓死し、残る二百名たらずの兵隊も餓死寸前にあった。その為、島の森の中では《想像に絶する残虐事態が展開されていた》。
引き揚げは、夜間に行われたが、足の遅い貨物船は使わず、数隻の駆逐艦を使用した。
『隼鷹』に乗艦した、引き上げ部隊の将校は、辺りを憚って、ポッリ、ポッリ、ガ島の様子を話してくれた。
「いよいよ食べ物がなくなり、動く爬虫類は全部食い尽くした。食べだした頃は、何とか火をつくり、焼いて食べていたが、焼いてるうち人に見つかる為に、見つけるとすぐ生のままたべた。
「戦友が死ぬとすぐに『すまん許してくれ』と手を合わせ、何人かでその遺体を刻んで食べた』と、ガリガリに痩せたこの将校の話と同様、別の生還者が語っている。
(死者は次々骸骨だけになる。だが順番に都合よく死んでくれない。一番弱って死にそうな者が対象になり、無言のうちみんなの目がそこに集る。狙われたら最後、誰かが息の根をとめる同時に一斉にむらがりその肉をむしり取る。まるでサバンナの猛獣と同じだ。
そうした毎日が『誰かに殺られるのでは』と戦々恐々と、夜もろくろく眠れず、島じゅうが修羅場だった)カッコ部分は生還者某軍曹の言です。
引き上げの当日は、引き上げることを、隊員に何も知らせずに、隊長は、『本日、最後の総攻撃を行う。動けない者は、手榴弾で敵と共に自爆するように、動ける者は隊長について来い』と命令した。
そして、隊長にようやく、ついてきた人たちだけが海岸に出て、引き揚げ艦に乗艦した。夜陰に乗じて行われた、撤収作業は、たいした被害もなく無事に終了した。
◆アンダマン島に敵前上陸
昭和一九年一月、空母を降りて、海軍陸戦隊と共に、インド洋のアンダマン島に、敵前上陸した。数隻の駆逐艦から、カッターに乗って上陸してみると、そこには敵らしき姿は、まったく無く、無敵上陸となった。
島に、インドの精神病院があって、ドイツ人のドクターが、たった一人だけ残っていて、鉄格子のはまった病室では、数人の女性患者が、スッポンポンの姿で、我々男性を見て、キャーキャと迎えてくれた。
街の雑貨店に、日本では既に売っていなかった森永ビスケットや、多くの日本商品を売っていた。
つづく
朝風97号掲載 2006年5月号

硫黄島全滅のその後
横浜市 小沢 政治
北地域で包囲された部隊は夜半に全滅。一旦は機関銃の止んだ隙間を抜けて暗い藪の戦場跡、野原らしき中に走り込む。目的の兵隊壕は何処なのか、と腰を低くして歩くうちに、前方の豆灯は、友軍の壕から洩れてくるランプの灯と思い、三人で近づいたところ、米軍の戦車一群であった。これに追はれて夢中で走りに走った。行き止まりは崖の端の上であった。
この時、他の二人はどこへ行ったのか。ここにはいなかった。この崖を下る他に生きる道はない。銃床で足元を砕き乍ら、一歩ずつ降りて行く。
頭上に来ていた戦車が去っても、元に戻る姿勢が、どうやってもとれず、この時、自決を心に決め、まず、大切な銃を投げ捨てた。次に死ぬ気で飛び降りた。
すでに所属部隊は全滅しているのだし、行く所、進むべき所も判らない。戻れば戦車がいるだけである。
今が死ぬ時だと思ったし、生きる術も、闘う術もなし。戦車に対抗する爆薬もなしで、あの時は深く考えなかった。その心の余裕もなかった。
(もう俺も死ぬ機会がきているのだ)と他のことは何も考へていなかった。
暗夜の中、下は打ち寄せる海岸線の白波。水際が白く見えているだけであった。
スーーと下の地面に吸い込まれ行くようであり、頭の中は真白であったとはあの時のことかしら?
奇跡があったのだ
着地点はサラサラした砂山であったため、全身埋まったが、躓きながら這い出せた。どこも痛くない。俺は生きているのだと、気がついた。砂の上を白波の方へと歩いてみた。歩ける。どこも痛くない。怪我もしていないようだ。俺は死んではいない。人間の世に、今は居るのだと思ったら、改めて気持ちが入れ替わった。白波を浴び乍ら歩き出した。
これから独りぼっちの敗残兵生活が始まる。何処を、どのように歩き、出陣前のの壕に、戻ったのか、前半位まできり、思い出せない。後半の行動は頭に残っていないようだ。この出陣前の壕に入り、暮らす内、あるひ、戦利品漁りの米兵に見つかり、連絡したのであろう、討伐隊がやって来た。攻撃を行った。
火炎放射機で焼き出され
手榴弾や発煙筒を投げ込まれ、その内に火炎放射機を吹き込まれたが、空気抜き穴から奇跡的に脱出できた。前方の分隊壕内に飛び込み、戦死者の屍の中に潜り込んだ。そのうちに日中が過ぎ去り、討伐隊は夕暮れに引き揚げて行った。
人情紙風船
壕の外に出たが、行く所もなし、焼け出されたその姿は半焦げの服装で、下半身は火傷の上、裸足である。何一つ持たず、身に付ける物とて何も無いのである。当てどもなく暗い中を海の方へ向かい歩き出した。目的があったわけでもなかった。幻者みたいなものであったかしら。
海に向け歩く内に、谷間の入り口に出た。両側は丘の台地である。その谷底を歩いていたところ、左右所々に、横穴式の洞穴や濠らしき所がある。その穴に人ろうとすると、人り□にどこかの兵が入っている。入れてくれない。
「負傷していないか。食べ物、持っているか。武器、持っているか」と聞く。持っていないことが判ると、「ダメだ」怒鳴り、脅かすだけで入れてはくれない。
海辺の方にと、次々にと進んで行くが、点々と左右にある壕は、何処も同じことを云って入れてはくれない。水際まで来てしまった。東の天空は明るくなってきた。陽が上がれば、米軍陣地より見つかり狙撃されるだけである。仕方なく、渚に打ち上げられている海の芥を冠り、近くの岩陰に身を寄せて、夜のくるのを待つことにした。
この時、同じような運命の持ち主の敗残兵が、近くに来ていて、意気投合、二人は一組となり、足を組み削合わせて水際にて潜む。天空がすっかり明るくなってきた頃、昨夜、歩いてきた谷間の方で、米軍と友軍の撃ち合う銃声が聞こえてきた。初めは双方の銃声であったが、やがては、米軍のみとなる。止んだ。
次の壕が見つかったらしく、少し近くで又、撃ち合いの銃声。やがて米軍の銃声のみとなり、これが次第に近づいて来る。近くの銃声が止んだ時、芥の間から見えた。岩の上に下半身のみが見える米兵の姿が。彼は背を海にして、内陸方面を見ているのである。横に抱えた軽機は、よく手入れがされているらしく、油で光っていた。
奇跡が起きていた。昨夜、あの時、何処かの壕で、親切に入れてくれたならば、今日の私の命は無かったのだ。生と死は紙一重である。あの時は一時、入れてくれないことを恨んだが、人間、何処に生死の分かれがあるか分からないものだ。乞食より哀れな見窄らしい敗残兵の姿と化した戦力にもならぬ者は、助けたくない筈だ。これが究極の戦場の心理というものであろう。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【谷田川・註」
毎日新聞の日曜版に連載された「戦跡巡礼」につぎのような話が載っていたことがある。硫黄島で戦って負傷し、米国の病院に搬送された日本兵が、同室の米兵に「どこで戦って負傷したのだ」と聞かれた。
「硫黄島だ」と答えると、米兵はベッドから飛び降り、直立不動の姿勢をとって敬礼したという。
日本では最悪の恥辱とされる捕虜となった兵に対する礼節に、勝べくして勝った国と、負けるべくして負けた国の差を考えさせられた。そして「硫黄島」と聞いて、敗者に敬礼をおくる勝者の姿の中に、戦いの凄まじさを考えた。
小沢政治さんは、そこで戦い、「玉砕」を生き延びた。「朝風」創刊当時からその体験を綿密に語り続けている。
朝風100号掲載 2006年12月号

忘れじのニューギニア、敗戦六十年目の夏に
町田市 三橋 國民(八十四歳)
ニューギニア戦線で生き残った茂住光雄さんと二人、かつて「白骨街道」と呼ばれた北岸の波打ち際の径を辿っていた。熾烈な戦いの果て、転進中の兵士たちが、この周辺で次々と折り重なるようにして斃れていった悲劇の現場でもある。
しかし、半世紀を過ぎた今は、密林から迫り出している巨樹の幹に、微かに残された銃弾の破片など、僅かな痕跡を目にしただけだった。私の前を歩いていた茂住さんが、斜め前方の空を指さして急に立ち止まった。
「三橋さん、あれはー体何んだろう? ほら、あれだよ!」
約二十メートル先、海沿いに連なるマングローブの濃緑帯の上に、右側から迫り出している密林の大樹が覆い披さるように枝を拡げているのが見える。どうしたわけか、梢の一坪ほどのところは木の葉が全くついていない。
茂住さんが見付けたのは、その何もついていない梢の真ん中にぶらんと下がっている黒くて大きな塊であった。干からびた木の実のようにも見える。素早くウオッチング用の双眼鏡を取りだした。茂住さんが懸命に確かめている。
「驚いたなあ、あの塊はだねぇ、むかし兵隊たちが使っていた『飯盒』だよ……。横っ腹に彫りこんである名前も読めるよ」
渡された双眼鏡で私も覗いてみた。
「……タナカ……、田中って彫ってあるなあ。でも、あんな高いところに飯盒がまたどうして?」私には見当がつかなかった。すると、茂住さんが、「これはねぇ、私の想像だが、たぶん田中という兵士が、ここまでやってきて力が尽きてしまい斃れたんじぁないかな。そして、あの木がまだ若木だった頃の小枝に、空になってしまった自分の飯盒を引っ掛けた……そして、そのまま息絶えた……ということだったんだろうねぇ」
確かに飯盒が木の天辺にまで駆け上がるはずはなかった。力尽き斃れた田中の五体は、やがて打ち寄せる波に漬かり、溶かされていったのだろう。五十年を超えた歳月は、斃れた兵士が最期のさいごまで手離さなかった飯倉を、少しずつ、天空に釣り上げていった・・・。大木の枝は決して飯倉を放そうとはしなかったのだ。田中という若い兵士の『最期の証』を確りと抱きしめてーーー。
茂住さんは、当時の陸軍士官学校出身で、生粋の軍人だった。百五十人の部下を引き連れ輸送の任務につていたが、全兵員をこの地区で失っている。
同じころ私は、別の部隊、高射砲の一兵士として二度目の召集を受けニューギニアに上陸していた。二年が過ぎた敗戦時には、四十人いた分隊員中二人の生き残りになっていた。病魔、事故、戦闘といった臨死体験のあと、四度目にはとうとう瀕死の重傷を負ってしまったが、辛うじて故郷へ帰ることができた。
今回の慰霊行で、茂住さんと私は、次のようなことを密林に住むパプアの人たちから聞かされた。それは、今も密林の中を彷徨っている日本兵の亡霊に、多くの人が出会っているというのである。
私たちが目撃したのなら、過剰意識による幻覚ということにもなる。しかし、二十代の戦争を全く知らないパプアの人たちに、当時の日本兵の写真を見てもらうと、「そうそう! これと同じ姿の兵士が彷徨っているんです。暗いジャングルのなかを……」と脅えたように言う。
国のためとだけ信じ、殉じていった若者たちが、今も亡霊となって現れてくるーーー。すでに士くれと化したはずの僚友たちは、一体何を訴えたいのだろうか。
私たちのような最前線での体験者は、手を合わせ冥福を析るだけではなく、自分の「行動そのもの」で戦争の悲惨さを、次への世代を担う若者たちへ伝える責務があると思っている。
この国が巻き込まれるであろう「戦争」は地震のように決して避けられない。人間の欲望が無くならないかぎり-‐-。だから、戦争を知らない世代の方たちは、「戦争史観」を掘り起こし、身につけ、変事に即応できる「自分自身の意見」を確りと持って欲しい。
このことこそ、六十年前散華し、日本の礎となってくれた彼らの「尊い死」に、はじめて応えられるのである。
敗戦六十年は語れても、七十年を語る人は少ない。あれほどひたむきに戦争の真実と「鎮魂」の大切さを訴え続けていた茂住さんも、二年前、八十二歳で波乱の生涯を閉じられた。
朝風100号掲載 2006.12月

フィリピン北部ルソン島戦闘敗戦記
激兵団戦車通信隊(旧戦車第二師団満州六八部隊)
河村 一朗
目 次
一、はじめに
二、戦いの概略
三、隊長が兵隊から泥棒
四、糾弾・戦没戦友
五、敗走―放浪
六、栄養失調と死
七、プログ山腹郭陣地
八、投降への道―投降
九、終局
付記・略歴
地図
1、はじめに
「戦争」とは、私なりに振り返り述べるに当り、先づその背景と立場を理解されたい。一つは自分はその時点に於ける「帝国軍人」であった。次の一つは現在「戦争」は十五年戦争・太平洋戦争・第二次世界大戦といろいろ呼ばれているが、私は「挙国一致」の「大東亜戦争」と深く肝に銘じていた。この戦いは日本を盟主とする「大東亜共栄圏」の確立であり達成でもあった。「鬼畜米英撃滅」すなわち欧米のアジア支配を排除する「アジアの解放」であり、ひいては「八紘一宇」のわが国の世界制覇の戦いである。それは「聖戦」であり「正義」の戦いでもあった。
自分はその尖兵となり真の「愛国者」となる決意のもとに、国民「一億一心」聖戦完遂の国情のなか、「日の丸」の旗と歓呼の声で勇躍志願のうえ出征した。これが当時の歴史的背景・情況の一端である、と云えば仰々しいと思われるが私の社会観・価値観である。
戦後四十年余の現在「戦争」への幾多の歴史的解釈・評価は、後知恵で残念ながら当時の自分の知得するところでなかった。以上の歴史的事実を前提にし自分の戦記を記す。「戦争」を直視するささやかな資料となり、また在天の多くの戦没戦友の追悼・慰霊となればという想いである。
2、戦いの概略
昭和十七年十一月、陸軍通信学校生徒隊を卒業(陸軍少年通信兵第八期生)、時に十八歳。直ちに旧満州(勃利)の戦車第二師団戦車第七連隊に配属。ついで同師団満州六八部隊に転属、六八は、戦車第二師団通信教習所ともいい、師団隷下の各部隊の通信兵教育・指導に当たり、また師団の神経中枢の構成組織である。十九年九月、動員が下り師団はフィリピン・ルソン島に派遣され撃兵団と改称、六八は、同兵団戦車通信隊(略して師通∥師団通信)と呼ばれた。軍曹の私は通信隊無線の一つの分隊の班長であった。
二十年一月、二年四ヶ月前、我が日本陸海軍の比島攻略作戦の上陸を展開した地域、ルソン島リンガエン湾岸に米軍の逆上陸である。レイテ作戦を終えたマッカ―サ|元帥指揮の比島ルソン奪回反攻作戦の開始である。このとき米軍の資料によると、その戦力は優秀な戦車師団を含む五ヶ師団十九万一千人、その日のうち四ヶ師団が上陸し戦闘、同湾に集結した艦船・輸送船等は九十五隻という大軍事力の投入であったと云う。
撃兵団は他兵団・部隊と共にこれを激撃、比島ルソン防衛作戦の火蓋を切った。米軍は激しい艦砲射撃と圧倒的装備を誇る上陸軍に優勢な戦車師団、さらに絶対的優位な制空権を以ての海陸空の砲爆攻撃の猛攻である。以下詳細な戦闘詳報は戦記物として多く出版されているのでそれに依られたい、撃兵団はこの激撃作戦の主力師団で果敢に守備・攻撃の応戦を繰り返した。が、何分にも多勢に無勢、その上にわが空軍の制空権のない師団精鋭戦車隊の激撃は、残念にもほとんど夜間機動の苦戦を強いられる劣勢不利な作戦であり、米軍の圧倒的軍事力に切歯扼腕である。それでも劣勢をカバーするに旺盛な体当りの敢闘精神でもって戦い、しかも撃兵団よく一ヶ師団にて最前線延長六十キロにわたる縦横無尽の勇戦奪闘の大展開である。その結果、約一ヶ月の湾岸激撃・防衛という当初の作戦目的を達成し、上陸米軍将兵にわが軍攻撃の容易ならざる苦戦の程を知らしめ、敵の心胆を寒からしめる成果をあげた。
なおこの作戦は世界戦史上まれな戦例といわれている。また撃兵団の精鋭戦車隊の一つは作戦遂行の戦歴を高く評価され、比島(第十四)方面軍最高司令官・山下奉文大将より感状を授与された。この作戦中、兵団旅団長・重見伊三雄少将以下隊員、戦車もろとも残らず玉砕した後のことと思う、私は隊長の師団本部訪問に随行した。ここではじめて師団長・岩仲義治中将の豪快な風貌と馨咳に接した。師団長は童顔を面にたたえられ、隊長に戦車隊と自分との長い関係というか経歴を語られ、今度の作戦をもって自分の戦車による最後の御奉公と満足の意を述べられていた。私はその会話を傍で厳粛な気持で拝聴した。
二月初旬、撃兵団はこの平野部作戦から北部ルソン山岳地帯に転進(後退)した。バレテ峠(鉄兵団∥第十師団)・サラクサク峠(撃兵団)を中心に日米両軍の北部ルソン攻防の激戦である。この戦いは四ヶ月余り六月初めまで展開され、わが兵団は先の作戦で戦車の潰滅的損害を受け、戦車師団としての軍事的機能を完全に失い、野戦(歩兵)師団として戦った。この峠の戦場でも米軍の圧倒的軍事力を思い知らされ、わが陣地では味方の空軍の機影を求めて空を仰ぐこと頻りである。しかし敵観測機は絶え間なくゆうゆうと頭上にあり旋回し、わが陣地の動静を偵察し、地上では物量に物を云わせての物凄い砲攻撃、見たこともないブルドーザーで山谷をけずり崩し道路の建設、その後を戦車・トラックによる進攻である。味方が一発でも発砲すれば敵の絶好の目標となり、迫撃砲等の数百発と思われる弾丸が集中豪雨のようにはね返ってくる。迂闊に銃の引き金に指も懸けられない、それでもわが峠の陣地は、先に述べた如く約四ヶ月の長期間堅く守備された。この戦いの頃になると食糧補給はもとより軍需物資の補給は全くないか、あっても形ばかりで自給自足の戦いである。その困難のなかで一進一退、如何にわが軍が敵の猛攻に勇敢、よく善戦したかを雄弁に物語るものである。兵隊のなかには敵前逃亡に等しい戦線離脱も見られる。峠の要所に検問所が設けられ、ここで将校に説得されて武器の給与もなく、丸腰のまま.再び陣地に追い返されている。
後日、撃兵団はこの戦いによって軍司令官・山下大将より感状を授与されたと聞く。わが戦車通信隊も兵団本部に所属し、上陸以来無線器材をもって各部隊の前線各陣地、また後方連絡勤務と、分隊班毎に派遣され移動散開して活動した。今日、なおわが戦車通信隊の戦闘詳報はなく隊としての戦歴は知るところでない。この戦いの最中、師団参謀長・森厳大佐が亡くなられ、自分は弔問の隊長に随行した。イムガンの砲兵陣地である。ただ一台の備え付けの大砲が敵陣地に弾丸をさかんに発射していた。砲声は暗闇の山頂に殷々と響きわたる、まさに参謀長の死を悼む弔砲の如きであった。
六月初め、ついにバレテ峠は米軍に突破された。続いてこの為遂に撃兵団もサラクサク峠を撤退、通信隊は山谷に添って北上しピンキアン谷地に移動した。米軍はバレテ峠から戦車を先頭にカガヤン河谷平地へ電撃的に殺到進攻、戦局は急転し、わが軍は潰滅的大混乱と敗走に落ち入った。通信隊はさらに北上しサリナスに後退したが、前方すでに敵の侵入により遮断され、挾撃を受ける危険にさらされた。.六月中旬頃、この危険を避けて北西方に向って山岳地帯に入る。通信器材を水牛の背で運搬、折悪しくの激しいスコール、山道は雨でぬかる急な坂である。水牛は器材の重さとぬかる坂道に足をとられて滑り、もんどり打って器材もろとも谷底に転落した、この時点で戦車通信隊の役割は終った。
3、隊長が兵隊から泥棒
この頃、すでに早くサラクサク峠の戦いより食糧の支給はなし、飢えとの戦いが始まっていた。それでも兵隊は各自何んとかして若干の米・塩を調達保持していた。僅かとはいえ彼らにとっては命の綱であり心の糧でもあった。兵隊が炊事に当るを見ると、最初は米飯であったが、保有も限度があり米の利用に工夫が生れてくる。フィリピン米は粘りなくもさもさである、飯盒に一合位の僅かな米で炊くなかで何回も水を入れて炊くと、米飯は飯盒の半分以上にも増え、空腹を満たす。そのうち米の支給に期待がもてなくなり戦いの合間に野草の拾集で雑炊、それも今となっては飯粒が数えられる位となっていた。
ところが隊本部では食糧をすでに消費尽くし、隊長は「米を持ってこい」と公然と恥も外聞もなく執拗に命令(要求)、また伝令まで寄越す請求振りである。この前まで隊長は何処で手に入れるのか入れたのか、天幕のなかで飯盒一杯の真白い御飯を食し、たまたまこれを目にした兵隊を驚かせている。兵隊はとにかく供出命令に驚き頑として忌避する、供出する程持っていない。自分は兵隊の意に応えて「米は有りません」と大声で復命した。大声は本部との間に若干の距離があったからである。付近に散開している他の兵隊も驚き、この成行と様子の結果如何をうかがっている。付近は緩やかな傾斜の山腹で松の木立が一本一本点在し、一見懐かしい内地の風景を思わせ、心の安らぎを感じた印象が鮮明に残っている。このあと何事もなく普通の通り本部の後を追って進んだ。激しいスコールのあとの熱帯太陽の焦熱、敵観測機の頭上の旋回、それによる敵の攻撃を想定する切羽詰った不安、また必死に急峻な山道を喘ぎ登る苦しさ、これらが重なってみな心身とも疲労困憊の極であった。たまたま林に囲まれた、一寸した平な広場の草原の林の陰で分隊毎に休憩のところで、突然、集合の命令がかかった。「所持品はそのままにして全員集合」である。自分は所持品に不安を感じて、再度、命令を確認するとその通りであると。
甲種幹部候補生あがりの将校の命令・指揮・号令で整列・点呼・宮城揺拝・軍人勅諭斉唱・柔軟体操と、続いてこの新品将校の要領を得ない甲高いうわずった訓示が長々と続行される。かかる形の整然とした集合点呼は上陸以来何ヶ月振りである。それまでは分隊班毎の「異常ありません」の報告をするだけであった。集合の間、陸士出身の颯爽としていた隊長は、他の将校等とともに全然姿を見せない。指揮は終始この甲幹チンピラ将校である。全員疲労と空腹で頭は朦朧、やっと長い点呼と訓示の集合が終り解散、ホッとして所持品の場所に戻ると、所持品入れの背負袋・雑のう、そして飯盒まで荒され散乱し、米・塩がきれいに盗まれている、山中の盗難とは考えてもいなかった。今後の行動から考えても、何時まで保持できるか分らない僅かな米・塩である。丁度、塩はこの出来事の前、スコールによって不注意にも溶かし流してしまい、同僚の戦友の厳しい注意と再度の分配で一人親指ほどの量であった。ほんの僅かといえ、大切な食料の盗難を知った兵隊は、その瞬間、ビックリ仰天。それはがく然、呆然自失、一同「ああっ」もう叫びというより喉より絞り出す呻きで言葉も出ない。いっとき、涙も出ない鳴咽とため息が続く、異様というか不気味な雰囲気である。やっと自己を取り戻し、盗んだのは他の部隊の兵隊か、原住民の仕業か、比ゲリラ兵か、そんな形跡は何処にも見当らない、死に物狂いであたり近辺を探し廻るが後の祭りである。本部を覗いてみればもぬけのからで出発の後、出発について何も聞かない指示もない。兵隊はがっくりと肩を落し、物の怪に取り付かれたようになったが、諦めたのか気を取り直したか、再び、我れに帰り本部(隊長)に遅れては大変と、今まで何事もなかった如く、真剣な顔で急ぎ懸命に後を追う。その夜、同僚がそっと耳打ちしてくれた。唖然、なんと驚くことに泥棒が隊長とは。隊長と将校が全員集合させたうえ、彼らだけで兵隊の所持品をあさり米・塩を奪ったのだ。そう考えれば先の米・塩の汚い要求、全員集合に於ける「所持品はそのまま」といいおかし気なことばかり、それに隊長の天幕(休憩)の位置は葉の繁茂する灌木に遮ぎられ、われわれの位置とほんの目と鼻の近くだ。「上官の命令は天皇の命令」「上官の命令は絶対服従すべし」を逆手に取った意図と魂胆による、計画的行動(犯行)だったのだ。そのうえに彼らは部下に今後の行動も行先も何も説明もせず告げず、夜逃げ同然に去って行ったのだ。すでに遠く逃げたのか影も形も見えない。
兵隊は隊長・将校のかかる部下を欺むく卑劣行為と見捨てられ置き捨てられたことは全く知らない。知らせるには余りにも衝撃が大きい。かりに知っても部下には上官に反抗する術も無い、かかる仕打ちに甘んじて耐えるしかない。なお、これより先、自分の分隊はサリナスより他部隊の戦うピンキアンに派遣された。再び帰隊でとって返すとき、同期の戦友が隊長・将校の理不尽な横暴と万魁の恨みを語り、終りに「貴様も隊長・将校に注意しろ」と。自分は彼の上官に対する批判と反抗的言動、そのうえ帰隊拒否に動転した。懸命に止めたが聞かず、闇の中を敵の方向に飛び込んで行った。いま同期が別れに残した注意しろの言葉が痛切に胸をつく思いだ。隊長へ行方不明を報告、同期の行方不明に何んの質問の言葉もない、去るものは去れか。これから米軍に投降収容されるまでの約三ヶ月近く、山中離散の衆と化し、飢えによる生死の極限状況、原始的な難苦行の放浪の戦いである。
4、糾弾・戦没戦友
隊長は陸士出身の少佐(当時)、職業軍人のエリート、父親は陸軍大将、れっきとした名誉と栄光に輝く大日本帝国軍人の名門である。それが軍人として「米を持ってこい」でさえ恥だと思われるのに、兵隊を騙し打ちで食料を盗み、そのうえ「皇軍の兵士」「天皇の赤子」を棄て去り、つぎつぎ哀れな餓死に追いやった。これが「皇軍」の指揮官か、「国賊」もいいところである。当時、比島決戦の声高く大東亜戦争の天王山と呼号され、激戦(敗退)また激戦(敗退)と、まだ決戦はこれからだというプログ山腹郭陣地による反撃の意気込みの時であった。通信隊は最前線から見れば距離の長短はあれ後詰で、敵との隊を挙げての接触・直接の交戦は一度たりとなく、兵隊はみな銃と弾丸に手榴弾を保持する完全武装で一戦を交える戦闘能力あり、軍隊であれば当然とはいえ、まだ戦意もあり個人的覚悟(決死の覚悟)もしていた。また戦争全体の作戦・戦況は兵士の承知するところでないが、ひたすら「聖戦」必勝と「神国」日本の勝利も確信していた。そういう時点、「将校は部下を指揮掌握し、帝国を守護する責任と任務」を持つという、「将校の本領」を放棄し自分らだけ生きのびるつもりであったのか、卑怯者と云うより常軌を逸する狂気の沙汰以外の何物でもない。事実、わが隊の将校全員無事生還だ。
兵隊は隊長・将校を「武士道」の権化とも「神」とも思う尊敬と信頼をもち慕い寄りかかっている。戦いの中では一層である。常日頃からその挙動と措辞から勇気と喜びと、他人事でない頼り甲斐と面倒見に魅力と安心感を抱いていた。また、云うまでもなく上官の「命令」「指揮」は絶対であり、兵隊は云われた通り死地に飛び込んで行く忠誠という、強い精神的関係にある。その統卒能力はどこへいったのか、なぜ適切な命令、指揮の行動と手段が執れなかったのか、無能というには余りにも職業軍人にあらざる破廉恥行為である。さらに兵隊をつぎつぎ置き去りにし決定的敗残敗北の身に落し己の犠牲(人身御供)にしたのだ。全く部下の期待を裏切る殺人的行為である。続く放浪の二ヶ月余りの間、事実、隊長・将校の姿・顔を見ることも声を聞くこと一度もなかった。
その間、山道の途中に於て戦友・他隊の兵隊達を含めて多くの兵隊が、浮浪の身同然となり倒れまた取り残され、・悲しいかな空しく「菊花紋章入りの銃」を掻き抱き餓死を待つを見る。これが兵隊の「忠君愛国」、「滅私奉公」の姿、上官に対する誠実と心服の結果であろうとは考え及ばないところであった。
通信隊全員百四十余名、前線に派遣され本当に戦傷死した同僚・戦友もいるが、戦死者六十余名の七割は置き去られ見捨てられるか、身心の疲労と焦躁が重なり、遂いに飢えによる餓死である。それも遺棄された。軍隊では将校にあらずんば人に非ずか、「下士官・兵は消耗品」と云われ人間扱いでないのだ。「山行かば草むす屍」「醜の御楯」の字句通りであり、死者は寂として声なしである。それにしても誰にも見て取られることなく唯一人苦悶の末に餓死とは悲愴・無惨の極である。その「地獄と死の道」はサラクサク・ピンキアン谷地・サリナス・アンチポロ・キアンガンに至る土人道である、人間の「畜生と餓鬼の道」でもある。
5、敗走・放浪
敵地で異境の山岳地帯、地図もなく全くの地理不案内、オマケに頼りの指揮官は逃げ去り居所不明。また上空には敵観測機が執拗にわれわれを追跡偵察する、こちらの動静は敵に明らか、いつ襲撃か砲爆弾を受けるか、心細さを通り越しての絶望である。自分はどうでも成れという自暴自棄気味、それでも分隊として行動する戦友(兵隊)もいるのだと思い直し、気を振り絞り他の部隊・兵隊の移動もみられるので、その進行と方向を追って進む、それは宛先のないわが師団の目的集結地に、また不明のわが隊の本部に合流、到着できると思ってのことである。そのうち敵観測機の出現も止まる、敵の攻撃の危険を脱し山中深く踏み込んだようだ。山岳地帯は標高一千メートル以上の山々であり、熱帯とはいえ平野部と違い高度による低気温、熱帯性独得の植生・果樹は見られず小動物の生物も居ない。夜間は格段の肌寒さ、日中でも雨の続くときは冷雨による肌寒さが身にしみる。もう戦いのことは忘れて頭で考えること戦友との話は喰う食べることである。食べられる野草を拾集し腹に入れる、はじめ慣れるまで生の野草は口が受付けない、食べられるものでもない、無理に口に入れても噛めない、呑み込もうとするが喉も通らない、飯盒で煮てどうにか腹に押し込めるのである。この野草拾集と煮炊は、単独の落伍兵や傷病兵には身一つなので自由な動きもできない、下手に行動すれば山路を外れ山中に迷い、また誰の頼みも助けも叶わないので栄養失調を待つまでもなく餓死である。栄養失調で餓死寸前で助った多くの兵隊は、何人かの行動による元気な同僚の親身な(戦友愛)野草拾集と炊事によるものである。野草は春菊・よもぎ・ばせう・すべり草・唐辛子等々で、唐辛子が塩のかわりの調味料・食欲増進剤である、味も素気もない食事で米・塩に対し痛切に適わぬ欲望を抱いた。たまたま見かける原住民のさつま芋畑はすでに掘り尽くされ、先行した兵隊に荒され、残っているのは葉っぱと茎だけ、これも結構な食料でいよいよ草食動物の生活である。
険しく深い山谷をつぎつぎ越え、こんな野草食を毎日毎回いくら食しても飢餓(空腹)状態が続き間違いなく栄養失調に落ち入る、それに加えてマラリア熱・脚気・下痢(赤痢)等の合併症の蔓延である。進むほどに飢えと疲労で足を引き摺り歩く、腕に力を入れた杖で体を支える、誰も腕や肩を借すものはいない、みな体力消耗である。動けない歩けない兵隊は落伍者として取り残され力尽きて、誰にも見てとられることなく行倒れ(屍)の野ざらしである。傷病兵にいたっては最初から哀れな落伍者である、傷口は剥き出し膿が流れ蛆がわいている、包帯していても包帯は黒づんだ血で固まり、見るものをして目を覆わしめる。歩ける者は必死に進む、先行した同僚が路の脇にうずくまるに出合う、本人は衰弱甚だしく立ち上れない、寒さに鼻水を垂らし大粒の流れる涙でくしゃくしゃの顔をあげ、カ細い声で「連れて行ってくれ、頼む」と哀願する、こちらも自分の体を支えるに精一杯で余力はない、元気な戦友でも居ればと思う。心にもない空しい慰めの言葉「後ですぐ迎えにくる、待っとれ、頑張れ」を掛けてそのまま離れ去る、二度と会うことのない全く気休めの文句を残しての別れである、太陽の熱い日で同僚の眼鏡がやけに光を反射して輝いていた。
進む先々、子供のように深く喉から息を吐き出すように泣きじゃくる兵隊、同じように涙も枯れ何を聞いてもひくひぐ顎を前後してしゃくっている兵隊。倒れて路のそばの木陰に長く伸びている兵隊、まだ息があり胸が波うっているが意識はない、軍靴も剥がされ所持品も持っていかれている。元気な兵隊は追われる如く、この有様に、何んの関心も無く前を急ぎ進む。ところがその急ぎ通り過ぎた兵隊が今度は自分が倒れ、落伍し坐り込み連行を哀願する、そのまま取り残され死を待つという繰り返しである。進む程に落伍兵の姿は死体に変る、死体は腐敗甚だしく脹れあがり、軍服はピンと張りボタンがはじけ飛ばんばかり、面体はヒョットコ面で誰であるか、戦友の見分けもつかなくなった。さらに腐敗の進んでいる者は、顔の肉は崩れ黒い皮膚の残る骸骨と化している。この生き別れ死に別れの有様が、目的の集結地への方向指示標識であり、各自の死に至る過程と死に様である、また各自最後の「死の墓標」である、戦いの「敗走」とはかくの如きであった。
自然の障害もある。熱帯独得の雨季による増水の渓谷を渡る。流れは猛る濁流で危険このうえない、目前で徒渉に失敗した兵隊が激流につぎつぎ流され、川中の岩石に叩きつけられ、二度と流れから姿を見せない、恐怖の一瞬が繰り返される。が、何んのこともない誰も無表情、無感動である。移動の動物・追われる動物の群が河川に飛び込み渡るように、兵隊は濁流の流れに身をまかせ、渡る流される。兵隊はこのようにバタバタ倒れる、その死と屍にほとんど無感覚になった。死者はそのまま遺棄され誰にも合掌されることなく、落伍兵には声を掛けることもなく、一瞥して黙々と行き過ぎる。言葉を交しても、問いは「ここは何処で」「今日は何日で」「何隊で」「何処へ行けばよい」「この部隊を知りませんで」、その答は「わからないで」「知らないで」とかいずれもこれらの問答に「・・・・あります」を付し、この二、三の言葉による短い挨拶程度である。行き過ぎ振り返れば、哀れ落伍兵の目が追っている、何かを訴えようとするかに目が涙で光っている。
落伍兵は「連れて行ってくれ」と云うが「助けてくれ」とは吐かない、徹底した軍隊教育の賜である軍人精神が、心の片隅に残っているのだろう。所定の前線守備陣地から離脱した兵隊、また戦いの中で自分の師団・部隊から分断されてはぐれた兵隊は、脱走兵(逃亡兵)扱いである。将校に発見され訊問を受ける兵隊が自分の所属部隊を答えた途端に、理由を聞かれないで頭ごなしに怒鳴り付けられている、結果、どの隊にも収容されることなく放任である。兵隊はがっくりと肩をすぼめて立ち去るが、林や草むらに見え隠れしながら将校の姿を避け、われわれ師団の後を追っている。将校たちの兵隊への残酷な虫けら扱いかくの如きであるのか。たまには珍らしい情景もある、部隊として固まり、上官よく兵隊を叱咤激励、互に協力させて引卒している。しかし落伍と見なされば死者同様に遺棄されるに変りない、まだ意識あり動けないばかりに一層哀れというべきである。同じ師団であっても自分の部隊の兵隊以外の他部隊の兵隊には目もくれない、他師団であればなおさら相手にしない邪魔扱いである、万事が勝手で他人事である。強固な団結を誇る日本軍も烏合の衆と化し、山中の猿の群にも劣る群と化したのだ。力尽き倒れ、置き捨てられ、見捨てられ、自然に遮ぎられ、また道に迷い別れ別れになり、栄養失調に罹かり、最後は屍となる。まさに「敗走」は「死の行進」である。
6、栄養失調と死
栄養失調ははじめどんどん痩せ細り骨皮となる、ついで顔よりまた足から上下の何れからか浮腫み水脹れになる。太股を親指で圧すと親指の付根近くまで深くめり込み凹みのあとがつく脚気という。軍靴も履けない足になる。ひどくなると足の甲皮が裂けて裂口に蛆がわく。男性のシンボル(睾丸)もゴムマリのように脹らみテカテカの光沢を放つ、汗をかき塩をふき痛いので谷川の水で洗う。田舎の年寄がよく云っていた「頭とキン玉は雛がないと役に立たん」「頭とキン玉は若いうちに使え」の言葉を思い出してこれで人生の終りと苦笑。頭髪の伸びは止り薄茶色となり、虱が喰い込んでいる。身体は全面に疥癬とその瘡蓋である。軍服は虱の巣、虱つぶしは指では間に合わず、縫目にそって丸石でこすり叩いて潰す、薪火の上で軍服を乾かすと熱気で虱が落ちはじける。毎日の定刻にマラリア熱、はじめ激しい全身のガタガタふるえの悪寒(寒い寒いの)発作が続く、続いて体温四十度以上の熱発(暑い暑いの)症状である、苦しみ体の衰弱を一層加速し気をも狂わす。大便は緑色(野草色そのまま)のゼリー状の便、食の度に便で直前に食した不消化のまま、腹の中のもの全部が排便される大盛である。便が終ると食い、食うと便という繰り返し、食っても食っても空腹である。下痢(赤痢)も大変だ。下痢を催し終って立ち上るとまた催す、始終立ったりしゃがんだりでまことに忙しい。腹痛を伴うので口を喰い縛り、顔をひん曲げ天を仰いで踏ん張る。終いには垂れ流しでズボンは汚物だらけのまま、下痢止めに薪火の炭をガリガリかじり便は真黒となる。負傷兵の傷口は剥き出しのままである。傷口は膿が流れ蛆がわいている。蛆も死体と生ける者では種類が違う。死者の蛆は動物の死体と同じコロコロであるが、傷の蛆は真白い細く軟かい短い蛆である。しかもべったりと傷口にへばり付いている、始末は自分で谷川の流れに膿とともに洗い流す。兵隊の栄養失調は以上これらの合併症である。また生死の極限状況にある体調であるので投降したとき助かった者の体重をみると、甚だしい者は、三分の一位に減り二十キロ前後である。
この栄養失調状態のなかで最後の餓死となる。横臥して立ち上ることも出来なくなると終りであるが、終りの死の予知と予告もある。死直前の兵隊の周囲を見ると、兵隊の体の生血で生きている虱が早々と逃げ出して、隣の生の長いと思われる者にぞろぞろ移動している、虱による死の予告である。またその吐く息は鼻をつく強い動物の腐臭(死臭)である。それは頭が痛くなるような嘔吐を催すような強い悪臭の発散である、死の前にはすでに体内の腐敗が進行しその臭いが吐きだされるのだ。長い間の横臥で起き上ることもできず、全く周りの者に苦痛も悲哀もかこつこともできなくなった者が、突然、元気に起き上る、気味悪いぐらい気分の爽快を述べ、楽しそうに周りに談笑饒舌、終って再び横臥する、死の直前には全身の神経が麻痺し苦痛を感じないのだ。いづれの現象も死の予知となる。このあと全く意識を失ない、短時間のうち周りに気付かれることなく、静かに眠るが如く息を引きとる、明日はわが身である。峻瞼な山中で人跡未踏の僻地に、この有様で朽ち果てるは残念無念と云うより悲愴である。
7、プログ山腹郭陣地
放浪の記述で死への過程と状況を、放浪の終局まで述べたが、再び自分の放浪の終局への動きに帰る。八月中旬、五里霧中、右往左往の彷徨であったが、何んとか他の部隊と兵隊の後を追って集結地(本隊)南アンチポロに到着した。プログ山腹郭陣地の一つである。陣地らしい防禦施設は見られない。あちこちで他隊の兵隊同士の感激(?)の再会、上官の慰労激励を受ける兵隊の点景が見られる。その一方で戦いの後、長期の焦躁と疲労による栄養失調、くたびれた垢と泥まみれの軍服に裸足の乞食の姿同然の兵隊が多い。ここまで来て頼る隊も戦友を知る術もないのか、路端に坐して前を通る兵隊の後姿を、物恨めしの表情で寂しそうな目で追っている。また前を通る者から何か言葉を掛けてくれるを期待するかの様にも見える。わが通信隊本部も居所不明である。本部・各分隊班毎に散在しているのだ。体力も限界で尋ねる気力も報告の必要も感じない。そのうちぼつぼつ戦友から折角ここまで来て同僚の先輩・戦友がただ涙にむせて死んだ悲しい知らせが耳に入る。足の向くまま行き当りバッタリでうろうろしているうち、隊長の宿舎、原住民の高床式の簡単な竹材家屋を尋ね当て到着の報告に行った。
隊長はすだれ越しに坐ったまま半身を乗り出した。自分は隊長の顔を見上げた途端、報告の言葉も出ず悔しさで涙が込み上る思いと、腹わたが煮えくり返る体の血の熱さを感じた、隊長の顔を直視するだけだ。隊長は無言で頭をひくひく前後に動かし鼻あしらいの様子、命令、指示も部下への鼓舞激励、慰労の言葉もない。「戦いの終り」も耳にしている。自分は心でこの馬鹿野郎何も知らないと思っているのかと、ただ上官の手前、その畏怖の念から恨み怒る心の行場もなし、我慢悄然と退去した。このとき本部近くに同期が野営していた。自分の哀れ惨めな乞食同様の姿に同情したかどうか、ネズミの尻尾の先ほどの青唐辛子を二、三本差し出し恵んでくれた。自分は思わず無言で受取った。唐辛子は今では塩にかわる貴重な調味である。嬉しかった有難いと思った。受け取るに返礼の言葉が口から出ず、このあと、その辛味で心を取り戻したが、自分が飢えに取り付かれ餓鬼に落ちている情無さに思わず涙した。
再び宿営の場所を北アンチポロに移動する。急な坂道の山越えである。越えると目前に横幅のある滝が見える。健康な兵隊が気持よさそうに快晴の空の下で水浴を楽しんでいる。その前を通り過ぎ、原住民の段々畑(棚田=水田)が勾配の急な山頂から深い谷に広がっている場所に出る。水田の稲穂は刈り取られ根株だけ、この棚田の山の中腹に野営である。野営は何の設備もいらず、木陰にごろりと野宿で、けもの同様に身一つを動かすだけだ。周辺は日当りもよく、見晴しの展望の開けた位置で、気分的に爽やかさと安堵を感じた。あまり展望がよく前方に敵あれば、こちらの動きは明らかで攻撃の目標となり易いことが懸念されたが緊張感はない、本当に戦いは終ったのだろうか。不思議に危険とか恐怖を感じない、むしろ矢でも鉄砲でもこいの開き直りである。いつか知らぬ間に、近くの原住民の草葺きの平屋に隊長(本部)が移っていた。自分は報告に行くでもなく、足を引き摺って顔を出した。隊長、将校以下珍らしく本部全員顔を揃えている。土間に枯れ草を深々と厚く敷きつめ、部屋の奥に雁首を入口に足を向け、木偶坊のように並び、なんと元気に気持ちよく寝転んでいる。自分の姿を見て一斉に顔を向ける、隊長はじめ誰も立ち上ることもなくひと言の口も開かない。ただ彼らの顔には、様を見ろ、くたばりそこない奴と云わぬばかりの嘲笑の面構えである。自分も立ったまま無言のままである。屈辱にさいなまれた悔しさの思いに、怨念と憎悪が沸々とたぎる。自分は彼らの汚い面、蛙の面に小便の馬鹿面の一人一人をじっくりとなめ廻し、忘れまい許さないぞ死んでなるものか、また死んでも必らず戦没戦友と共に復讐と怒りの神とならんと、脳裏に焼きつけた。捕虜収容所病院で自分の姿を鏡に写し、その裸姿に青春の面影はなく、オランウータンの子供そっくりで、われながらその哀れな老化の異形さに驚いた。
8、投降への道ー投降
九月初旬、山中がにわかに騒々しくなる。今まで見掛けなかった兵隊の動きと往来が繁しくなったのだ。彼らの動きで、「日本は負けた」「戦いは終り」と、ここではっきり大日本帝国の敗北と崩壊に終戦の一端を知る。この情報が山中を駆け巡っているのだ。自分らもなんとなく落着かない。しかし衰弱し気落ちの同僚の戦友にも往来する兵隊の動きにも、心なしか軽よさを感じる。それにしても隊長(本部)の指示・命令・連絡は依然として皆目無しである、本部は何処かに引き払ってしまった。戦友が夢遊病者のように立上り歩き出す、何を云っても聞かない、通る他隊の兵隊の後を追うのである。歩くうち野戦病院があると聞く、場所不明のまま行き着いた。野戦病院は建物も天幕も無く、野天の傷病兵のたんなる寄場で、林の中のじめじめと湿った日当りの悪い場所。幹部候補生見習士官の軍医一人、衛生兵も看護婦も居ない。医療器具・薬品・包帯もガーゼも無い、薬品と云えば赤チンキ、器具は軍医の持つメスだけである。患者は負傷者少なく、栄養失調者が多い。負傷者は早く途中で治療手当もなく落伍し倒れたのだ。栄養失調者の治療は浮腫んでいる足のくるぶし付近を消毒もせずメスを入れ切開、痛みも出血もない、あと赤チンキを塗布、自分の巻脚絆を包帯がわりに自分でぐるぐる巻くだけ。同僚には医療の医の字もない、注射も投薬の薬品もないのだ。傷口の手当は赤チンキの塗布だけ、膿や蛆の除去にもならない、包帯もなく傷口は剥き出しのままである。療養は食事、各自の自給自足で、横臥している者は餓死を待つばかり。動ける者は食料を求めて、長居は無用と早々に一人何処へか退散する。入退院と餓死は自分勝手次第である。病院(傷病兵)の前を堂々とした恰幅の司令官・山下大将が通過する。誰も将軍に対し起立・不動の姿勢も敬礼もしない、ただ目で見送るだけ、厳格な帝国軍人の規律・態度も形骸化したのだ。将軍は降服調印の為キアンガン下山の途次であるという。
九月中旬、投降の部隊・兵隊の群が繁くなる。群につられて自分らも野戦病院を抜け出し、群の後を衰弱した体で歩む休むの小刻みで足を運ぶ。歩ける動ける群が軽くどんどん追い越して行く。そのうち山中に珍らしい洋館の建物に行き当る。建物内部はがらんとして調度品も何もない、その内部は病院と同じく傷病兵のたまり場である、しかし軍医も指揮者も居ない。また傷病者は甚だしく衰弱し死の宣告されたような者ばかりである。すでに死体が彼らの横に点在している。面倒をみる者はもとより、周りの者でも片付ける体力もなく死体と同床異夢である。まさに集団「死の墓場」である。全員みな食を摂っていない、炊事も見られない、どん底に喘いでいるだけである。野戦病院と同様、お互の会話と云えば、「腹一ぱい、米の御飯」「白い御飯」「塩を舐めたい」と、食への悲嘆と渇望の反すうである、もう何も話せない衰弱の者もいる。それに加えて、建物の前の路が投降への道であり、投降の群の通過を見つめて「日本に還れる」「日本で死ぬる」と云う、いつどのようにして生還する当もない切ない望みと、淡い望郷の話が交される、隣のものとの会話は意識ある者の寂しさを紛らわす楽しみである。
そのうち投降する部隊の群に銃も帯剣(ゴボー剣)も所持せず全く新調の軍装、重そうな背のうの列を見る、自分らの服装は汗と垢と泥だらけ、下は糞の垂れ流しの汚物まみれのズボン、群の列は一見、みなの目を引く、物の有る所には有るものだと驚いたりと、この列に向って兵隊の一人が突然「連れて行ってくれー」と悲鳴とも思える悲痛な声をあげた、これを合図に他の兵隊もつられて一斉に連呼哀願する絶叫の大合唱となる。横臥したまま、坐したまま、なかには起き上り転がりながら、さらに建物の外に路にいざり這い出る、声を絞り出し手を振り必死に連行を懇願、その絶叫、喧騒は山谷にこだまし響きわたる。仰向けに横臥し声も出ないが意識ある者は、胸元で固く両手を組み合掌の形で、天井に上向きのまま両手と体をしきりに揺り震わしている、断末魔である。しかしこの部隊も、後続するどの兵隊の群も何処吹く風と早足で行き過ぎ振り向きもしない。この世の阿鼻叫喚の地獄図絵である。この打ちひしがれたあと、兵隊たちはもう子供のように身をよじり泣きじゃくる。なかには涙も声も枯れ握り拳で坐した両股を、伸び臥した者は土の上を叩いて哀しんでいる。まさに餓鬼の姿である。なお力を振り絞って立ち上った兵隊は、うつろな焦点の定まらない目を見開き、ふらふらの放心状態で後を追う、地獄から這い上る亡霊か亡者である。これも数メートルと歩かぬうちつぎつぎと倒れ二度と立ち上らない、絶望のうめきとため息が低く地底から湧くように流れる、彼らの呻吟はいつまで続くか、死だけが待っている。悲運に見舞われたと云うには、余りに冷酷無慈悲である。自分も同僚も立ち上り歩く。何処まで歩けるか行けるのか、あてのない投降に生きる夢を託し必死に歩を進める。彷徨とこの建物、先の野戦病院のその後の兵隊、戦友の消息、模様は杳として知るところでない。唯、聞く「戦死」「戦死者」の二、三字である、餓死者の戦没月日は出鱈目が多い、これらの兵隊の死に誰が立合い確認したのだ。
同僚ともども、もう二日三日も食を口にしていない。この前、まだ元気な同僚の戦友から厳しく食を摂ることを注意され勧められたが駄目だ。どのくらい歩いたか、自分も同僚も精も根も尽き果て道端に坐り込む、同僚は横になり気息奄々ついに、息を引き取った。意気消沈、自分も終りだ駄目だと、遺体の傍でうづくまり顔を伏せてぼんやりしていた。人影が自分の前に近づいたので顔を上げる。丸腰の兵隊が四人か自分を見下しながら、周囲をしきりにうかがい警戒している。彼らのような兵隊に放浪の道で何回か近づかれ話し掛けられ同行したこともある、彼らは戦線離脱兵かはぐれ兵隊だ。自分にいま近づいたのは戦線離脱の鉄兵団の兵隊である。彼らについては放浪の過程で話を聞いている、その話によるとバレテ峠を米軍に突破された際、師団は東方に、はぐれた兵隊は西方にと峠で分断され、前線基地を離れたとき、撃兵団撒退方向に紛れ込んだ、どの部隊にも収容されず、見つかれば所属部隊を聞かれ答えると、理由は聞かれるまでもなく、即座に脱走兵(逃亡兵)扱い、厳しく咎められ、罵詈雑言の気合で、帰る方向も道も原隊不明のまま止むを得ず身を隠すようにして、撃兵団と行を共にしていると。また彼らの戦線離脱は米軍の進攻により守備陣地に取り残され、米軍の攻撃なく弾丸も尽き陣地の役割がなくなり離れただけで、脱走でも逃亡でもない。取り残され後方には味方もいないと、以上の話である。自分らの境遇と似たり寄ったり、見捨られ置き去られたことに何の変哲もない。
ところで彼らは「戦争が終った」を耳にして出てきたが、指揮官も居ない、これからの行動にどう対処したものか判らない、そのうえ身の置きどころなく、どの隊にも収容されず、脱走兵扱いされ心配の種ばかり。自分に何処へ行くかを話し掛けてきた。自分は投降の途中であると話を切る、話す話も気力もない、何も彼らの必要・助力を感じなかった。彼らは周囲をうかがい何か相談と思案をしている。自分は衰弱と疲労で頭もかすみ、彼らの話は聞きとれない、気になり煩しいので長い時間を感じる。時々、前を通る投降の群を警戒し話を中断する。話が決ったのだ。彼らは自分の銃と帯剣を取り上げ外し他の兵隊にあずけ自分を身軽にする、二人の兵隊は自分の両脇を抱えあげ助けるようにして、自分の無惨な姿を先頭に立て投降に同行するのだ。自分ははじめ身ぐるみ裸にされると驚いが、彼らは自分を班長に祭り上げ、撃兵団の兵隊に化け、自分の分隊員に早変りしたのだ。自分は一瞬助かると蘇生の思いだった、長い道だったが彼らの激励・気合を受けながら引き摺られ無事キアンガンに運ばれ、銃も帯剣ももとの通り返され身に付けられ道端に転がされた。彼らの欣びの別れの挨拶に自分は言葉なく無言であったが、彼ら兵隊たちは米軍に収容される投降の列に、心も軽やかに元気よく潜り込んだ。終始、戦い・放浪で長い行動をともにした同僚の戦友はそのまま遺棄した。どのくらいの時間が立ったか、うづくまる自分の前に、自分の班の唯一人元気な同僚が現われた。しかし仲間の戦友の死と遺棄に激怒の言葉を投げ残して去った。同僚同志と一日の僅かの時間のなかで、彷徨の終りにきて、なほ同僚との惨めな生と生死の決別とは、自分の生涯の最大の悪夢である。多くの兵隊・戦友の還らざる「ルソンの山谷」、冷酷非情、痛恨の生地獄、何をもって瞑目せよと云うべきか、己の生還を奇跡と思うが、頭に浮かぶのは無念の苦悩と悔恨の想いばかりである。
9、終局
他の傷病兵と共に米軍に収容された。傷病兵の多くは独り自力で、また戦友の助力で山中を下り投降した者である。山に放置され迷いさまよう兵隊・傷病兵の救出は聞かない。自分は他の傷病兵とともに軍用トラックに乗せられ、ついで無蓋貨車に移され、一路、モンテルパの捕虜収容所病院に出発した。途中の各所でフィリピン人の子供が待ち構え、裸足で走り飛び出してくる、わが軍によるか、戦いのなかでか、国土は破壊・荒廃され、家も親兄弟でも失ったであろう、泣きながらトラック、貨車に向って「ドロボウー」「バカヤロー」と、自分らに罵声を浴びせ、振り上げた小さな拳による投石が繰り返えされる。華やかな「日の丸」の旗と歓呼の声に送られた雄途の結末の空しさがこれである。鳴呼、名誉の帝国軍人、大日本帝国万歳、天皇陛下万才!
(昭和六二年四月二四日記)
筆者略歴
大正一四年二月生鳥取県に生まれる
昭和十三年三月山郷尋常小学校高等科卒業
昭和十五年二月陸軍通信学校生徒隊入校(陸軍少年通信兵第八期生)
昭和十七年十一月同校卒業。戦車第二師団戦車第七連隊配属(満州国勃利)、同師団満州六八部隊(戦車第二師団通信教習所)に転属
昭和十九年九月比島上陸、参戦。
昭和二十年十二月復員。


ガ島戦に生きて
伊東市 関野 治次
昭和十八年一月二十日午前十時、ガタルカナル島アウステン山守備の私達部隊は米軍の戦車を伴う海兵隊に包囲された。
守備隊本部には各中隊より拠点を死守して全員が玉砕した悲報が続々と報告されてくる。本部書記は迫撃砲の集中射で全員が負傷し動けるものは武川曹長と私だけになった。
正午頃、本部と大中隊の間に発煙弾が打ち込まれ、艦砲射撃と迫撃砲の集中攻撃を受け守備隊本部の「タコツボ」は約半数が吹き飛んでしまった。陣地内にあった樹木は全部倒壊し足の踏み場もない、そのなかから重傷者を捜し応急手当を行ったが、砲弾破片創のため傷口が数ケ所あり手の施しようがなく、皆出血多量で眠るように死んでいった。食糧も補給されず、医薬品もなく、栄養失調症となり、下痢、マラリヤを併発し、そして最後は砲弾破片創で死んでいった仲間たちに対し埋葬も出来なかったことを申し訳なく思う。
見晴台方面の海兵隊は午前中より更に増強され戦車四輛とジープ数台が確認された。
午後一時頃であろうか、支隊司令部より伝令がきた。撤退命令である。
守備隊長は各中隊の動ける将校を本部に集め撤退の要旨を次のように説明した。
「現在の戦況は皆の知るところである。守備隊は今夜半を期して見晴台及び「イヌ」陣地に対し総攻撃をかけ突入を計る。突入成功後は部隊主力と合流し再びルンガ岬の敵前上陸に参加する。動けないものは陣地に残置し最後まで戦い自決せよ。生きて虜囚の辱めを受けるな。」
長時間の飢餓の後がこの状態で進むも死坐するもまた死であった。
そしてその晩の突入目標も決定し死に対する整理もつき突入命令の来るのを待った。
向かい側のスピーカーが、君が代を前奏し、明瞭な日本語で次のように語りかけて来る。
「勇敢なる日本兵諸君、戦いは終わりました。武器を捨ててこちらに来なさい。暖かいコーヒーとパンやミルクをあげましょう。貴方がたの生命は条約によって保障します。今晩中にこちらに来なさい、明日は貴方がたの陣地を総攻撃します。生命を大切にして早く日本に帰りましょう。日本軍は飛行機も輸送船もなくなりました。貴方がたの食糧も近くなくなるでしょう。早くこちらへ来て休みなさい。そして早く戦いをやめましょう。」
このような効力のない放送をくりかえし続けている。すでに食糧も途絶えて一週間になる。調味料に使用していた海水も残り少なくなった。前回の海水汲みは、戦死者二名を出した。蟻の巣も、陣地付近は取りつくした。土色のトカゲも食べつくしいなくなってしまった。死の直前になっても食べることが脳裏から離れない。思うことは食べることのみである。
午後四時頃であろうか、大隊副官小瀧中尉に呼ばれ、部隊伝令として私と武川曹長は陣地を脱出し司令部に行くことになった。絶食同様の日が続き動くのも嫌な私達であったが、命令となれば仕方ない。命令の要旨を通信紙に書いた。
一、陣地変更命令は受領した。
一、守備隊は初志命令通りアウステン山の保持に専念し米軍を最後まで陣地に引き付け全 軍の犠牲になって働きます。
一、陣地変更は現状況では出来ません。動ける者をもって今夜半、前方敵陣に対し突入を計ります。配属部隊を含め約一〇〇名である。 以上
武川曹長は功績関係書類を、私は戦死者名簿を、それぞれ図のうに入れ、赤錆びた拳銃を刀帯にしっかりとくくり付けて、軍刀を杖代わりにし、スコールの霧を利用して包囲陣を脱出した。
丸山道を約四キロ位歩いたところで私はマラリヤの熱発で歩行ができなくなった。武川曹長に緊急伝令なので先に行くように促したが残って手当をしてくれた。
熱にうかされ死んだように休んで翌朝は早く目が覚めた。上空では相変わらず敵戦闘機の哨戒が続いている。
米軍の豆マイクロホンに注意しながら郷子林とジャングルの関を進み、敵の分哨らしきところに着いた。付近は缶詰の空き缶と食べ残しの食糧が沢山あったがすぐは手をつけず、しばらく付近の様子を伺い、安全を確認して給与にありついた。半月ぶりの食糧らしき食べ物であった。
夕暮れを利用して出発し郷子林を進むこと約二時間、海兵隊の砲兵陣地らしきところにつき当った。先頭の武川曹長が海岸の地形偵察、私が山側の地形偵察とそれぞれ区分して、落ち合う場所を決定し分哨らしき物の発見につとめている最中、海岸方面で自動小銃の発射音を間いた。若しやと思い落ち合う場所に待ったがこなかった。やむなく近くのジャングルに入り、明日まで様子を見ることにした。
翌朝武川曹長がやられたのを確認して(武川の死体を道路下に埋めた)先をいそぎ所属部隊を探したが不明であった。
連絡所らしきものがあるので行ってみると、同期生の牧野かおり支隊は昨夜撤退したという。この時初めて部隊の撤退が分かった。
私も第二回目の撤退に間に合いボーゲンビル島で部隊の状況報告をし任務を終了した。
朝風1号掲載 1988.2月
